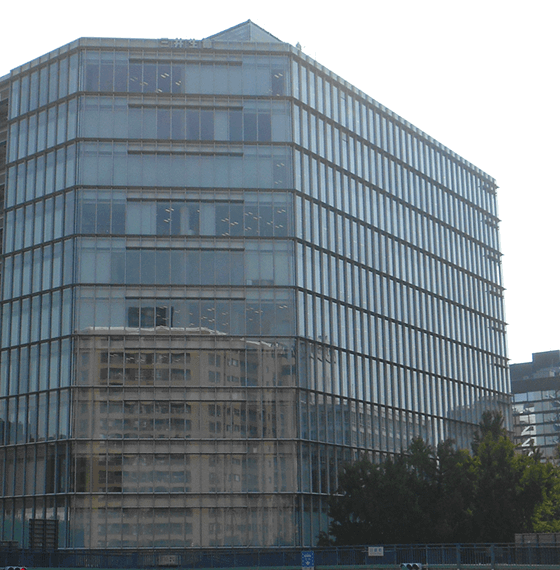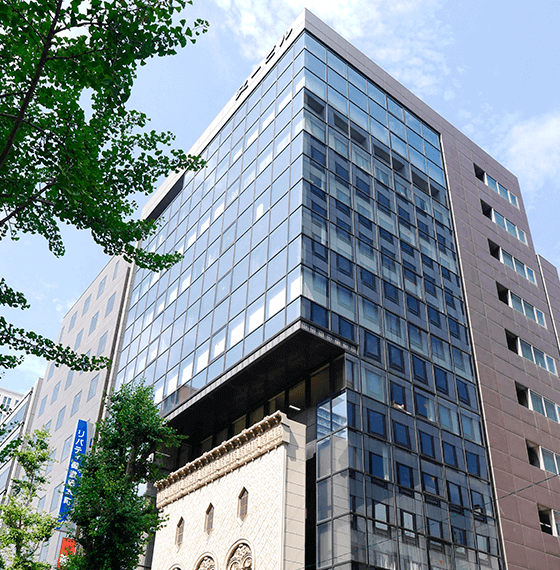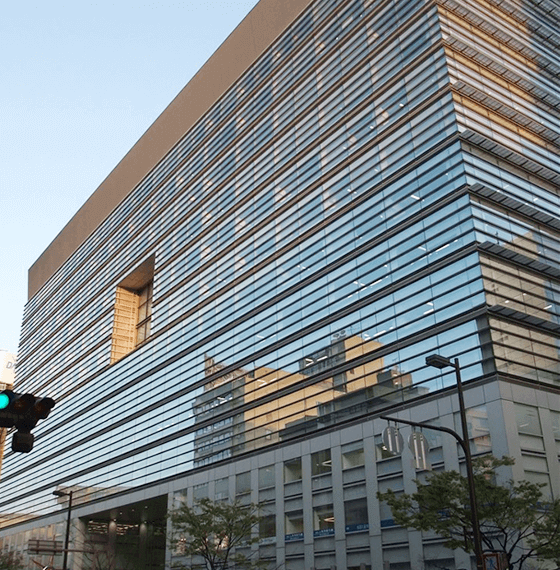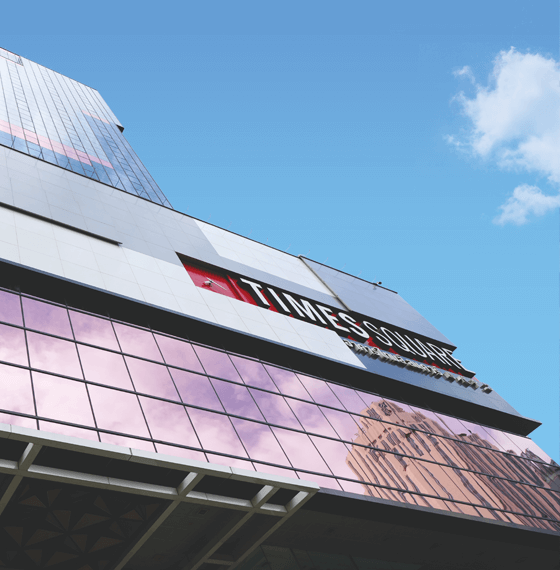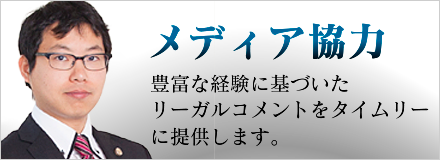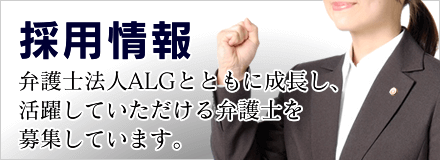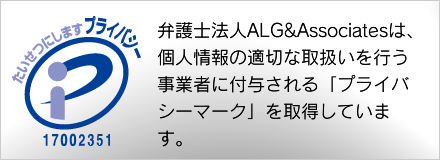限定承認をわかりやすく解説!メリット・デメリットや手続き
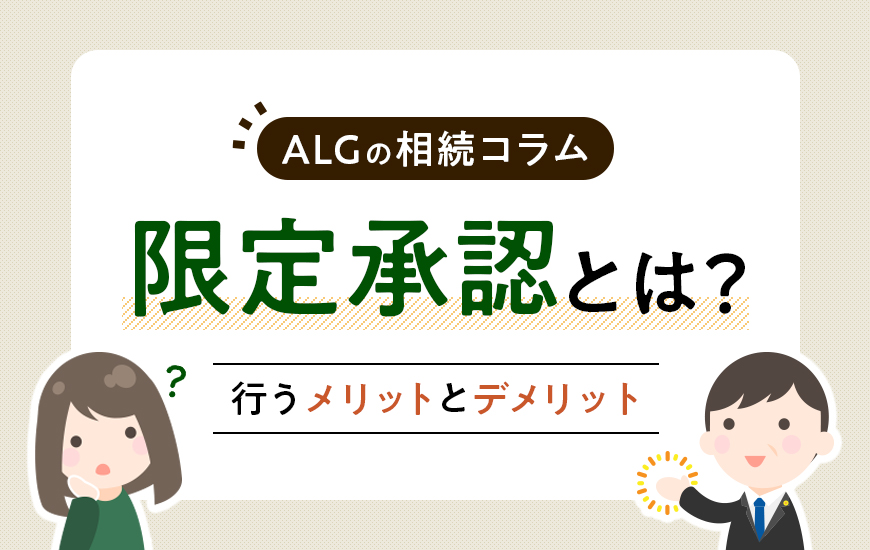
相続財産の内容は様々です。プラスの財産だけでなくマイナス財産もあることはよくあります。
では、マイナス財産があったときは、相続人はどう対応すればいいのでしょうか。遺産も負債も全部引き継ぐのか、もしくは全て引き継がない選択をするのか悩むことでしょう。実は、受け取る遺産の範囲を限定できる相続方法があるのはご存知でしょうか。本稿ではそんな特別な相続方法である、限定承認について解説していきます。
目次
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産もマイナス財産も全て相続しますが、相続財産から被相続人の借金などのマイナス財産を清算して、それでも相続財産が残っていれば、その余剰分を相続するという方法です。
つまり、マイナス財産についてはプラス財産の額を上限として弁済を行うので、マイナス財産の過多によって相続人本人の財産が損なわれることがない仕組みになっています。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
限定承認のメリット
限定承認は、すべて相続する単純承認や、すべて相続しない相続放棄とは違って少し複雑な相続方法です。手続きが大変でも限定承認を選択するメリットとはなんでしょうか。代表的なものについて確認しておきましょう。
負債を負うことがない
限定承認は、プラス財産の総額を上限としてマイナス財産の弁済を行います。つまり、「プラス財産<マイナス財産」の場合であっても、相続人はプラス財産で弁済しきれなかったマイナス財産については弁済の責任を負いません。そのため、相続財産調査で判明していなかった債務について、あとから請求がきたとしても、プラス財産の範囲内での清算とできるため、相続人が安心して選択できる相続方法です。
そして、「プラス財産>マイナス財産」の場合は、弁済した後の残余財産を受け取ることができます。
連帯保証人の地位は受け継ぐことに注意が必要
では、被相続人が主体ではなく、主債務者の連帯保証人となっている債務についてはどのような取扱いになるでしょうか。
実は連帯保証人の地位というのは、相続の対象となるので、限定承認を選択した場合でもその地位は相続人に引き継がれることになります。この場合の債務についてもプラス財産の総額の範囲内で弁済の必要性があります。相続財産調査の際には、被相続人が主体となっている債務だけでなく、連帯保証人となっている債務についても注意が必要であることを念頭に置いておきましょう。
特定の財産を残せる
相続財産の中には、生活基盤となっている自宅など、取得しないと相続人の生活に支障がでるものもあるでしょう。
限定承認ではこのような特定の相続財産を、相続人が債務者よりも優先して買い取ることが認められています。この優先して取得する権利を先買権と言い、家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額で相続人本人が自身の財産で買い取る仕組みとなっています。
自己資金が必要になりますが、特定の財産を優先的に守れるのは大きなメリットではないでしょうか。
限定承認のデメリット
被相続人の負債を背負うリスクを回避できるので、限定承認にはメリットしかないように感じるかもしれません。しかし、限定承認には煩雑な手続きが必要というデメリットの側面もあります。
限定承認を選択することによるデメリットについても確認しましょう。
相続人全員が限定承認する必要がある
単純承認もしくは相続放棄の場合は、各相続人がそれぞれで選択することが可能です。しかし、限定承認については、相続人全員で行うことが条件となっています。つまり、相続人間で意見が一致しなければ限定承認による相続はできません。これは限定承認の最大のデメリットといえるでしょう。
そして、すでに単純承認している相続人がいれば、その時点で限定承認を選択することはできなくなります。限定承認を選ぶ可能性がある場合は、できるだけ早い段階で相続方法についての話し合いを行いましょう。
相続放棄した人がいる場合
もし、相続人の中で相続放棄をした人がいると、限定承認の選択にどう影響するでしょうか。
法律上、相続放棄を選択した相続人は、最初から相続人ではなかったとみなされることになります。つまり、相続放棄をした相続人がいたとしても、その相続人以外の全員の意見が一致していれば、限定承認を選択することは可能です。
もし限定承認を反対している相続人がいれば、相続放棄を検討する余地があるのかも確認してみると良いでしょう。
相続財産に手を付けることができない
限定承認を選択したとしても、その手続きが終わるまでは相続財産を処分するなどの行為はできません。
もし一人でも相続財産に手を付けた場合には、単純承認を選択したとみなされることになり、限定承認の手続きを継続することができなくなります。その場合、マイナス財産についても全て相続することになってしまい、非常に大きなリスクを伴う可能性もあります。
もし相続財産に対して何か手続き等必要であれば、必ず専門家へ相談し、限定承認手続きの妨げにならないのか確認しましょう。
税金がかかってしまう場合がある
相続の税金といえば相続税ですが、限定承認の場合には譲渡所得税も発生する場合があります。
まず、マイナス財産を遺産内で清算し、プラス財産の余剰があれば、その余剰分に対して相続税がかかる可能性があります(基礎控除内であれば相続税がかからないなど、個別事情によって変わります)。
そして、限定承認による財産の異動について、税制上は、「被相続人から相続人へ時価で財産が売却された」とみなすため、譲渡所得税が発生する可能性があります。例えば、被相続人が2000万円で取得した土地が、相続時には3000万円の時価になっていると1000万円の含み益が発生します。この1000万円は相続人へ譲渡したことによって発生した利益とみなされ、被相続人が譲渡所得を得たという構図になります。みなし譲渡所得が発生すると、被相続人の死亡から4か月以内に被相続人の譲渡所得に関する準確定申告を相続人が行う必要もあります。
遺産となる不動産の価格が高額な場合は、多額の譲渡所得税が発生してしまうことについては、注意が必要ですので、この点はあらかじめ専門家に相談されるべきでしょう。
申請までに手間や時間が掛かる
限定承認を選択するには相続人全員での申請が必要です。そのため、正確な相続人の把握が非常に重要です。普段付き合いのある親族のみが相続人とは限りませんので、必ず戸籍等を取得して調べる必要があります。
相続人が判明したらその全員と連絡をとった上で、相続方法について話し合います。もし、限定承認を希望しない相続人がいれば、説得する、もしくは相続放棄してもらえるのかについても協議が必要でしょう。相続人全員の協力体制が必要であり、限定承認には手間と時間は必須といえます。
受理された後も、更に手続きがある
限定承認に関する書類を裁判所に提出し、受理されてもそこで終わりではありません。限定承認は遺産の範囲内で負債を弁済し、超過分については債務を負わないとするため、公正な清算手続きが必要です。
そこで、官報という政府の機関誌を使って、限定承認を行う旨を公告し、債権者へ権利の申し出を促すことになります。公告期間経過後に、申し出のある債権について、遺産の範囲内で弁済・清算を行っていくことになります。限定承認の手続き開始から完了まで1年以上かかることも少なくありません。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
限定承認の手続き方法
限定承認の手続き方法を知っている人は少ないでしょう。相続人全員の同意がとれたら、家庭裁判所へ必要書類を提出し、受理してもらうことになりますが、その必要書類や手続き全体の流れ等も確認しておきましょう。
限定承認に必要な書類
限定承認の選択を家庭裁判所へ申告することを申述と言います。申述の際には一般的に以下のような書類の提出が必要となります。
- 限定承認の申述書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍含む)
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票(被相続人の最後の住所地のもの)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 財産目録
- 財産目録に関する証拠書類
- その他、家庭裁判所より提出を求められた書類
なお、被相続人の子で死亡している方がいる場合には、その子の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も必要となります。
上記書類を家庭裁判所へ提出することになりますが、管轄は被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所になりますので、提出先を間違えないよう気をつけましょう。
限定承認の手続きの流れ
限定承認の手続きの流れは、その財産内容等によって多少異なりますが、大まかには下記のような流れとなります。
- ①申述書類一式を管轄の家庭裁判所へ提出
- ②限定承認の受理(家庭裁判所から通知が届きます)
- ③官報へ限定承認を選択した旨及び債権者の申出について公告
- ④必要な場合には鑑定人選任申立てを行い、先買権を行使する
- ⑤相続財産の現金化(換価業務)
- ⑥債権者等へ相続財産による弁済
- ⑦弁済後に残余財産がある場合には、相続人で遺産分割協議の上、財産を取得
費用
まず、相続人を確定させるための戸籍謄本等の取得費用(1通450円~となります)が必要です。そして、申述書類を提出する際には、収入印紙800円と、その後の書類郵送費用として郵便切手を家庭裁判所へ納めなければいけません。郵便切手については各裁判所によって金額やその内訳が異なりますので、提出前に問い合わせておきましょう。
申述書類が受理されたら、官報への公告費用が必要となります。
さらに、不動産等があれば清算手続きのために換価業務が必要であれば、鑑定費用や競売等に関する費用が発生します。
限定承認の期限は3ヶ月
限定承認を選ぶのであれば、相続の開始を知った時から3か月以内に手続きを行わなければいけません。
しかし、相続人全員での話し合いも必要であり、3か月ですべて整えるのは難しいケースもあります。では、3か月の期間を超過した場合はどうなるでしょうか。
もし、なんら手続きせずに期間超過した場合には、単純承認したものとみなされ限定承認を選択することは出来なくなります。3か月という期間内に書類提出が難しそうであれば、家庭裁判所で申述期限を延長する手続き(期間伸長申立て、といいます。)をあらかじめ行っておきましょう。
限定承認についてご不明な点はぜひご相談下さい
限定承認は相続人本人の財産が、被相続人の負債によって脅かされることが無いので、非常に安心感のある相続方法です。しかし、その大きなメリットを享受するには、単純承認や相続放棄の手続きのように簡単にはいきません。手続きの完了まで時間もかかりますし、手続き内容も非常に専門的です。
弁護士へ依頼すれば限定承認のデメリットである複雑な手続きという問題をクリアできます。手続き可能な期間も限られているので、限定承認について少しでも迷われたらまずは弁護士へご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)