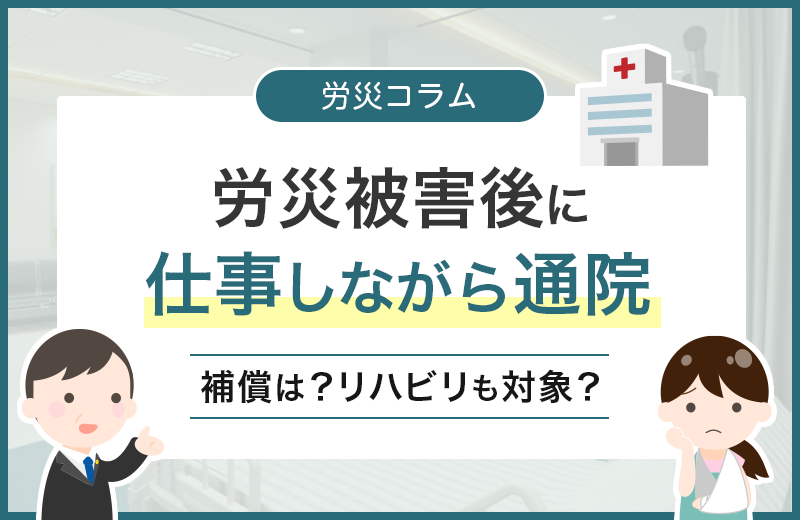
労働災害による傷病で治療が必要になった場合、仕事をしながら通院を続けていらっしゃる方も少なくありません。
傷病のダメージが軽度で業務に従事することが可能だったり、仕事の都合でどうしても休めなかったりと、仕事しながら通院するご事情はさまざまですが、仕事しながら通院した場合でも労災保険の補償を受けることが可能です。
そこで今回は、労災後に仕事しながら通院する場合の補償に着目して、労災保険から受けられる補償の内容や、リハビリ通院した場合の補償について解説していきます。
目次
労災により仕事をしながら通院する場合の治療費は補償対象
労働災害による傷病の治療に関しては、仕事をしながら通院する場合も労災保険の補償対象です。
治療に要した費用について労災保険より療養(補償)給付が受けられます。
療養(補償)給付とは?
療養(補償)給付とは、労災による傷病で治療を必要とする場合の補償です。
治療に要した診察、検査、画像撮影、薬剤、手術、入院、リハビリなどの現物給付あるいはその費用の支給が行われます。
療養(補償)給付が行われるのはいつまで?
療養(補償)給付は、労災による傷病の完治または症状固定するまで行われます。
したがって、仕事しながら通院した場合も給付の対象となり、通院頻度・回数・期間は問いません。
そもそも労災の補償給付とは?
労災保険による補償には、次の8種類があります。
なお、通勤災害における労災保険給付の名称には“補償”がつきません。
これは、通勤災害における保険給付が労働基準法の災害補償責任に基づかないためですが、受けられる補償内容に違いはありません。
| 療養(補償)給付 | 労災による傷病で療養が必要になった場合の給付 |
|---|---|
| 休業(補償)給付 | 労災による傷病で療養するため労働できず、賃金を受けられない場合の給付 |
| 障害(補償)給付 | 労災による傷病が完治せず、残存した後遺症が“後遺障害”に認定された場合の給付 「障害(補償)年金」または「障害(補償)一時金」が支給される |
| 傷病(補償)年金 | 労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治せず、一定の傷病等級に該当する場合の給付 |
| 遺族(補償)給付 | 労災により労働者が死亡した場合の、遺族に対する給付 「遺族(補償)年金」または「遺族(補償)一時金」が支給される |
| 介護(補償)給付 | 障害補償年金または傷病補償年金の受給者で、症状が重く、現に介護を受けている場合の給付 |
| 葬祭料等(葬祭給付 | 労災により死亡した労働者の葬祭を行う場合の給付 |
| 二次健康診断等給付 | 職場の定期健康診断などの結果で脳血管・心臓疾患に関連する項目に異常所見が認められた場合の給付 |
仕事しながら通院した場合に受けられる補償は2種類
労災保険による補償のうち、「仕事をしながらの通院」に関連するのは療養(補償)給付と休業(補償)給付の2種類です。
労災の休業補償は仕事しながら通院している場合でももらえる?
労災保険による休業(補償)給付は、仕事しながら通院している場合でも受け取れる可能性があります。
休業(補償)給付とは?
休業(補償)給付とは、労災による傷病の療養で労働することができない場合の補償です。
休業4日以降に、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が休業(補償)給付として支給されます。
休業(補償)給付の支給要件は?
- 業務上の事由や通勤によって被った傷病で療養していること
- 労働できない状態にあること
- 会社から賃金を受けていないこと
休業(補償)給付は、上記3つの条件をすべて満たす場合に行われます。
したがって、仕事しながら通院した場合も対象となり、通院した日の休業(補償)給付を受け取れます。
このとき、欠勤だけでなく、遅刻・早退した日も支給の対象となることがあります。
有給を使って通院した場合も給付対象になる?
有給休暇を使って通院した場合は、労災保険による休業(補償)給付は受けられません。
なぜなら、賃金を重複して受け取ることになるためで、有給休暇を取得する日は休業補償が適用されなくなるので注意しましょう。
有給休暇と労災保険の休業補償を組み合わせることは可能です
労災による通院日に、有給休暇と休業補償のどちらを使うかは、労働者ご自身で自由に決めることができます。
そのため、たとえば次のように、有給休暇と休業補償を組み合わせて利用することが可能です。
- 休業初日から第3日目までの待機期間に有給休暇を利用する
- 待機期間以外の通院日は、休業(補償)給付を受ける
労災の休業補償期間中に仕事をしたら休業補償は打ち切られる?
労災の休業補償期間中に「仕事をした=賃金を受けた日」は、休業(補償)給付を受け取ることはできません。
ですが、「労災による傷病で、労働することができず、賃金を受けていない」という要件を満たす日については、休業(補償)給付が受け取れます。
休業補償が打ち切られることはある?
次のいずれかに該当する場合は、休業(補償)給付の支給が打ち切られます。
- 労災による傷病が完治した場合
- 症状固定した場合
- 傷病(補償)年金に切り替わる場合
なお、症状固定した場合と傷病(補償)年金に切り替わる場合については、次項の「リハビリ通院」で掘り下げて解説しますので、そちらもご参考になさってください。
リハビリ通院はいつまで労災の補償対象になるのか?
労働災害による傷病でリハビリ通院が必要になった場合は基本的に、支給要件を満たす場合や、傷病が完治するまでは労災保険給付が受けられます。
ただし、次に該当するケースでは、なにかしらの症状が残っていても給付が打ち切られてしまいます。
症状固定した場合
傷病の治療をこれ以上続けても症状の改善が見込めない状態を症状固定といいます。
症状固定と判断されると、症状が残っていても、休業(補償)給付が打ち切られます。
傷病(補償)年金に切り替わる場合
療養開始から1年6ヶ月を経過しても治癒せず、その傷病が障害等級第3級以上に該当すると労働基準監督署長が判断すると、休業(補償)給付が打ち切られて、傷病(補償)年金に切り替わります。
症状固定後に後遺障害等級が認定された場合
症状固定後に労災による傷病の後遺症が残ってしまった場合、障害(補償)給付の請求をすれば、後遺障害等級認定を受けることができます。
後遺障害等級が認定されると、休業(補償)給付に代わって、障害(補償)給付が受けられるようになります。
障害(補償)給付とは?
残存した後遺症が、後遺障害等級認定された場合の補償です。
認定された等級に応じて、労災保険から次のような補償がうけられます。
- 障害等級第1級~第7級に該当する場合:障害(補償)年金
- 障害等級第8級~第14級に該当する場合:障害(補償)一時金
仕事をしながら通院する際の労災給付を受け取るための手続き
仕事をしながら通院した場合の、労災保険給付を受けるための手続きについて、順を追ってみていきましょう。
①労災保険給付を受けるための請求書を提出する
請求する保険内容によって、それぞれ請求書を作成・提出する必要があります。
主な必要書類は次のとおりですが、添付や追加提出を求められる書類もあります。
| 療養(補償)給付 | 【労災指定医療機関を受診する場合】 <業務災害の場合> <通勤災害の場合> 【労災指定医療機関以外を受診する場合】 <業務災害の場合> <通勤災害の場合> |
|---|---|
| 休業(補償)給付 |
<業務災害の場合> <通勤災害の場合> |
②給付金が支給される
労働基準監督署による調査が行われ、労災認定されると保険金が支給されます。
《障害(補償)給付を受けるためには?》
障害(補償)給付を請求する場合、症状固定後に医師が作成した診断書を添付して、次の請求書を管轄の労働基準監督署に提出します。
| 障害(補償)給付 |
<業務災害の場合> <通勤災害の場合> |
|---|
診断書の取得費用は請求できる?
障害(補償)給付の請求時に添付が求められる診断書の取得に要した費用は、次のいずれかの請求書を併せて提出することで、療養(補償)給付として受け取れます。
- 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
- 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
仕事をしながら労災の治療をする際に不安なことがあれば弁護士にご相談ください
労働災害によって傷病が生じると、経済的な負担が大きくなってストレスに感じる方もいらっしゃると思います。
仕事をしながらでも、治療を受けるために賃金が得られなかった場合は、労災保険から給付金が受け取れますので、忘れずに申請しましょう。
「通院する日は有給を取得するように会社に指示された」
「数時間だけ仕事を休んで通院したけど、休業補償は受けられないといわれた」
など、仕事しながらの通院でお困りのことは、弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
労災の被害に遭われた方の不安や負担が軽減できるように、弁護士がアドバイス・サポートいたします。

監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格 : 弁護士 (東京弁護士会所属・登録番号:41560)
東京弁護士会所属。私たちは、弁護士106名、スタッフ220名(司法書士1名を含む)を擁し(※2023年1月4日時点)、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、バンコクの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。
初回相談無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※電話やメール等で弁護士が無料法律相談に対応することは出来ませんのでご承知下さいませ。
