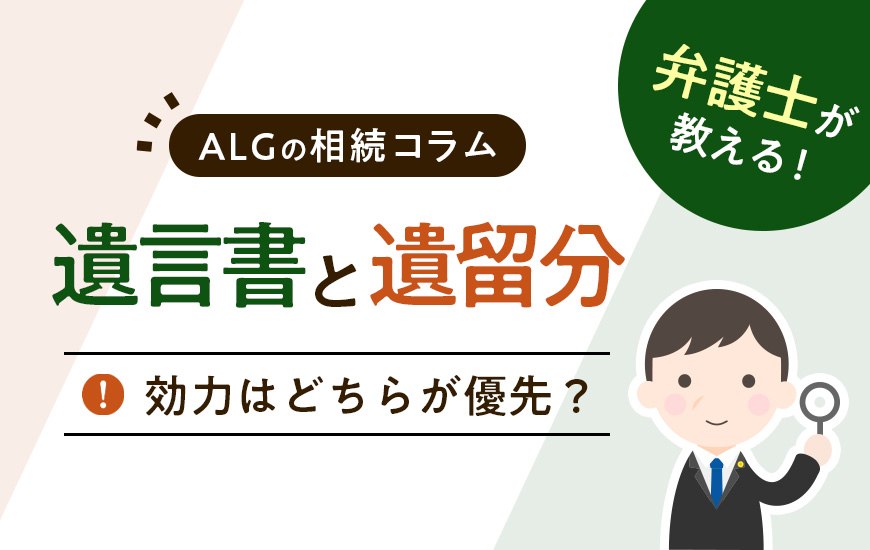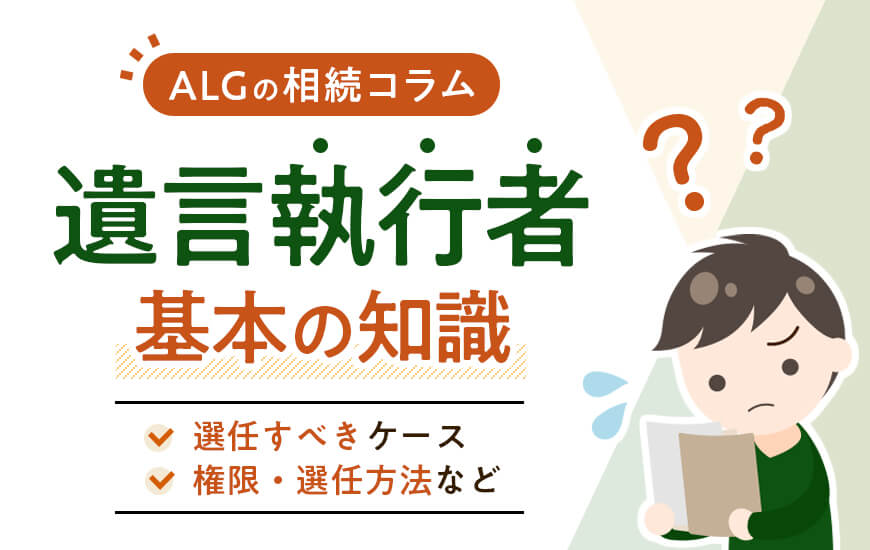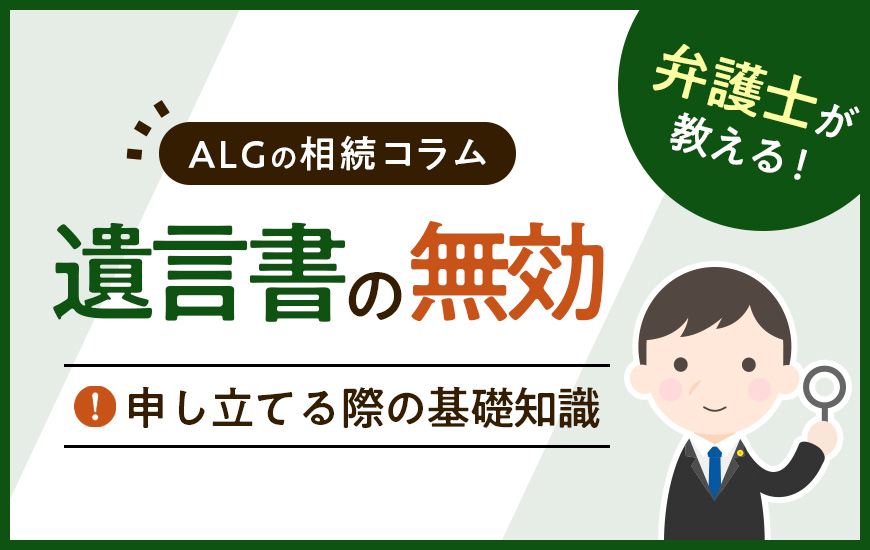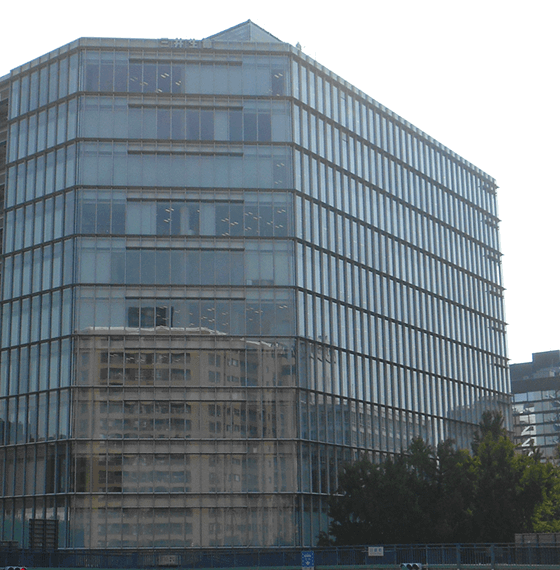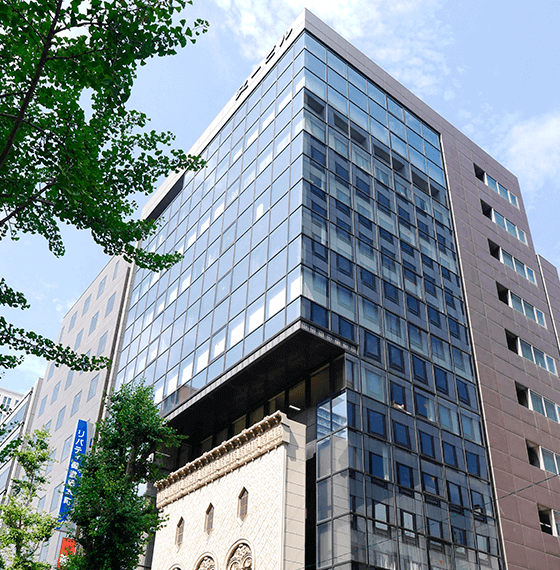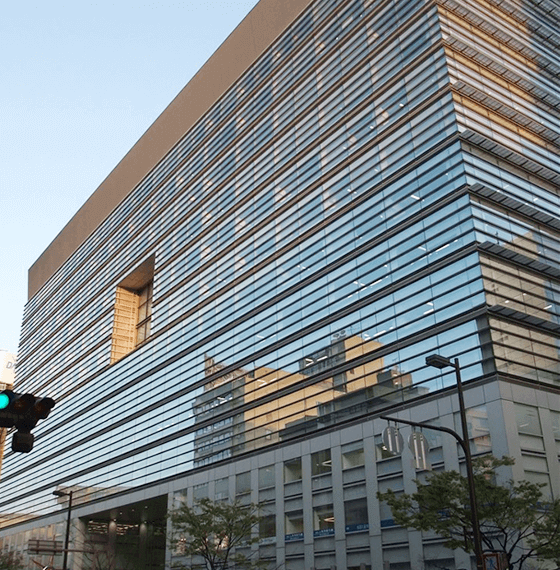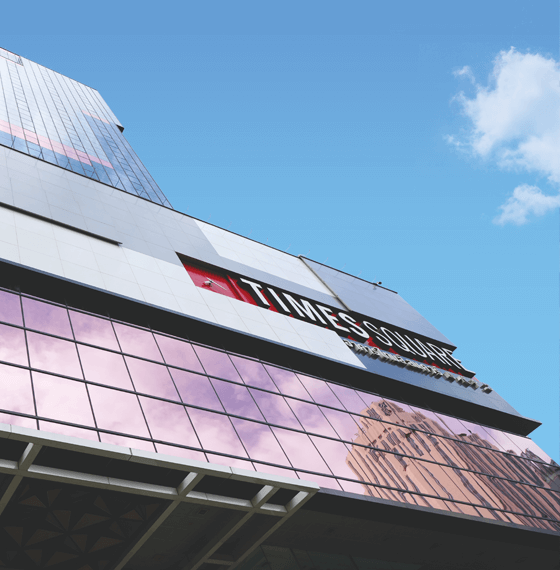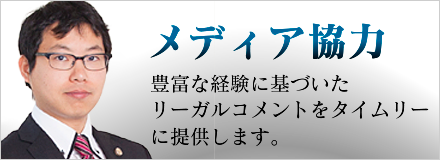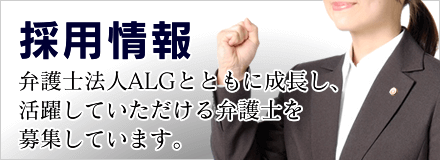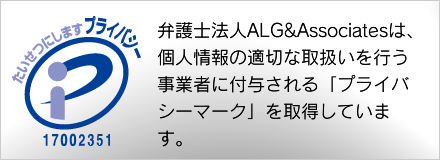公正証書遺言でもめる7つのケース!トラブル回避のポイントや対処法など
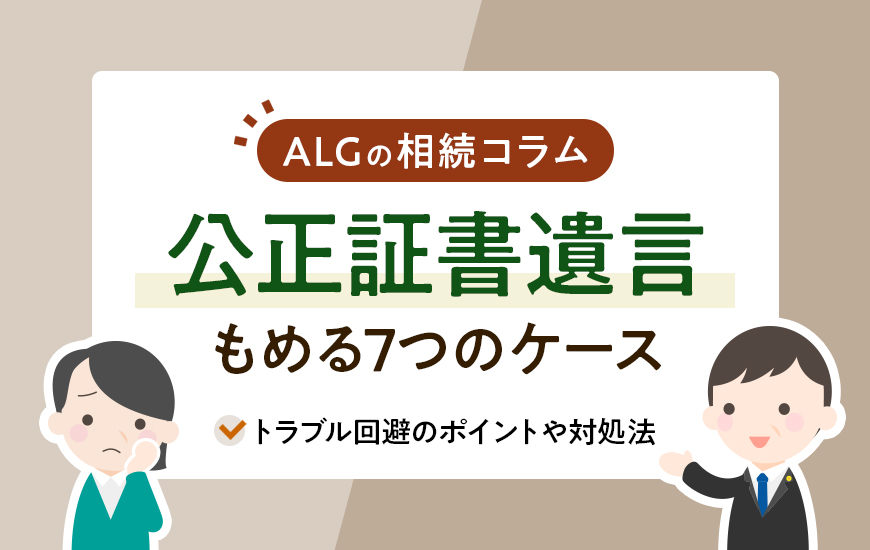
公正証書遺言は、もめるリスクの低い遺言書です。そのため、遺言書を作成するときには、なるべく公正証書遺言にすることが望ましいでしょう。
しかし、公正証書遺言であっても、効力や遺留分、死後の手続き等についてもめてしまう場合があります。
この記事では、
- 公正証書遺言でもめるケース
- もめない公正証書遺言を作成するポイント
- 公正証書遺言の撤回や書き換え
- もめた場合の対処法 等
について解説します。
目次 [表示]
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、2人以上の証人が立ち会って、公証人によって作成される遺言書です。
形式的なミスで無効となることが少なく、紛失や破棄、改ざん等のリスクもほとんどないので、被相続人にとっては安心できる方式です。
しかし、公正証書遺言は必ず有効になるわけではありません。
被相続人に遺言書を作成する能力がなかった場合や、作成するときの手続きが誤っていた場合等では、遺言書が無効となってしまうおそれがあります。
また、公正証書遺言であっても遺留分を失わせることはできないため、相続財産の配分が偏っているともめるおそれがあります。
遺言書の内容を実現するための手続きでもめるおそれもあります。
公正証書遺言でもめる7つのケース
公正証書遺言は、主に以下のようなケースでもめることがあります。
- 遺言者が認知症だった
- 公証人への口授(くじゅ・こうじゅ)を欠いていた
- 不適格な証人のもと遺言書を作成した
- 遺留分を侵害している
- 錯誤(勘違い・誤解)があった
- 公序良俗に反している
これらのケースについて、次項より解説します。
遺言者が認知症だった
遺言書作成当時、被相続人が認知症を発症していた等、遺言能力に疑いがある場合には、作成した公正証書遺言の有効性についてもめるおそれがあります。
遺言能力とは、自分が作成した遺言書の内容を理解して、その遺言書が生じさせる結果を認識する能力のことです。
公正証書遺言であっても、遺言能力のある状態で作成されたことが必ずしも保証されるものではありません。
被相続人が認知症であった場合の遺言能力の有無は、遺言書作成時の被相続人の様子や医師の意見、遺言書の内容が合理的か否か等を検討して判断されます。
なお、複雑な内容の遺言書よりも、特定の相続人に全財産を相続させるというような、シンプルな遺言書の方が遺言能力は認められやすくなります。
ただし、疎遠だった者に全財産を与えるような、合理的に説明できない内容の遺言書については、遺言能力のなかったことを推定させる要因になり得ます。
公証人への口授(くじゅ・こうじゅ)を欠いていた
公正証書遺言を作成するときには、遺言書を作成する者の意思によって、基本的には遺言書の内容を自分の口で公証人に伝えなければなりません。これを口授といいます。
しかし、実務では、公証人が事前に遺言者やその家族と打ち合わせをして遺言書の文案を作成し、遺言書作成当日には、公証人が遺言書にその書面を読み聞かせ、これを遺言者が「はい」などと発語して応答するというケースが多いです。
判例はこのようなケースでは口授があったものと判断しています。
ただし、遺言書を作成した日の前後における被相続人の様子から重度の認知症が疑われるケースや、当日に遺言書の内容を読み上げられたときの反応が、単に頷いただけであったケース等では、遺言書が無効と判断されるおそれがあります。
不適格な証人のもと遺言書を作成した
公正証書遺言を作成するときには、2名以上の証人の立ち会いが必要であり、証人が不足していると遺言書は無効となります。
単純に証人が足りないケースだけでなく、証人になれない者が証人として立ち会っていたケースでも、遺言書は無効となります。
証人になれない理由のことを欠格事由といいます。欠格事由として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 未成年者である
- 遺言書の作成時に、相続人になると推定される者
- 相続人になると推定される者の配偶者や子、両親等
- 公証人の配偶者
- 公証人の書記および使用人
遺留分を侵害している
遺留分を侵害する公正証書遺言を作成することは可能であり有効ですが、遺留分侵害額請求によってもめるおそれがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている相続財産の最低限の取り分です。
遺留分を侵害された者は、他の相続人等に対して、遺留分に相当する金銭等を請求できます。この請求を遺留分侵害額請求といいます。
遺留分による争いを起こさないためには、相続財産の分配を、あまり偏らせないようにする方法が考えられます。
遺言書と遺留分の効力について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
錯誤(勘違い・誤解)があった
公正証書遺言を作成したときに、被相続人が重大な勘違いや誤解をしていた場合には、遺言書が無効となるおそれがあります。
例えば、自身の死後に親族の面倒を見てもらうつもりで、親族の面倒を見る義務のない老人ホーム等へ全財産を遺贈する等、重大な勘違いや誤解をしていたことが明らかなケースであれば、遺言書は無効となる可能性があります。
ただし、被相続人の目的等を遺言書に明記していない場合には、勘違いや誤解を証明することは簡単でないため、被相続人に勘違いや誤解があったのかについてもめるおそれがあります。
公序良俗に反している
作成した公正証書遺言が公序良俗に反していると無効となります。
例えば、法律上の配偶者がいるのに、愛人に全財産を遺贈するような遺言書を作成すると、公序良俗に反すると判断されるリスクが高いです。
夫婦関係が実質的に破綻しており、相続財産がなくても配偶者は困窮しない等の事情があれば、公序良俗違反にならない可能性もあります。
しかし、法定相続人の生活を理不尽に脅かすような遺言書は、無効とされるリスクがあるため注意しましょう。
その他
公正証書遺言が有効であり、遺留分を侵害していないケースであっても、もめるおそれはあります。
もめやすいケースとして、主に以下のようなものが挙げられます。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-524-003来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
もめない公正証書遺言を作成するポイント
もめない公正証書遺言を作成するためのポイントとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 弁護士に作成サポートを依頼する
- 認知症の場合は医師の診断書を取得しておく
- 証人が適格であるか確認する
- 遺留分に配慮する
- 作成前に相続人と話し合う
- 付言事項を活用する
- 遺言執行者を指定する
これらのポイントについて、次項より解説します。
弁護士に作成サポートを依頼する
公正証書遺言を作成する前に、弁護士にサポートを依頼しましょう。
公証役場や公証人は、遺言書の形式を有効なものとするために注意を払ってくれますが、もめないようにするための配慮はしてくれません。
弁護士に依頼すれば、不動産の分配等、もめやすい事項の扱いについてアドバイスを受けることや、トラブルを予防するための文言を記載するためのアドバイスを受けることが可能です。
認知症の場合は医師の診断書を取得しておく
遺言書を作成するときに、認知症が疑われるような症状がある場合には、医師の診断書を取得しましょう。
診断書があれば、遺言書を作成するときに、遺言能力に問題がなかったという証拠の1つにすることができます。
ただし、診断書があれば遺言能力を確実に証明できるわけではありません。
遺言書の内容が理解可能な程度にシンプルであったか、合理的であるか等、さまざまな事情が考慮されます。
なるべく、事前に弁護士へ相談しておくことが望ましいと言えます。
認知症による相続への影響について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
証人が適格であるか確認する
公正証書遺言を作成するときには、被相続人との関係等を十分に検討しましょう。
作成時に相続人になることが推定される者や、遺言書で相続財産を遺贈される予定の者については、証人とすることができません。
証人になってもらえる者の心当たりがない場合には、日当などを支払えば、公証役場に手配してもらうことが可能です。
また、弁護士に公正証書遺言の作成のサポートを依頼すると、証人の手配を代わりに行ってもらえる場合が多いです。
遺留分に配慮する
公正証書遺言でも遺留分をなくすことは基本的にできないので、遺留分制度を理解して、遺言書の内容を検討する必要があります。
遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合には、権利者に遺留分侵害額請求しないことを求めるために、付言事項を記載しておく必要があります。
ただし、付言事項に強制力はないので、請求が行われることを念頭に置かなければなりません。
そのため、遺留分侵害額請求を受けた者が困らないように、支払いの原資となる預貯金等を準備しておく必要があります。
作成前に相続人と話し合う
遺言書は単独で作成できるものであり、公正証書遺言を作成するときに相続人等の了承を得る必要はありませんが、もめるのを防ぎたければ、作成する前に親族等へ自分の意思を伝えておくことが望ましいでしょう。
遺言書を作成する事実と、大まかな内容を伝えておくことによって意思を理解してもらい、もめることを防げる可能性があります。
公正証書遺言を作成することを伝えておくと、遺言書に気づかないまま、相続手続きが進んでしまうことを予防できるメリットもあります。
付言事項を活用する
公正証書遺言でもめるのを防ぐためには、付言事項によって、自身の意思を伝えるようにしましょう。
付言事項とは、遺言書に記載する相続人等に伝えたいメッセージであり、法的拘束力はありません。
しかし、相続財産の分配が偏っている理由などを説明できるので、感情的な対立が緩和され、もめるのを防ぐために有効な可能性があります。
遺言執行者を指定する
遺言執行者とは、遺言書に記載されている内容を実現するために指定される者です。
相続人からは独立した立場で手続きを進めてくれるため、遺言書の内容を実現できる可能性が高まります。
遺言執行者は、相続人の1人であっても指定できます。しかし、相続手続きを行うためには、専門的な知識が必要となることが多いです。
また、収集しなければならない書類も多数に及ぶケースが多いので、十分な時間のある者でなければ難しいでしょう。
遺言執行者は、なるべく専門家に依頼して指定することをおすすめします。
遺言執行者について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
公正証書遺言の撤回や書き換えは可能?
公正証書遺言であっても、撤回することや書き換えることは可能です。
そのため、無効になるリスクのある遺言書や、もめるリスクの高い遺言書を作成してしまったことに気づいた場合には、なるべく早く作り直す必要があります。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるので、自分で破棄することはできません。
新たな遺言書を作成する方法により、前の遺言書の効力を失わせることが可能です。
公正証書遺言に納得いかない・もめた場合の対処法
公正証書遺言に納得いかない場合や、遺言書によってもめた場合には、主に以下のような方法で対処します。
- 相続人全員で話し合う
- 遺言無効確認調停・訴訟
- 遺産分割調停・審判
- 遺留分侵害額請求権の行使
これらの対処法について、次項より解説します。
相続人全員で話し合う
公正証書遺言でもめた場合には、まずは相続人同士の話し合いで解決を試みます。
相続人の全員が合意して、遺言執行者などの同意が得られれば、遺言書の内容とは異なる割合で相続することができます。
話し合いが進まないときには、弁護士に依頼して、交渉を代理してもらうことも有効です。
第三者が介入すれば、感情的な対立が緩和されて、冷静に話し合える可能性があります。
遺言無効確認調停・訴訟
当事者の話し合いで解決できない場合には、遺言無効確認調停を申し立てます。
遺言無効確認調停とは、遺言書を無効とするための話し合いであり、家庭裁判所で調停委員会に仲介してもらいながら行います。
あくまでも話し合いなので、公正証書遺言が有効であるか、無効であるかの結論が強制されることはありません。
調停が成立しなければ、遺言無効確認訴訟を提起します。
遺言無効確認訴訟では、遺言書が無効であると認められる可能性があります。
ただし、遺言書が無効となっても、相続財産の分配について結論が出されるわけではありません。改めて、遺産分割協議などを行う必要があります。
遺言書の無効を申し立てるための基礎知識について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺産分割調停・審判
公正証書遺言を無効にできたとしても、遺産分割協議がまとまらないために相続財産を分配できない場合には、遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停とは、相続財産の分配等について行う話し合いです。
調停がまとまらない場合には、遺産分割審判へ自動的に移行します。審判では結論が強制されるため、相続財産の分配等については最終的な決着が図られます。
遺留分侵害額請求権の行使
公正証書遺言を無効にできない場合には、遺留分侵害額請求を行いましょう。
遺言書によって偏った分配が行われたとしても、受け取ることのできる相続財産が遺留分に不足するときには、不足分に相当する金銭を他の相続人に対して請求することが可能です。
ただし、遺留分侵害額請求権は、「相続が開始されたこと」と「遺留分が侵害されたこと」の両方を知ってから1年で消滅時効が完成し、援用されてしまうおそれがあります。
遺言無効確認訴訟を提起しても、遺留分侵害額請求権の時効の進行を止めることはできないため、予備的に遺留分侵害額請求を行う必要があります。
公正証書遺言でもめるトラブルを回避するためにも、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。
遺言書が無効となるリスクを抑えるためには、公正証書遺言を作成する必要があります。
しかし、公正証書遺言であっても無効となるケースや、もめてしまうケースはあります。
そのため、遺言書を作成する前に、弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。
弁護士であれば、遺言書を有効にするために注意するべき点や、なるべくもめないようにするための方法等についてアドバイスできます。
せっかく作成した公正証書遺言が有益になるように、疑問に思う点については弁護士に確認することをおすすめします。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-524-003来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)