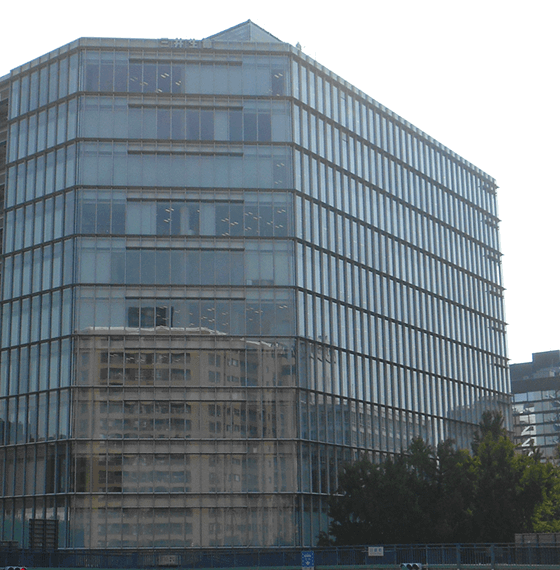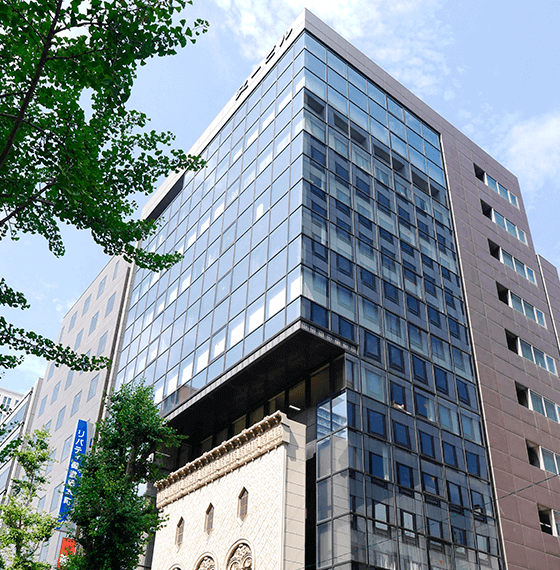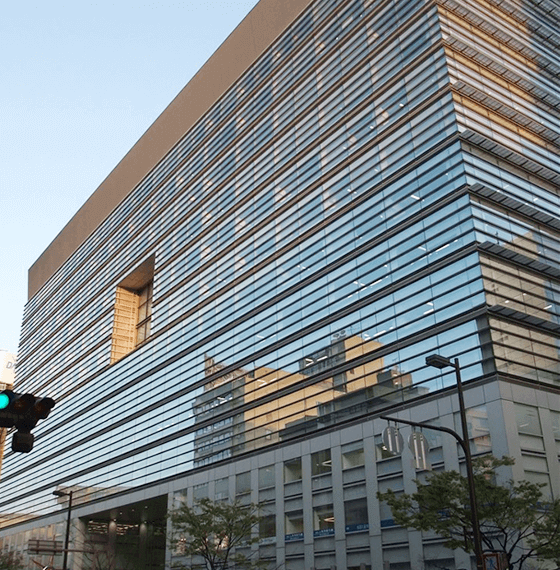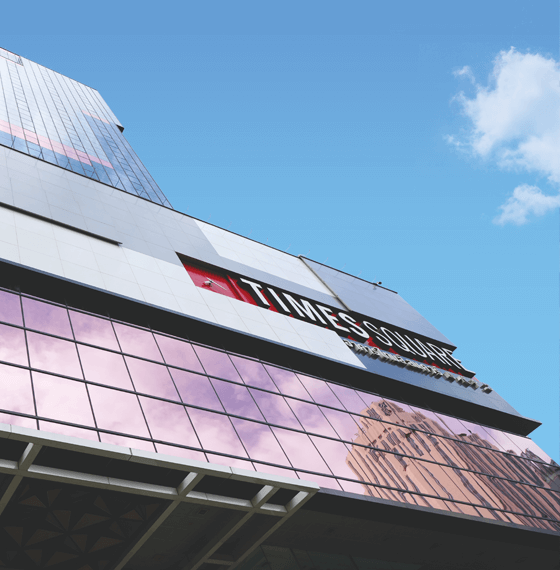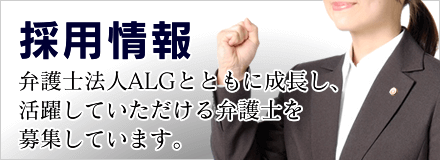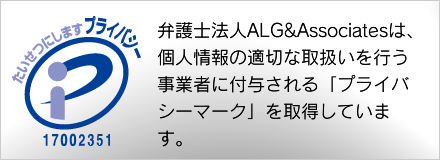ニューズレター
2017.Mar Vol.28
社宅契約における注意点
不動産業界:2017.3.vol.28掲載
私が経営しているA株式会社はマンションを所有しており、従業員に社宅として使用させています。ところが、半年前に退職した従業員であるY氏が今も社宅から出て行ってくれないのです。
Y氏と締結した社宅契約(以下「本件社宅契約」といいます。)には、「従業員が退職した場合、本契約を直ちに終了し、退職従業員は退職日から3週間以内に社宅を明渡さなければならない」(以下「契約終了条項」といいます。)と定められています。
そのため、Y氏に社宅を明渡すことを求めたいのですが、法律上の問題はないでしょうか。
本件社宅契約における契約終了条項が有効であれば、Y氏による社宅の使用は違法な占有となります。
しかし、本件社宅契約における社宅使用料が近隣の賃料相場と近接している場合、本件社宅契約は建物賃貸借契約に該当すると判断される可能性があります。
その場合、本件社宅契約には借地借家法が適用されることになり、契約終了条項は無効となってしまいますので、Y氏に社宅の明渡しを求めることは困難であると考えられます。
さらに詳しく
1.社宅契約と借地借家法との関係
建物賃貸借契約には借地借家法が適用されますので、賃貸人から建物賃貸借契約を一方的に終了させるためには借地借家法上の厳格な要件を満たしていなければなりません。
そして、本件社宅契約が建物賃貸借契約に該当する場合、契約終了条項は借地借家法上の厳格な要件を満たすものではないことから、契約終了条項は無効となってしまいます。
2.社宅契約の性質
本件社宅契約は、従業員であることが前提となっているものの、A株式会社はY氏から社宅使用料を受領しておりますので、建物賃貸借契約に該当するとも考えられます。
この点、最高裁判所は、社宅使用料が「維持費にも足らない低廉なもの」であった事案において建物賃貸借契約であることを否定しましたが(最判昭和30年5月13日)、社宅使用料が「世間並みの家賃相当額」であった事案において建物賃貸借契約であることを認めました(最判昭和31年11月16日)。
すなわち、社宅契約が建物賃貸借契約に該当するか否かは、社宅使用料と近隣の賃料相場とを比較することにより、実質的な判断がなされているのです。
3.結論
以上のとおり、契約終了条項の有効性は、本件社宅契約が建物賃貸借契約に該当するか否か、すなわち社宅使用料の高低によって判断されます。そして、本件社宅契約が建物賃貸借契約には該当せず、契約終了条項が有効だった場合には、Y氏に社宅の明渡しを求めることができると考えられます。
社宅契約が建物賃貸借契約に該当してしまった場合、退職従業員に対して社宅の明渡しを求めることは困難となります。
したがって、従業員と社宅契約を締結する際には、社宅使用料の金額については特に注意を払うことが必要となります。
- ニューズレター vol.154
- ニューズレター vol.153
- ニューズレター vol.152
- ニューズレター vol.151
- ニューズレター vol.150
- ニューズレター vol.149
- ニューズレター vol.148
- ニューズレター vol.147
- ニューズレター vol.146
- ニューズレター vol.145
- ニューズレター vol.144
- ニューズレター vol.143
- ニューズレター vol.142
- ニューズレター vol.141
- ニューズレター vol.140
- ニューズレター vol.139
- ニューズレター vol.138
- ニューズレター vol.137
- ニューズレター vol.136
- ニューズレター vol.135
- ニューズレター vol.134
- ニューズレター vol.133
- ニューズレター vol.132
- ニューズレター vol.131
- ニューズレター vol.130
- ニューズレター vol.129
- ニューズレター vol.128
- ニューズレター vol.127
- ニューズレター vol.126
- ニューズレター vol.125
- ニューズレター vol.124
- ニューズレター vol.123
- ニューズレター vol.122
- ニューズレター vol.121
- ニューズレター vol.120
- ニューズレター vol.119
- ニューズレター vol.118
- ニューズレター vol.117
- ニューズレター vol.116
- ニューズレター vol.115
- ニューズレター vol.114
- ニューズレター vol.113
- ニューズレター vol.112
- ニューズレター vol.111
- ニューズレター vol.110
- ニューズレター vol.109
- ニューズレター vol.108
- ニューズレター vol.107
- ニューズレター vol.106
- ニューズレター vol.105
- ニューズレター vol.104
- ニューズレター vol.103
- ニューズレター vol.102
- ニューズレター vol.101
- ニューズレター vol.100
- ニューズレター vol.99
- ニューズレター vol.98
- ニューズレター vol.97
- ニューズレター vol.96
- ニューズレター vol.95
- ニューズレター vol.94
- ニューズレター vol.93
- ニューズレター vol.92
- ニューズレター vol.91
- ニューズレター vol.90
- ニューズレター vol.89
- ニューズレター vol.88
- ニューズレター vol.87
- ニューズレター vol.86
- ニューズレター vol.85
- ニューズレター vol.84
- ニューズレター vol.83
- ニューズレター vol.82
- ニューズレター vol.81
- ニューズレター vol.80
- ニューズレター vol.79
- ニューズレター vol.78
- ニューズレター vol.77
- ニューズレター vol.76
- ニューズレター vol.75
- ニューズレター vol.74
- ニューズレター vol.73
- ニューズレター vol.72
- ニューズレター vol.71
- ニューズレター vol.70
- ニューズレター vol.69
- ニューズレター vol.68
- ニューズレター vol.67
- ニューズレター vol.66
- ニューズレター vol.65
- ニューズレター vol.64
- ニューズレター vol.63
- ニューズレター vol.62
- ニューズレター vol.61
- ニューズレター vol.60
- ニューズレター vol.59
- ニューズレター vol.58
- ニューズレター vol.57
- ニューズレター vol.56
- ニューズレター vol.55
- ニューズレター vol.54
- ニューズレター vol.53
- ニューズレター vol.52
- ニューズレター vol.51
- ニューズレター vol.50
- ニューズレター vol.49
- ニューズレター vol.48
- ニューズレター vol.47
- ニューズレター vol.46
- ニューズレター vol.45
- ニューズレター vol.44
- ニューズレター vol.43
- ニューズレター vol.42
- ニューズレター vol.41
- ニューズレター vol.40
- ニューズレター vol.39
- ニューズレター vol.38
- ニューズレター vol.37
- ニューズレター vol.36
- ニューズレター vol.35
- ニューズレター vol.34
- ニューズレター vol.33
- ニューズレター vol.32
- ニューズレター vol.31
- ニューズレター vol.30
- ニューズレター vol.29
- ニューズレター vol.28
- ニューズレター vol.27
- ニューズレター vol.26
- ニューズレター vol.25
- ニューズレター vol.24
- ニューズレター vol.23
- ニューズレター vol.22
- ニューズレター vol.21
- ニューズレター vol.20
- ニューズレター vol.19
- ニューズレター vol.18
- ニューズレター vol.17
- ニューズレター vol.16
- ニューズレター vol.15
- ニューズレター vol.14
- ニューズレター vol.13
- ニューズレター vol.12
- ニューズレター vol.11
- ニューズレター vol.10
- ニューズレター vol.09
- ニューズレター vol.08
- ニューズレター vol.07
- ニューズレター vol.06
- ニューズレター vol.05
- ニューズレター vol.04
- ニューズレター vol.03
- ニューズレター vol.02
- ニューズレター vol.01
- 不動産業界 vol.119
- 不動産業界 vol.118
- 不動産業界 vol.117
- 不動産業界 vol.116
- 不動産業界 vol.115
- 不動産業界 vol.114
- 不動産業界 vol.113
- 不動産業界 vol.112
- 不動産業界 vol.111
- 不動産業界 vol.110
- 不動産業界 vol.109
- 不動産業界 vol.108
- 不動産業界 vol.107
- 不動産業界 vol.106
- 不動産業界 vol.105
- 不動産業界 vol.104
- 不動産業界 vol.103
- 不動産業界 vol.102
- 不動産業界 vol.101
- 不動産業界 vol.100
- 不動産業界 vol.99
- 不動産業界 vol.98
- 不動産業界 vol.97
- 不動産業界 vol.96
- 不動産業界 vol.95
- 不動産業界 vol.94
- 不動産業界 vol.93
- 不動産業界 vol.92
- 不動産業界 vol.91
- 不動産業界 vol.90
- 不動産業界 vol.89
- 不動産業界 vol.88
- 不動産業界 vol.87
- 不動産業界 vol.86
- 不動産業界 vol.85
- 不動産業界 vol.84
- 不動産業界 vol.83
- 不動産業界 vol.82
- 不動産業界 vol.81
- 不動産業界 vol.80
- 不動産業界 vol.79
- 不動産業界 vol.78
- 不動産業界 vol.77
- 不動産業界 vol.76
- 不動産業界 vol.75
- 不動産業界 vol.74
- 不動産業界 vol.73
- 不動産業界 vol.72
- 不動産業界 vol.71
- 不動産業界 vol.70
- 不動産業界 vol.69
- 不動産業界 vol.68
- 不動産業界 vol.67
- 不動産業界 vol.66
- 不動産業界 vol.65
- 不動産業界 vol.64
- 不動産業界 vol.63
- 不動産業界 vol.62
- 不動産業界 vol.61
- 不動産業界 vol.60
- 不動産業界 vol.59
- 不動産業界 vol.58
- 不動産業界 vol.57
- 不動産業界 vol.56
- 不動産業界 vol.55
- 不動産業界 vol.54
- 不動産業界 vol.53
- 不動産業界 vol.52
- 不動産業界 vol.51
- 不動産業界 vol.50
- 不動産業界 vol.49
- 不動産業界 vol.48
- 不動産業界 vol.47
- 不動産業界 vol.46
- 不動産業界 vol.45
- 不動産業界 vol.44
- 不動産業界 vol.43
- 不動産業界 vol.42
- 不動産業界 vol.41
- 不動産業界 vol.40
- 不動産業界 vol.39
- 不動産業界 vol.38
- 不動産業界 vol.37
- 不動産業界 vol.36
- 不動産業界 vol.35
- 不動産業界 vol.34
- 不動産業界 vol.33
- 不動産業界 vol.32
- 不動産業界 vol.31
- 不動産業界 vol.30
- 不動産業界 vol.29
- 不動産業界 vol.28
- 不動産業界 vol.27
- 不動産業界 vol.26
- 不動産業界 vol.25
- 不動産業界 vol.24
- 不動産業界 vol.23
- 不動産業界 vol.22
- 不動産業界 vol.21
- 不動産業界 vol.20
- 不動産業界 vol.19
- 不動産業界 vol.18
- 不動産業界 vol.17
- 不動産業界 vol.16
- 不動産業界 vol.15
- 不動産業界 vol.14
- 不動産業界 vol.13
- 不動産業界 vol.12
- 不動産業界 vol.11
- 不動産業界 vol.10
- 不動産業界 vol.09
- 不動産業界 vol.08
- 不動産業界 vol.07
- 不動産業界 vol.06
- 不動産業界 vol.05
- 不動産業界 vol.04
- 不動産業界 vol.03
- 不動産業界 vol.02
- 不動産業界 vol.01