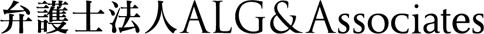年金を受給していても債務整理はできる?影響や注意点などを解説


借金の問題は債務整理で解決を図ることができますが、年金を受給していても債務整理はできるのか、債務整理をすると年金にどのような影響がでるのか、気になるところです。
そこで本記事では、債務整理と年金の関係に着目して、年金受給者でも債務整理は可能なのか、年金に与える影響や注意点を解説していきます。
年金生活をするなかで借金が返済できずにお困りの方のお役にたてば幸いです。
目次
年金を受給していても債務整理はできる?
年金を受給していても債務整理することは可能です。
そもそも債務整理とは、借金の返済で悩んでいる人を、話し合いや裁判所の手続きによって借金を減らして、生活再建をサポートすることを目的とした、国が認めた救済制度です。
そのため、年齢や収入の種類に関係なく、債務整理を利用することができます。
年金受給者が債務整理をする場合、公的年金と個人年金によって取り扱いが異なるため、それぞれ詳しくみていきましょう。
公的年金への影響
公的年金とは、国が運営する年金制度のことで、債務整理の手続き中も手続き後も、基本的に受け取る年金に影響はありません。
公的年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2階建て構造になっていて、それぞれ老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類があります。
| 老齢年金 | 10年以上の納付期間があれば、65歳以上になると受給できる年金 |
|---|---|
| 障害年金 | 事故や病気などで障害認定を受けたときに受給できる年金 |
| 遺族年金 | 亡くなった年金加入者によって生計を維持していた遺族(配偶者や子どもなど)が受給できる年金 |
いずれも国民の最低限の生活を保障するものとして、法律によって受給権が保護されています。
そのため、個人で権利や義務を自由に決めることができず、差し押さえも禁止されていることから、債務整理によって公的年金が差し押さえられて受け取れなくなったり、債務整理後の受給額が減らされたりすることはありません。
個人年金への影響
個人年金とは、公的年金を補って老後の生活をより豊かにするために、個人が保険会社や信託銀行と任意で契約して積み立てを行う私的年金のことです。
年金保険や個人年金保険と呼ばれることがあります。
個人年金の受給権は、公的年金の受給権とは異なり法律上の保護がなく、現金や預貯金などと同じように債務者個人の財産とみなされるため、債務整理の方法によっては強制解約や差し押さえの対象となるおそれがあるので注意しましょう。
年金受給者が債務整理をしたらどうなる?
年金受給者が債務整理をすると、公的年金の受給には影響しませんが、債務整理の方法によっては年金が振り込まれる口座や個人年金に影響が及ぶ可能性があります。
年金受給者が債務整理をする主な方法
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
債務整理の方法ごとに、年金への影響をみていきましょう。
任意整理の場合
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金の減額を図る方法です。
任意整理では整理する債権者を選択できるので、年金が振り込まれている口座の金融機関を任意整理の対象から外すことで、年金が引き出せなくなるなどのリスクを回避できます。
年金受給者が任意整理するためには?
年金受給者の場合、年金から生活費を差し引いた額で、利息や遅延損害金をカットしてもらった後の元金を3~5年で分割返済が可能であれば、任意整理が認められる可能性があります。
ただし、借金が高額な場合など自己破産を検討した方がよいケースもあります。
個人再生の場合
個人再生とは、裁判所を介して借金の大幅な減額を認めてもらう方法です。
個人再生では整理する債権者を選ぶことができないので、借入れがある金融機関の口座を年金の振込先に指定していると、口座が凍結されて年金が引き出せなくなるおそれがあります。
もっとも、債権が付いていない財産は残すことができるので、借入れをしていない金融機関の口座を年金の振込先に指定するなどの対策を講じることで、年金への影響を回避できる可能性があります。
年金受給者が個人再生するためには?
年金受給者の場合、年金から生活費を差し引いた額で、元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減額してもらった借金の残りを3年(最大5年)で分割返済が可能であれば、個人再生が認められる可能性があります。
ただし、自己破産を検討した方がよいケースもあります。
自己破産の場合
自己破産とは、裁判所を介して借金の支払義務を免除してもらう方法です。
自己破産では、返戻解約金が20万円を超える個人年金は強制解約となって債権者への返済に充てられます。
また、すでに受け取った年金については現金や預貯金として扱われるため、金額によっては処分の対象となって債権者への返済に充てられてしまいます。
自己破産を検討している場合は、個人年金やすでに受け取った年金の取り扱いについて、早めに弁護士へ相談してみましょう。
年金受給者が自己破産するためには?
自己破産は就労や収入の有無による制限を受けないため、一定の要件を満たしていれば、年金受給者であっても自己破産することが可能です。
ただし、自己破産は多くのデメリットを伴うため、自己破産すべきか慎重に判断しましょう。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
年金受給者が債務整理を行う際の注意点
年金受給者が債務整理を行う際には、次のようなことに注意しましょう。
- 年金受取口座が差し押さえ・処分の対象になる場合がある
- 年金受取口座が凍結されるおそれがある
年金受取口座が差し押さえ・処分の対象になる場合がある
法律によって保護されているのは「年金を受け取る権利」なので、すでに口座へ振り込まれた年金は預貯金と同じ扱いになります。
そのため、借金の支払いが滞ってしまうと、債権者によって年金受取口座の預貯金が差し押さえられてしまう可能性があります。
また、自己破産する際に口座の残高計が20万円以上ある場合には、年金を含めた預貯金が破産管財人によって処分され、債権者の返済に充てられてしまいます。
公的年金・私的年金を問わず、年金受取口座に多額の年金を貯蓄している場合は、自己破産を依頼する前に弁護士へ相談してみることをおすすめします。
年金受取口座が凍結されるおそれがある
年金受取口座を開設している金融機関やその関連会社から借入れをしている場合、債務整理の開始が通知されることにより口座が凍結されるおそれがあります。
口座が凍結されると、年金が引き出せなくなるだけでなく、金融機関によって債務の残りと預貯金が相殺されてしまう可能性もあります。
年金受給者が債務整理をする際は、弁護士に相談したうえで、年金をすべて引き出しておく、年金の受取口座を債務整理の対象に含まれない銀行の口座に変更するなどの対策を講じておく必要があります。
債務整理をすると確定拠出年金に影響が出る?
確定拠出年金は公的年金と同様に法律で差押禁止財産とされているため、債務整理の影響を受けません。
確定拠出年金は私的年金に含まれますが、公的年金と同様に受給者の生活を支える重要な役割を担っているとして、法律によって差し押さえが禁止されており、強制解約の対象にもなりません。
法律で差押禁止財産とされていて、債務整理をしても受給権や受給額に影響しない私的年金は、次のようなものがあります。
公的年金と同様に受給権が債務整理の影響を受けない私的年金
- 厚生年金基金
- 国民年金基金
- 確定給付企業年金(DB)
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
年金担保貸付は債務整理できる?
年金担保貸付は非免責債権にあたるため、債務整理をしても減額・免除されません。
年金担保貸付とは、年金の受給権を担保にして低金利で融資が受けられるという、年金受給者の生活支援を目的とした制度です。
生活費に充てられるべき年金が返済に充てられることで利用者が生活に困窮するケースが問題視され、2022年3月31日で廃止され、現在は利用できなくなりました。
年金担保貸付をすでに利用している場合、任意整理の対象に含めることができず、個人再生しても減額されません。
また、自己破産しても免責されないので、債務整理をしても年金担保貸付は完済するまで従前どおり年金からの天引きが続きます。
年金を受給している場合の債務整理は弁護士にご相談ください
年金を受給している場合、公的年金は債務整理をした後も減額されることなく受給することができます。
ただし、個人年金は自己破産をすると強制解約される可能性がありますし、現金や預貯金となった年金は手放さざるを得なくなる場合があります。
債務整理に詳しい弁護士であれば、債務整理のそれぞれの方法の特徴や年金の受給状況、借金の総額、資産状況などを踏まえ、任意整理や個人再生が可能なのか、自己破産するべきなのかを適切に判断し、アドバイスすることができます。
年金生活を送るなかで、借金の返済にお困りの方は、一度弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。