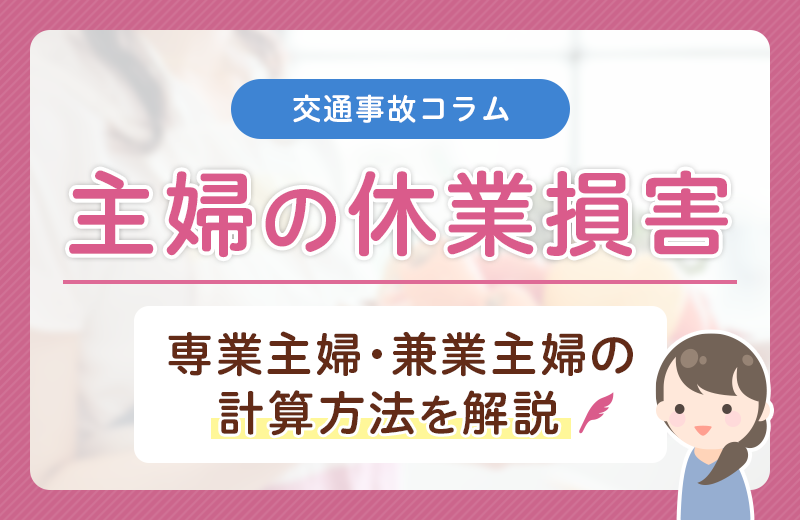交通事故の休業損害はいくらもらえる?休業補償との違いや計算の仕方
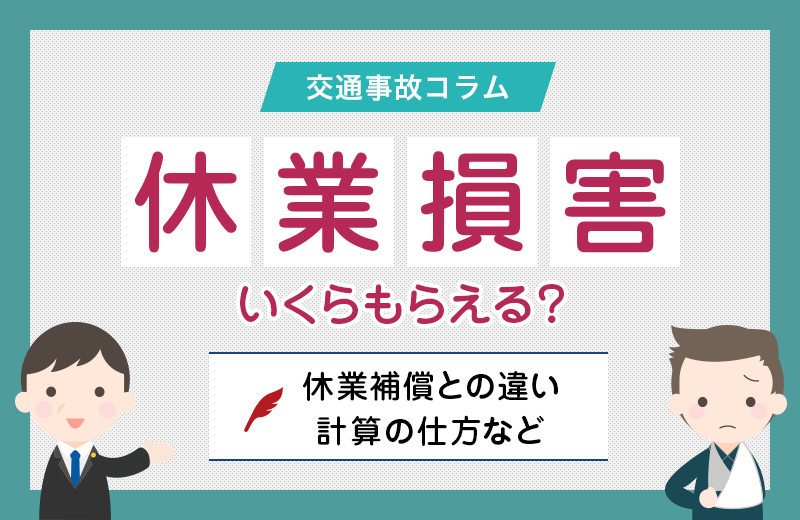
交通事故のケガで入通院が必要になった場合、体のことももちろん心配ですが、仕事を休むと収入が減るという不安も大きいのではないでしょうか。
もっとも、交通事故のケガが原因であれば、その収入の減少は加害者に請求することができます。
ただし、事故後の減収をすべて休業損害として取り戻せるとは限りません。休業損害の算定に使う事故前の収入や休業損害の対象となる休業日について、加害者側と争うケースが多々あります。
本ページでは、休業損害の計算方法や、被害者の職業による違いなど解説していきますので、保険会社から適切な補償を受けるためのポイントを掴んでいきましょう。
目次
休業損害とは
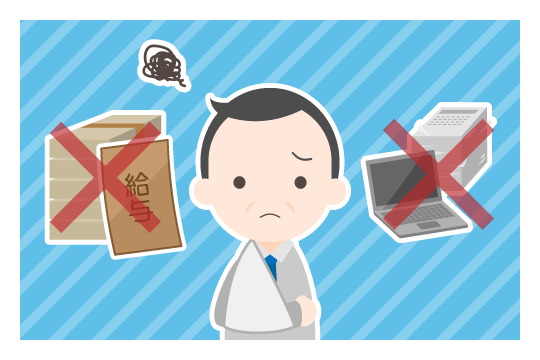
休業損害とは、交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために減ってしまった収入の補償をいい、加害者側に請求することが可能です。
通常、事故前の1日あたりの収入に休業日数をかけて計算します。
休業損害は、サラリーマンやOL、アルバイトなどの給与所得者、会社役員、個人事業主など事故前に収入を得ていた方はもちろんのこと、主婦など家事労働に従事している方も請求することができます。
また、無職者(失業者や学生)も、就職をして収入を得られる可能性が高いと認められる場合は、休業損害を請求できる場合があります。
休業補償との違い
休業損害に似た言葉として、休業補償というものがあります。
どちらも事故によるケガを原因とする、収入減少に対する補償ですが、対応する保険が異なります。
加害者側の自賠責保険・任意保険から支払われる補償を休業損害、労災保険から支払われる補償を休業補償といいます。
下表に2つの違いをまとめましたので、ご確認ください。
| 休業損害 | ・加害者が加入する自賠責保険または任意保険に対して請求する ・人身事故が対象 ・会社員、パート、アルバイト、個人事業主、会社役員、主婦、一部の学生や失業者が対象 ・有給休暇も補償の対象 ・補償額は「1日あたりの基礎収入×休業日数」(※自賠責保険においては、原則、日額6100円) 過失相殺により減額される(※自賠責保険の場合は被害者の過失が70%以上の場合) ・自賠責保険の場合は支払額に上限あり |
|---|---|
| 休業補償 | ・被害者の勤務する事業所が加入する労災保険に対して請求する ・仕事中または通勤中に発生した人身事故が対象 ・会社員、パート、アルバイトが対象 ・有給休暇は補償の対象外 ・補償額は 「給付基礎日額×80%(休業補償60%+特別支給金20%)×休業日数」 ・過失相殺による減額なし ・支払上限額なし |
交通事故に遭うのは何もプライベートの時間とは限りません。外回りの営業中に事故に遭うこともあるでしょう。
仕事中の事故であれば、休業損害だけでなく、休業補償も請求することができますが、2つの保険からの二重取りは認められていません。
どちらを選択すべきかは、個別の事情により変わります。複雑な判断が求められますので、仕事中に事故にあったなら、弁護士に相談することおすすめします。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
休業損害の計算方法|算定に必要な要素
実際の収入を基に休業損害を計算する場合、下記の計算式を用いることが一般的です。
計算するにあたっての注意点について一つずつ確認していきましょう。
3つの算定基準
休業損害を算定する基準として、以下の3つが挙げられます。
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士基準
各基準の内容は、下表のとおりです。
| 3つの算定基準 | 解説 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険の支払基準で、最低補償の基準。 被害者に過失がない場合は最も低額となる。入通院慰謝料や治療費、休業損害など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。 自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
| 弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。 弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
どの基準を用いるかで休業損害の金額が変わります。基本的には
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
の順で金額が上がり、弁護士基準による休業損害額が最も高額となる傾向にあります。 ただし、弁護士基準は、基本的に、弁護士が請求しないと認められない基準となっています。
基礎収入とは
基礎収入は、以下のとおり、算定基準によって求め方が異なります。
| 3つの算定基準 | 基礎収入の求め方 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 1日あたり6100円。ただし、実際の損害が6100円を上回ることを立証できれば、1日あたり1万9000円を上限に、実際の損害額が認められる場合あり |
| 任意保険基準 | 自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度 |
| 弁護士基準 | 交通事故前3ヶ月間の被害者の収入を日割りにした金額 |
自賠責基準の基礎収入は、最低1日6100円、最高1日1万9000円となりますので、1日6100円の収入を下回る場合は問題ありませんが、1日1万9000円を超える収入がある場合には、実際の収入の補償として不足する面があります。
一方、弁護士基準による基礎収入は、会社員の場合、事故前3ヶ月間の給与の平均値をとることが通常です。被害者の実収入から計算するので、実態に合った、最も適正な金額であるといえます。
なお、収入のない主婦や失業者、学生などの基礎収入は、厚生労働省が発表している各年齢別の平均年収の統計データ(賃金センサス)を使います。
休業日数について
休業日数とは、交通事故によるケガのために仕事を休み、入院、通院、自宅療養等をした日数のことです。休業日数として認められるか否かは、ケガの症状や治療経過、職種などから判断されるため、実際に休んだ日数すべてが休業日数としてカウントされる訳ではありません。
休業損害の対象となるのは、初診日から完治または症状固定日※までの間で働けなかった日となります。
ただし、症状固定後もリハビリや手術等が必要な場合は、例外的に症状固定後の休業損害が認められる場合があります。
ケガのために有給休暇をとった日も、休業日数に含めることが可能です。
会社員やアルバイト等は、勤務先が発行する休業損害証明書により休業日数を証明し、個人事業主や主婦等は、主治医の診断書や診療報酬明細書などにより、休業日数を証明します。
※症状固定日:これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態になったと医師が診断した日
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
職業別の休業損害の計算式
被害者の事故当時の職業ごとに、休業損害の計算方法が異なります。職業別の休業損害の計算式を下表にまとめましたので、ご確認ください。
| 職業 | 計算式 |
|---|---|
| 給与所得者 | ・(事故前3ヶ月間の給与÷90日)×休業日数 または ・(事故前3ヶ月間の給与÷稼働日数)×休業日数 |
| 主婦 | (賃金センサスの女子全年齢平均賃金÷365日)×休業日数 |
| 自営業 | ・(事故前年の確定申告所得額÷365日)×休業日数 |
| アルバイト・パート | (事故前3ヶ月間の給与÷90日)×休業日数 または (事故前3ヶ月間の給与÷稼働日数)×休業日数 |
| 無職 | 【就職先が決まっていた場合】 (賃金センサスまたは就職予定先の給与推定額÷365日)×休業日数 【就職先は未定だが、ハローワークに通うなど就労の可能性が高い場合】 (賃金センサスまたは失業前の収入額÷365日)×休業日数 |
| 学生 | 【内定を得ていた場合】 (賃金センサスまたは内定先の給与推定額÷365日)×休業日数 【内定を得ていなかった場合】 (賃金センサス÷365日)×休業日数 |
| 会社役員 | 【(役員報酬-利益配当分)÷365日】×休業日数 |
休業損害は、以下の3つの基準のいずれかを選択して、計算します。
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士基準
自賠責基準による休業損害の計算式は、以下のとおりとなります。
日額6100円×休業日数
ただし、給与明細等により、休業損害が日額6100円を超えることを証明できる場合は、日額1万9000円を限度に、実際の損害額が認められる場合があります。
任意保険基準は非公表であるためここでは割愛しますが、自賠責基準とほぼ同額が、多少高い程度となる傾向にあります。
以下では、弁護士基準による、職業別の休業損害の計算方法を解説していきます。
給与所得者の場合
給与所得者の休業損害の計算式は、以下のとおりです。
基礎収入の算定方法には、事故前3ヶ月間の給与を90日で割る方法もありますが、稼働日数で割る方が基礎収入額は高くなるため、弁護士基準ではこちらを使います。
また、給与とは手取り額ではなく、税金や社会保険料などを差し引く前の総支給額となります。
基本給だけでなく、家族手当などの各種手当も加算します。
ただし、給与額の変動が大きい場合は、事故前1年間の給与額をもとに平均日額を計算し、休業損害を算定する場合もあります。
なお、賞与の減少や昇給の遅れ、交通事故による退職等についても、交通事故との因果関係を証明できれば、休業損害として請求できる可能性があります。
主婦の場合
専業主婦(主夫)の休業損害の計算式は、以下のとおりです。
専業主婦の家事労働は実際の収入が無いため、賃金センサスの全年齢女子平均年収を365で割ったものを1日あたりの基礎収入として使います。賃金センサスとは、厚生労働省が、労働者の性別、年齢、学歴等の別に、その平均収入をまとめたデータです。
また、パート等を行う兼業主婦の場合は、実際の収入と賃金センサスを比べて高額である方を基礎収入として使います。パートと主婦業両方の休業損害を請求することはできません。
また、平等の観点から、主夫の場合も女性の平均賃金を使います。
なお、主婦の1日あたりの休業損害は、ケガの回復度に応じて徐々に減額する「逓減方式」で計算される場合もあります。
事故直後はケガで家事ができなかったとしても、回復するにつれて、家事が徐々にできるようになっていくと判断されるためです。
主婦の休業損害についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
自営業の場合
自営業者の休業損害の計算式は、以下のとおりです。
自営業者については、「事故前年の確定申告書」に基づき基礎収入を算定して、休業日数を乗じて休業損害を算定するのが通常です。
休業期間中も支払う必要のある、家賃や従業員給料、水道光熱費などの固定費は、基礎収入に参入することができます。
また、年度間で所得額に大きな変動がある場合には、数年分の所得額の平均値を適用することもあります。
もし確定申告をしていない、または確定申告の内容に不備がある場合には、他に収入を立証できる資料(預金通帳や伝票等)によって基礎収入を証明できる場合があります。
また、専業主婦のように賃金センサスを適用できるケースもありますが、妥当性が必要です。
もし、適切に確定申告ができていないのであれば、早めに専門家に相談しましょう。
アルバイトの場合
アルバイトの休業損害の計算式は、以下のとおりです。
シフト制のアルバイトで、週に2・3日程度の勤務の場合は、事故前3ヶ月間の収入を90日で割ると、基礎収入が実際よりも低く算定されてしまうため、弁護士基準では、稼働日数で割って基礎収入を算定します。
アルバイトの休業日数ついては、事故前の稼働状況を参考に、給与明細などの資料に基づき、事故による休業であることを証明する必要があります。
また、アルバイトをしているのが主婦であれば、実収入と賃金センサスを比べて、高額な方を採用して基礎収入額を求めます。
無職の場合
事故当時、無職であったとしても、働く能力があり、かつ、働く意欲もあって、事故がなければ働いていた可能性が高いといえる場合、事故前にすでに内定を得ていた場合などには、休業損害を請求することができます。
このケースでの休業損害の計算式は、以下のとおりです。
(賃金センサスまたは就職予定先の推定給与額÷365日)×休業日数
(賃金センサスまたは失業前の収入額÷365日)×休業日数
休業損害を請求するには、実際に働く意欲や能力があること、事故がなければ働いていたはずであることを、内定証明書や求職状況を証明する書類などをもとに立証する必要があります。
加害者側の保険会社が妥当と認めるかは難しいところですので、専門家に書類を持参して相談するのが望ましいでしょう。
学生の場合
学生であっても、アルバイトをしていた場合、事故による内定取り消し、事故によって留年し、就職時期が遅れた場合などには、休業損害を請求できる可能性があります。
アルバイトについては、前述のアルバイトの項目をご確認ください。内定取り消しや就職遅れによる休業損害の計算式は、以下のとおりです。
(賃金センサスまたは内定先の給与推定額÷365日)×休業日数
(賃金センサス÷365日)×休業日数
しかし、例えば被害者の事故前の単位取得状況が良くなかったような場合は、事故にあわなくても留年していたとして、加害者側が休業損害を否定するケースも多々あります。
よって、適正な休業損害を得たいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
会社役員の場合
会社役員の場合の休業損害の計算式は、以下のとおりです。
役員報酬は、実際に働いたことに対する「労働対価分」と、労働がなくても支給される「利益配当分」とに分けられます。休業損害として認められるのは、労働対価分のみとなります。
しかし、労働対価分と利益配当分は明確に区分されていないのが通常です。
役員報酬のうち労働対価分がどの程度なのかは、会社の規模や業務内容、被害者の役職・年齢・職務状況、他の従業員の報酬額との差など様々な要素を考慮して、判断されます。
例えば、社外取締役や顧問などの場合には、労務提供の割合が低いとみなされ、休業損害が認められにくい傾向にありますが、小規模会社の役員等で、従業員と同程度に働いているような場合は、労務対価部分が多いとして、休業損害を認められやすい傾向にあります。
公務員の場合
公務員の場合の休業損害の計算式は、基本的には給与所得者の場合と同じです。
ただし、公務員は一般の会社員と比べて、病気休暇制度が充実していることから、休業による減収がないとされ、加害者側の保険会社から休業損害を認められないことがあります。
しかし、休職したことによる賞与の減額や昇進の遅れ等については、休業損害として請求できる場合があるため、保険会社に対して粘り強く交渉することが必要です。
休業損害証明書とは
休業損害証明書とは、交通事故が原因で仕事を休んだことによる減収を証明する書類のことです。
欠勤日や事故前の賃金額を記入する欄などが設けられています。
会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者が休業損害を請求する際に、加害者側の保険会社に提出しなくてはならない大変重要な書類となります。
通常は、保険会社から送られてきた休業損害証明書の用紙を勤務先の担当者に渡して、必要事項を記入してもらい、保険会社に返送します。
休業損害証明書の書き方
会社員などの給与所得者が休業損害を請求するには、保険会社に休業損害証明書を提出する必要があります。
フォーマットは保険会社に送ってもらうこともできますし、保険会社のホームページからダウンロードすることもできます。
休業損害証明書は、被害者の勤務先である会社に作成してもらいます。
必要事項が記入されていなかったり、記載内容が間違っていたりする場合には、正しい休業損害を請求することができませんので、事実に基づき正確に記載してもらい、作成してもらった証明書の内容が正しいか、ご自身でも必ず確認しましょう。
特に重要なのは事故前3ヶ月の給与欄です。
基本給に付加給も含めた総支給額になっているか、総支給額から、社会保険料と所得税以外が控除されていないかなどは、基礎収入に大きな影響を与えるため、給与明細などで数字の確認が必要です。
休業損害はいつから受け取れる?
通常、示談交渉は、症状固定後に開始しますが、休業損害については、毎月の給与減額分をカバーするものですので、生活保障のためにも、示談交渉前から請求することが可能です。
書類の不備等がなければ、保険会社に請求後、約1~2週間程度で休業損害が支払われることがほとんどです。
休業損害を毎月請求するのであれば、勤務先の担当者にその旨伝え、毎月、休業損害証明書を作成してもらえるよう依頼しておくとスムーズでしょう。
もっとも、保険会社が、必ずしも、被害者から請求された休業損害全額の支払いに応じるわけではありません。
一定期間が経過すると、示談に向けて、保険会社が休業損害の打切りを打診することも考えられるため注意が必要です。
休業損害の請求の流れ
休業損害を請求する際の流れは、以下のとおりです。
- ①必要書類を加害者側の保険会社に提出する
- ②加害者側の保険会社から休業損害が支払われる
- ③毎月、1と2を繰り返す
- ④必要であれば示談交渉時に休業損害の増額を求める
- ⑤増額が認められれば、示談成立後、ほかの慰謝料などとともに、増額分が支払われる
なお、休業損害請求時に必要となる書類について、職業ごとに下表にまとめましたので、ご確認ください。
・必要書類
| 給与所得者・ アルバイト |
・休業損害証明書
・事故前年の源泉徴収票 ・給与明細 ・賞与減額証明書 |
|---|---|
| 主婦 | ・世帯全員の記載がある住民票
・家族構成表 ・家事労働についての自認書 ・事故前年の源泉徴収票(兼業主婦(夫)の場合) |
| 自営業 | ・事故前後の確定申告書の控え ・納税証明書 |
| 無職 | ・内定通知書 ・求職活動を行っていたことがわかる書類 |
| 学生 | ・内定通知書 ・内定取り消しや留年などにより、就職時期が遅れたことがわかる書類 ・休業損害証明書・源泉徴収票(学生アルバイトの場合) |
| 会社役員 | ・休業損害証明書 ・事故前年の源泉徴収票 ・会社の決算書類、役員会議事録など |
| 公務員 | ・休業損害証明書 ・事故前年の源泉徴収票 |
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害
交通事故によって退職となった場合にも休業損害を請求することが出来ます。
しかし、事故が無ければ退職していなかった、つまり退職と交通事故との間に因果関係があることを証明することが必要です。
自己都合の退職ではなく、交通事故のケガが原因で、既存の業務が困難になり、部署異動しても対応ができないといった具体的な事情を保険会社へ証明しないといけません。
もし、退職に至った場合には、休業損害を請求する為にも、勤務先に退職証明書の発行を依頼しましょう。
交通事故後の休業損害に関するよくある質問
交通事故の休業損害について、よくある質問をご紹介します。
会社員の各種手当は含めて計算できますか?
歩合給や残業手当、家族手当、職務手当、住宅手当といった付加給にあたる部分も含めて休業損害の計算に加えることができます。
ただし、残業手当については、事故前から日常的に残業が行われていたこと、事故後も事故前同様に、残業の必要性があることを示す証拠を提出できないと、保険会社に認めさせるのは難しいでしょう。
また、賞与減額についても、休業損害として請求が可能ですが、賞与の減額が事故を原因とするものなのか、単に業績悪化によるものなのかについて、勤務先の証明が必要になります。
しかし、賞与の評価基準が明らかでない場合には、主張立証が難しいため、専門家に対応を依頼することをおすすめします。
休業損害に請求時効はありますか?
休業損害も、交通事故という不法行為に基づく損害ですので時効が存在します。
交通事故発生から5年、もしくは症状固定した時から5年で時効となりますが、この期間については令和2年4月1日の民法改正以降のものが対象となります。
それ以前の事故であれば時効は3年になりますのでご注意ください。
もし、ご自身の事故についての時効が曖昧であるならば、先々のためにも、あらかじめ専門家に確認しておくことをお勧めします。
休業損害はいつまで貰えますか?打ち切られることはありますか?
休業損害が認められるのは、治療期間終了、つまり完治か症状固定と診断されるまでの期間です。しかし、保険会社は主治医からその診断が出る前に打ち切りの打診をしてくることがあります。
保険会社には交通事故に多い、打撲やむちうちなどに対し、治療期間終了の目安があるので、その期間を過ぎると、休業の必要性はないと主張してくるのです。
しかし、治療終了の判断はあくまで主治医ですので、もし、治療中に打ち切りを打診されたら、状況を説明し、先払い対応の延長を交渉してみましょう。
休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください
交通事故でケガをした場合、通院のため仕事を休み収入が減ってしまいますので、生活を安定させるには休業損害の請求が必要になります。
しかし、示談前の請求は、払い過ぎを防止するため、保険会社は支払いに慎重な対応をとることが少なくありません。
また、支払われたとしても、本来の給与水準ではなく、最低限の自賠責基準での金額になっている可能性もあります。
休業損害は、安心して治療を続けるためのライフラインともいえる賠償金です。その支払いを適切に受けられないために治療を疎かにしては本末転倒です。
ご自身の対応が正しいのか不安に感じたり、休業損害に不満があったりする場合は、ぜひ交通事故に精通した弁護士法人ALGにご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。