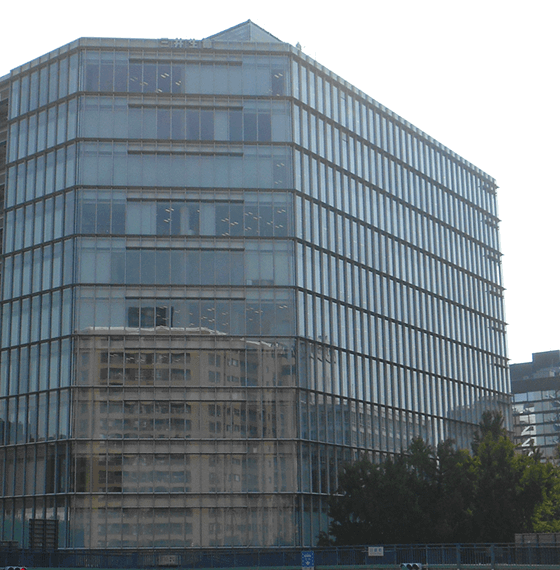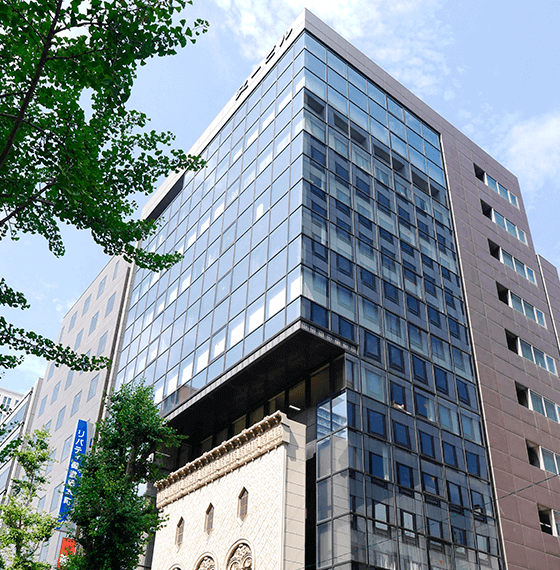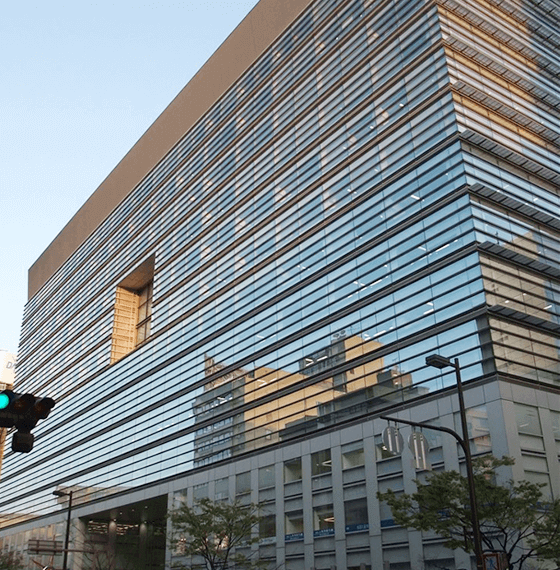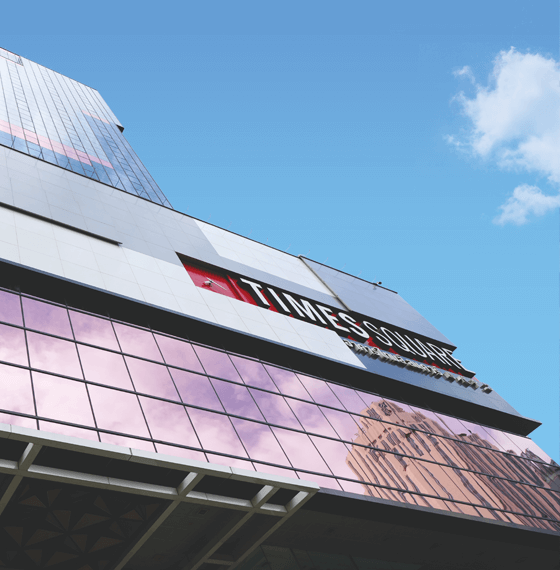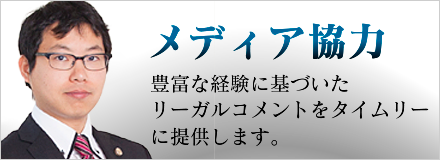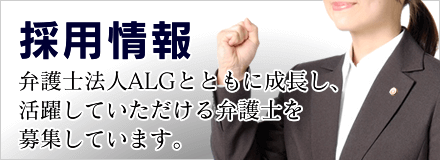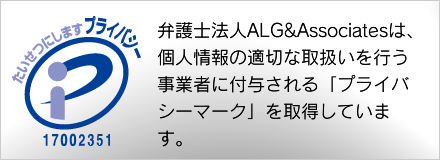遺産分割協議書とは?作成手順などの基礎知識を詳しく解説
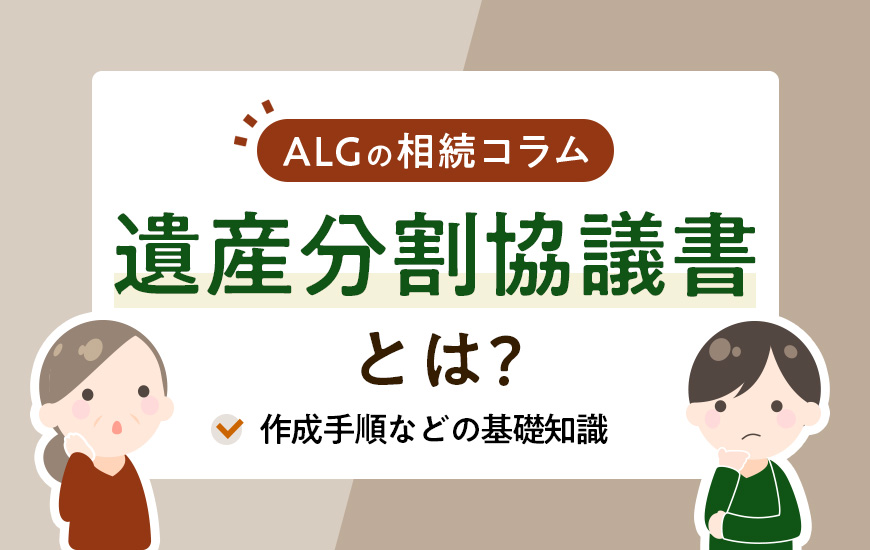
この記事でわかること
遺産分割協議書とは、相続財産の分配方法等に関する相続人間の合意内容を記載した書面です。 相続税の納税や不動産の相続登記等の場面で提出する必要があるため、慎重に作成しなければなりません。
この記事では、遺産分割協議書の作成の流れや書き方・注意点等について解説します。
遺産分割協議書を作成しようとお考えの方はぜひご覧ください。
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続財産の分配方法等について話し合う「遺産分割協議」によって決めた内容を記載して、相続人全員が署名押印した書面のことです。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効であり、無効な遺産分割協議によって作成した遺産分割協議書も無効となります。
無効な遺産分割協議書による相続手続きがやり直しになるリスク等があるため、適切な遺産分割協議書を作成しなければなりません。 なお、以下のような場合には遺産分割協議書が不要なこともあります。
- ●法定相続分に従って遺産分割する場合
- ●遺言書によって遺産分割する場合
- ●相続人が1人である場合
- ●相続財産が現金や預貯金のみである場合
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺産分割協議書が必要になるケース
遺産分割協議書は、法律で作成が義務づけられている書類ではありません。しかし、相続手続きで遺産分割協議書の提出を求められる場面は多いので、作成しておくべきでしょう。
遺産分割協議書の提出を求められる主な場所と、提出する理由については表をご確認ください。
| 提出場所 | 提出理由など |
|---|---|
| 税務署 | 相続税の申告を行うときに提出します |
| 金融機関 | 預貯金の口座を解約するときに提出します |
| 法務局 | 不動産の相続登記を行うときに提出します |
| 運輸支局 | 自動車の名義を相続人に変更するときに基本的には提出します |
なお、基本的には遺産分割協議書を用いた手続きでは原本を提出する必要があるため、コピーでは手続きができません。
手続きを行うときには、原本還付を申し出るようにしましょう。
法定相続分以外で不動産を相続する場合
法定相続分とは、法律で定められた相続財産の取り分の目安です。法定相続分により不動産を相続する場合には、遺産分割協議書は不要とされています。
ただし、複数の相続人が法定相続分によって不動産を相続すると、共有することになってしまいます。不動産を共有すると、売却が難しくなる等の問題が生じるおそれがあります。そのため、なるべく1つの不動産を相続する相続人は1人にするべきでしょう。
そこで、遺産分割協議書に相続人を明記して、相続登記を行うときに提出します。
金融機関での相続手続きをする場合
相続人が金融機関から預貯金等の払い戻しを受けるときに、遺産分割協議書を提出する義務はありません。各金融機関所定の書類に相続人全員が必要事項を記入すれば、遺産分割協議書がなくとも預金を解約することが可能なケースが多いです。
ただし、各金融機関所定の書類に相続人全員が必要事項を記入する等の煩雑な手間がかかるだけでなく、誰が預貯金を受け取ったのかについての証拠が残らないおそれがあります。
そのため、遺産分割協議書を作成して金融機関に提出することが望ましいでしょう。
相続税の申告が必要な場合
相続税とは、相続財産の金額が一定額を超える場合にかかる税金のことです。
相続税を納めるときには、遺産分割協議書の提出が義務づけられているわけではありません。しかし、被相続人の配偶者の税金を軽減するための措置等を受けるためには、必ず提出しなければなりません。
また、税金を軽減する措置等を受けない場合についても、国税庁は遺産分割協議書の提出を要望しているため、なるべく作成して提出するようにしましょう。
自分で遺産分割協議書を作成できる?
遺産分割協議書は、相続人が自分で作成することも可能です。
ただし、記載内容に誤りや不十分な点があると、相続手続きに支障が出る場合があります。
作成後には専門家に確認することをおすすめします。
遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議書を作成する流れは、主に以下のようなものです。
- ①相続人の確定
- ②被相続人の財産の確認
- ③遺産分割協議を行う
- ④遺産分割協議の作成
この流れについて、次項より解説します。
①相続人の確定
相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。
また、被相続人に、先に亡くなった子供がいる場合には、その子供が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要となる等、状況によって追加で戸籍謄本を収集しなければなりません。
遺産分割協議を行うときには、相続人全員が参加していなければなりません。相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議をやり直す必要が生じるため、相続人に漏れがないように注意しましょう。
②被相続人の財産の確認
相続財産は大きく2種類に区別することができ、相続人に利益をもたらすプラスの財産と、相続人に損失をもたらすマイナスの財産があります。
それぞれ、代表的なものとして以下のような財産が挙げられます。
【プラスの財産】
- ●現金
- ●預貯金
- ●株式
- ●国債・社債等の債券
- ●土地・家屋等の不動産
- ●自動車・バイク
- ●宝石・貴金属
- ●美術品・骨とう品
- ●著作権等の知的財産権
- ●ビットコイン等の暗号資産
【マイナスの財産】
- ●借入金
- ●ローン
- ●未払いの税金
- ●未払いの医療費
- ●飲食店等の未払い金(ツケ)
- ●連帯保証等の保証債務
財産を確定することができたら、財産目録を作成します。財産目録によって相続財産のすべてを確認できれば、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
③遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、相続財産の分け方等について話し合うことです。 ただし、全員が一ヶ所に集まって話し合う必要はありません。個別の同意や電話による話し合い、Web会議による話し合い等の方法でも有効です。
全員の合意があれば、その内容を遺産分割協議書にまとめて、郵送や持参等の方法で全員の署名と押印をしてもらいます。
なお、遺産分割協議で合意できなかった場合には、遺産分割調停や遺産分割審判によって遺産分割を行います。
遺産分割協議について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
④遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に記載するべき事項は以下のとおりです。
- ●被相続人の氏名
- ●相続人全員の氏名
- ●相続財産の内容
- ●それぞれの相続財産を受け取る相続人等
- ●後から判明した相続財産の分配方法
遺産分割協議書のひな形と書き方
遺産分割協議書は、一般的には以下のひな形のように記載します。ぜひご利用ください。
遺産分割協議書のひな形(テンプレート)
遺産分割協議書
被相続人の氏名 ●(●年●月●日死亡)
本籍地 ●
最後の住所 ●
生年月日 ●年●月●日
上記被相続人●の共同相続人である●及び●は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。
1.相続人●は、次の不動産を取得する。
所在 ●
地番 ●
地目 ●
地積 ●
2.相続人●は、次の預貯金を取得する。
●銀行 ●支店 ●(例:普通、当座、定期)預金
口座番号● ●円
3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人●がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を●通作成し、それぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。
●年●月●日
住所 ●
相続人 ● (実印)
住所 ●
相続人 ●
遺産分割協議書の作成する際のポイント
遺産分割協議書を作成するときのポイントについて、次項より解説します。
手書きでもパソコンでも構わない
遺産分割協議書は、決められた書式がなく、パソコン等を用いて作成しても問題ありません。
ただし、相続人の名前や住所は手書きすることが望ましいでしょう。なぜなら、相続人全員が参加して合意したことを証明する必要があるからです。
押印は実印を使用する
遺産分割協議書には、相続人の全員が押印する必要があります。このとき、押印に用いる印鑑は実印にしなければなりません。
これは、銀行や税務署等の機関が遺産分割協議書の提出を求めるときに、実印を押印して印鑑証明書を添付することを要求されることが多いからです。
必要な書類を集めておく
遺産分割協議書を作成するときに必要となる書類として、次のようなものが挙げられます。
- ●被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- ●被相続人の住民票の除票
- ●遺言書(作成された場合)
- ●検認済証明書(遺言書の検認を受けた場合)
- ●相続人の戸籍謄本
- ●相続人の印鑑証明書
- ●財産目録
作成期限について
遺産分割協議書の作成について、明確な期限は設けられていません。しかし、必要な手続きに間に合うように作成する必要があります。
例えば、相続税は基本的に相続の開始から10ヶ月以内に納税する必要があります。そのため、相続税を納税する義務がある場合には、10ヶ月以内に間に合うように遺産分割協議書を作成するべきでしょう。
遺産分割協議書は公正証書にするべきなのか
公正証書とは、公証役場において公証人が作成する文書です。 遺産分割協議書を公正証書によって作成する義務はありませんが、以下のような方は公正証書にするべきでしょう。
- ●代償分割によって相続する場合
- ●相続トラブルが発生するリスクがある場合
公正証書にするメリット
遺産分割協議書を公正証書にするメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- ①形式的な不備等により無効となるリスクが低い
- ②相続トラブルが発生したときの証拠としての価値が高い
- ③「執行認諾文言」を記載すれば金銭の支払について裁判をせずに強制執行ができる
- ④公証役場に20年間は保存される
公正証書にするデメリット
遺産分割協議書を公正証書にするデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- ①作成するときに費用がかかる
- ②公証役場に行く前に予約しなければならない
- ③作成するのに数週間かかることがある
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺産分割協議書についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
遺産分割協議書は、様々な機関に提出する重要な書類です。なるべく早く作成しておいた方が安心できるものであり、内容は正確に記載しなければなりません。しかし、被相続人の戸籍をすべて集めるだけでも大変な作業であり、思いもよらない相続人が存在するケースもあります。
そこで、遺産分割協議書を作成するときには弁護士にご相談ください。弁護士であれば、遺産分割協議に参加するべき相続人を特定する作業や、相続財産の内容を調べる作業等、様々な局面でアドバイスをすることが可能です。
相続税を納める必要がありそうな場合等では、時間の制限は厳しくなりますので、今すぐにでもご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)