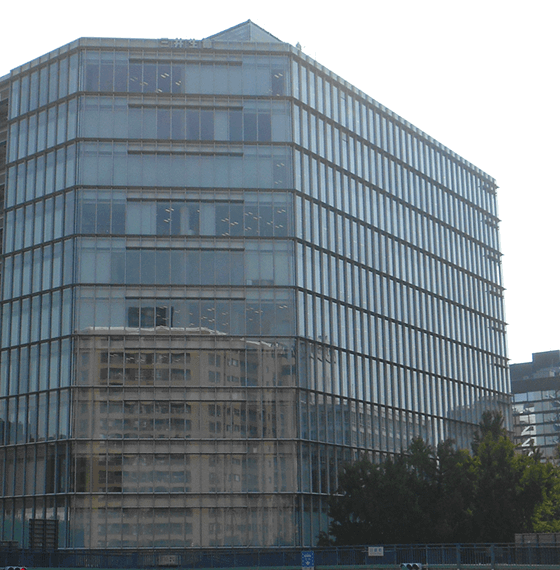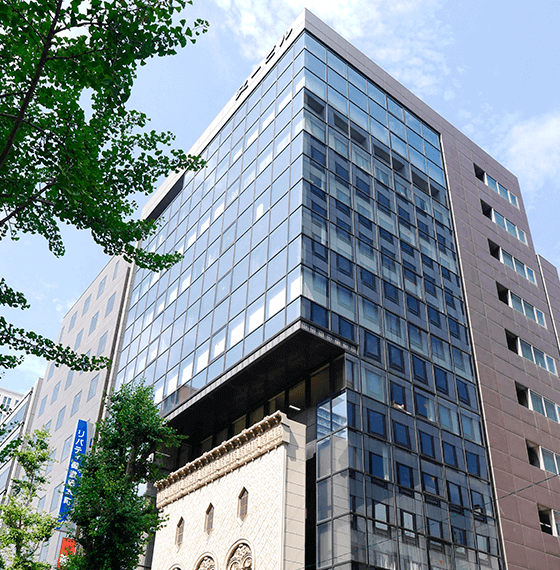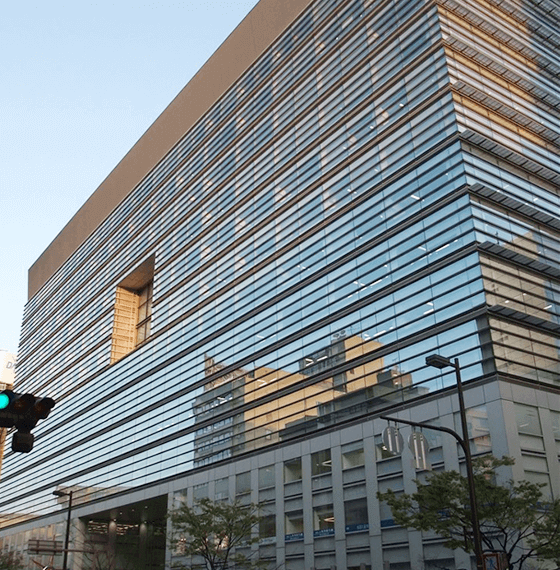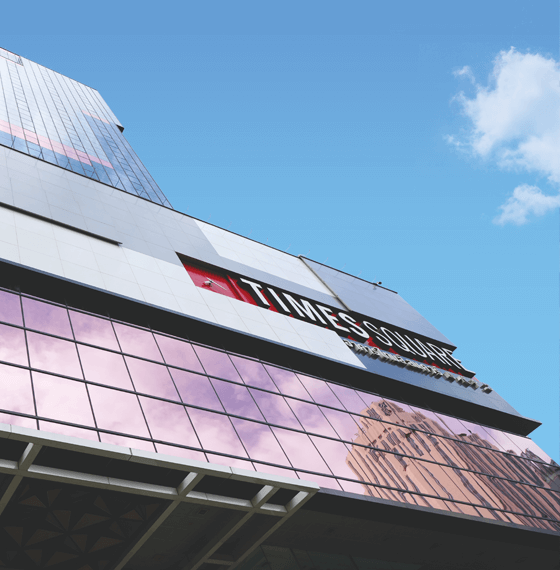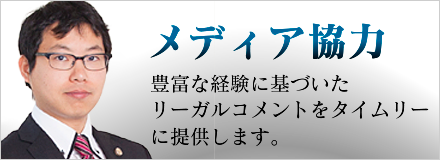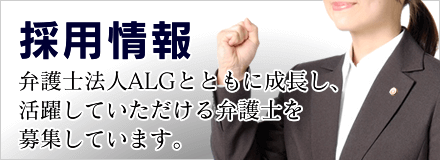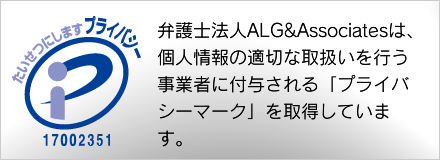遺産分割協議とは?必要性やケース別のポイント・注意点
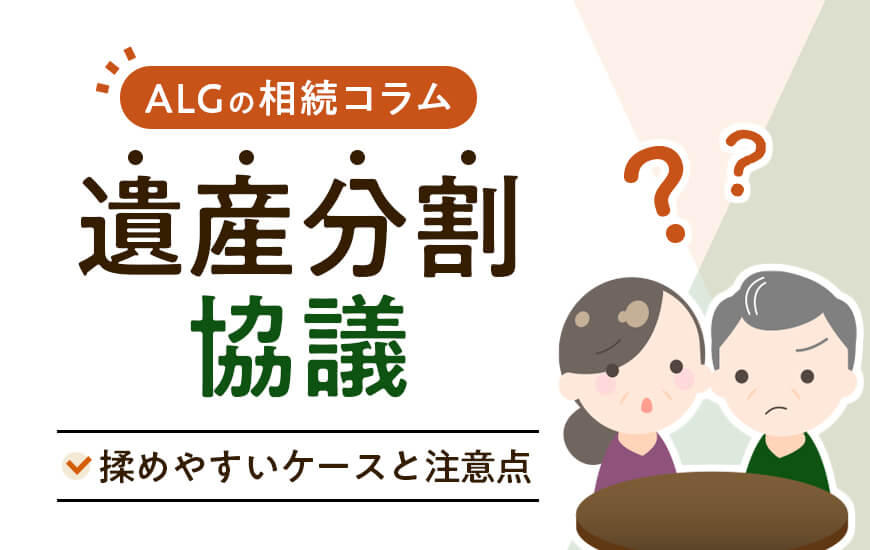
被相続人が亡くなると相続が発生します。相続人は誰なのか、相続財産には何があるのか、遺言書はあるのか。相続では調べることの連続です。調査を終えたら、次は相続人全員で相続財産の分け方について話し合うことになるでしょう。この協議も気をつけるべきポイントが多数あります。必要条件が揃っていなければせっかく行った話し合いも無効になるかもしれません。
本稿では1つずつ解説していきますのでしっかりと確認しましょう。
目次
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続財産の内容とその分け方について相続人全員が参加し、協議することを言います。この協議によって合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議のやり直しは原則不可
遺産分割協議は簡単にやり直せるのでしょうか。答えはノーです。遺産分割協議で一度合意した内容は、やっぱり気が変わった!などで覆せるものではありません。相続人全員の合意によって成立した内容には法的効力が発生します。協議内容を覆すことは困難ですので、安易に合意することは避けましょう。
全員の合意がなければ成立しない
遺産分割協議には絶対的な条件があります。それは相続人全員で合意することです。内容に反対する人が1人でもいれば協議は成立しません。多数決で確定するわけではないという点も覚えておきましょう。
また、相続人が1人でも欠けていると、その遺産分割協議は成立しません。後から協議に参加してない相続人がいた、とならないよう相続人の調査はしっかりと行いましょう。血縁関係は把握できていると思っても、被相続人の出生~死亡までの戸籍で確認が必要です。
相続人に未成年がいる場合
相続人が未成年である場合には、相続人であっても単独で遺産分割協議に参加することはできません。なぜなら遺産分割協議は法律行為に該当し、未成年は有効な法律行為を単独で行うことができないからです。また、通常未成年者についてはその父母や未成年後見人が法定代理人とし遺産分割協議を行うのですが、父母等自身も相続人であるケースが多々あります。この場合は、利益相反の問題が発生することもあり、父母等が法定相続人として協議に参加すると協議が無効になる可能性が高いため、裁判所へ特別代理人の選任を申立てる必要があります。特別代理人は相続に利害関係のない人物が選任されることが多く、手続きに時間がかかるため弁護士に相談した方が良いでしょう。
なお、成人年齢の引き下げにより、2022年4月1日からは18歳以上であれば遺産分割協議に単独で参加することが可能です。
相続人に認知症の人がいる場合
相続人が認知症を患っている場合、その症状の程度によっては遺産分割協議に参加することができません。認知症が進んでいると意思能力が認められず、その状態で法律行為である遺産分割協議を行うと無効になってしまうからです。
相続人の中に認知症の方がいる場合には法定後見制度を活用しましょう。法定後見制度は意思能力が不十分な場合に、不当に不利益な契約を結んだりすることのないよう、後見人等が本人に代わり法律行為を行うなど本人を保護するための制度です。法定後見制度は家庭裁判所へ申立をし、裁判所が後見人を決定します。
遺産分割協議でよく揉めるケース
土地や不動産がある場合
不動産は現金のように簡単に分けることができないため、誰か1人が取得するのか、もしくは相続人全員の共有にするのか決めなければなりません。前者のように相続人の1人が取得しても、他の相続人へ各人の相続割合を現金で支払えない場合はトラブルになります。
また、後者のように共有財産とすると、その不動産を売却しようと思っても共有者全員の同意が必要となり売却できないといった後々のトラブルが発生する可能性もあります。さらに不動産の評価額の査定方法についても各相続人によって主張が異なるケースもあります。
家業がある場合
家業がある場合には誰が後継者になるのかといった問題が発生します。
また、その後継者が家業に関する遺産内容を他の相続人へ開示せず、相続財産の全体が不明瞭なまま遺産分割協議を強行しようとするパターンもあります。
そして後継者が必ずしも家業を継ぐことに前向きとは限りません。我慢して後継者になったにもかかわらず、相続割合が等分になるのは納得できないといった心理的側面から遺産分割協議で揉めることもあります。
相続人以外が参加した場合
相続問題では、相続人以外の人間が意見することもよく見られます。例えば、相続人の配偶者にとっては相続財産の配分は決して他人事では無いため、自身の権利の有無にかかわらず遺産分割協議の場に参加する傾向があります。しかし、この場合の参加は利益を追求するためになることが殆どですので、遺産分割協議を乱す結果になることが多いでしょう。
遺産の分割方法
遺産の分割方法は4つに分けることができます。それぞれどういった特徴があるのかデメリットも踏まえて確認してみましょう。
現物分割
遺産をそのまま分ける方法が現物分割です。たとえば、自宅不動産は長男に、現金は長女に、株式は次男に、といった分け方です。
財産の種類ごとに相続するため、相続財産を細分化せずに残せるのがメリットですが、財産の種類によって価値に差があるため、各相続人に公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。
代償分割
特定の相続人が分割の難しい遺産を現物で取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払うことで相続割合の調整をとる方法です。
特に不動産が相続財産に含まれる場合には代償分割を選択されることが多いのですが、取得する相続人に金銭の支払い能力があることが必須となります。
換価分割
不動産など分割できない相続財産を売却などによって現金へ換金し、各相続人へ分配する方法です。不動産を取得したい相続人がいない場合や、代償分割するには代償金の準備が難しいといったケースでよく選択される分割方法です。
現金に換えることで相続財産を公平に分けることができますが、売却する手間や仲介業者への費用等の負担もあるので、相続人間で負担について事前に話し合っておく必要があります。また、売却すると譲渡所得税が発生する可能性がある点にも注意が必要です。
共有分割
相続財産を複数人で共有して相続する方法です。たとえば相続財産である不動産を複数の相続人で共有名義にし、各相続割合の持ち分を登記するのが一般的でしょう。
ただし、共有財産となれば処分行為を単独で行うことはできないので財産としての活用に制限があります。その状態で二次相続となった場合には、さらにトラブルの元になる可能性が高いと言えます。一度共有財産となったものを単独名義にするには共有物分割請求を行う必要があるので、共有分割の選択は慎重に行いましょう。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺産分割協議に期限はある?
法改正前に遺産分割協議の申立は10年とする法案が検討されましたが、現行法上、期限の上限は設定されていません。つまり相続が開始してから何年が経っていようとも協議は可能です。
ただし、民法改正によって特別受益と寄与分の主張については10年以内と制限されることになりましたので注意しましょう。
遺産分割協議をしないで放っておいたらどうなる?
遺産分割協議を行わずに放置しておくと、不動産については被相続人の名義のままとなり、固定資産税の支払いを誰が負担するのかといった副次的トラブルも発生するでしょう。
銀行口座についても凍結状態のままとなり10年経つと休眠口座になってしまいます。その場合には通常の相続手続きに加えてより多くの手続きが必要となるでしょう。
さらに、被相続人に借金があった場合、遺産分割協議も行わず相続放棄もしないままでいると単純承認したとみなされ債務を背負うことにもなります。放置せずできるだけ早く協議を進めるのが肝要と言えます。
遺産分割協議が無効になるケース
遺産分割協議は相続人全員が合意していることが絶対条件です。そのため、相続人が欠けた状態で行った協議は無効となります。
また、全員が揃っていても相続人の中に認知症や未成年者など判断能力に欠ける人が後見人等無しに行った協議であれば無効となってしまいます。
また相続財産の内容に漏れがあったなど、その情報があれば合意しなかったと認められる場合には錯誤として無効になります。
遺産分割協議のやり直しが必要になるケース
遺産分割協議が成立しても、新たに遺産が見つかりその遺産の存在を知っていればこの協議内容にならなかったと考えられる場合には錯誤により無効として協議のやり直しとなります。
また、協議成立後、協議書作成前に相続人が亡くなった場合、協議内容を証明できないのであれば、亡くなった相続人の相続人を含めて協議のやり直しを行うことがあります。まれに協議成立後に遺言書が見つかることがありますが、この場合には遺言書内容ではなく協議内容の合意を継続すると相続人全員の意見が一致していればやり直しは不要です。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺産分割協議に応じてもらえない場合にできること
遺産分割協議に応じない相続人がいる場合には、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対処法を知ることができます。
また、第三者が介入することで、その相続人が協議に応じてくる可能性もあります。それでも難しい場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てることも検討が必要でしょう。この点についても弁護士へ相談しておくと調停を申立てるタイミングなどもアドバイスを受けることができます。
そもそも遺産分割協議が必要ない場合
遺産分割協議は必ずしも全ての相続に必要というわけではありません。そもそも遺産分割協議を行う必要が無いケースもあります。その代表例をご紹介します。
遺言書がある場合
被相続人が遺言書を残しており、その内容に相続人全員が合意するのであれば遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、その遺言書が正しい様式にのっとって法定効力を持っている事が必要となります。
法定相続人が一人しかいない場合
法定相続人が1人しかいない場合には、他に相続人がいないので協議の必要性がありません。相続財産を1人で相続することになるので、財産調査を行い、相続放棄が必要かなどの見極めを行うことになります。
遺産分割協議のお悩みは弁護士にご相談ください
遺産分割協議は適切に行わなければ無効の可能性があるため、確かな知識が必要です。
そして、遺産分割協議に至るまでには相続人調査や財産調査が適切に行われていることも必須となりますが、決して簡単ではありません。協議が開始しても各相続人の意見が簡単にまとまるかは財産内容などによっても異なります。相続は調査~協議までケースバイケースですので、早期に専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けながら進めるのが最適な方法といえるでしょう。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)