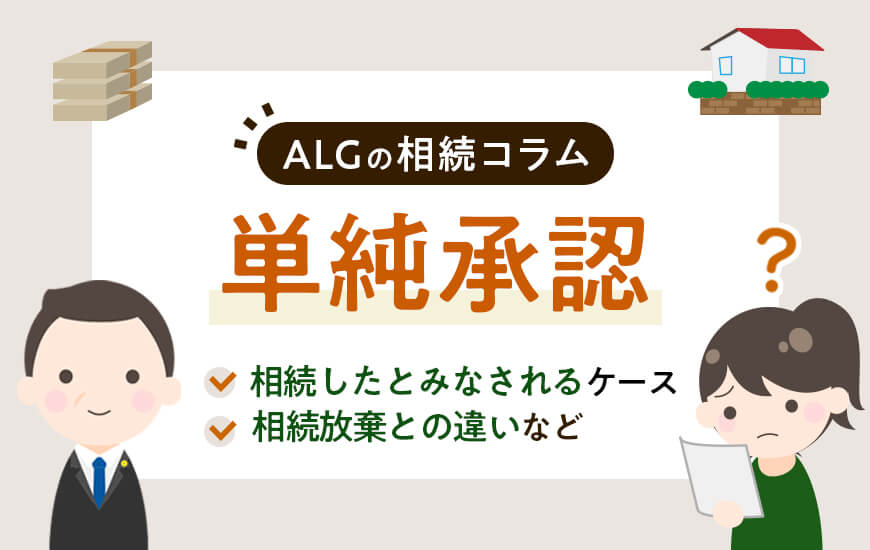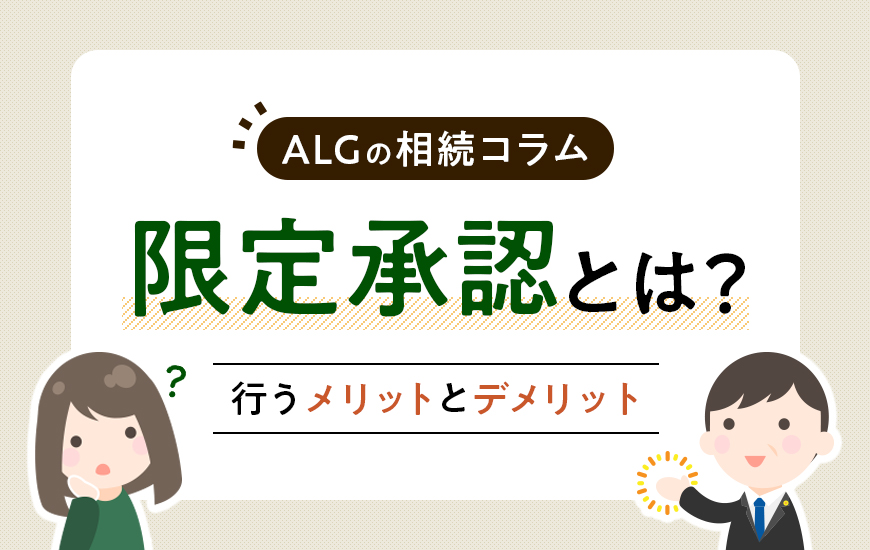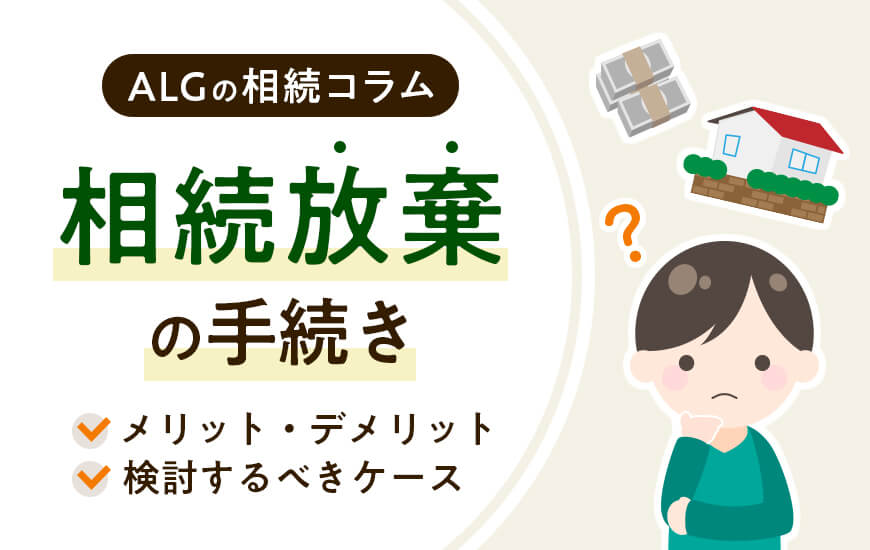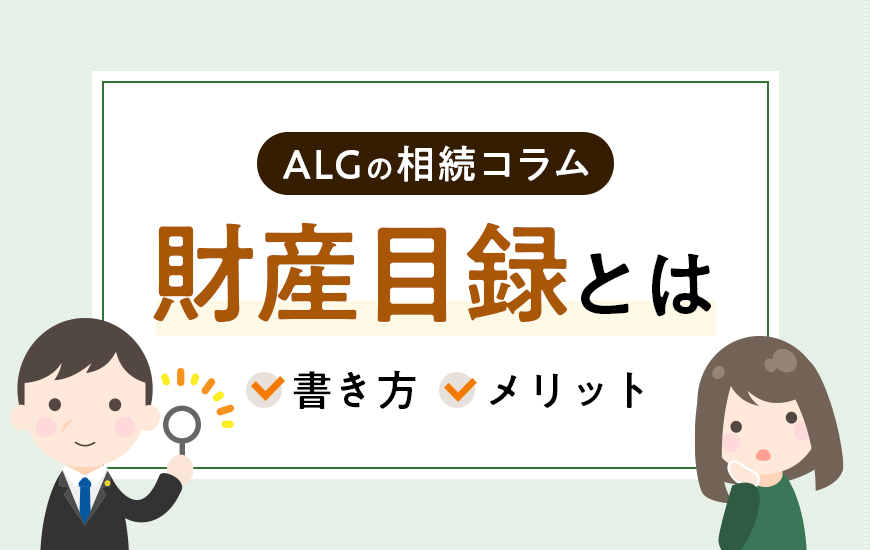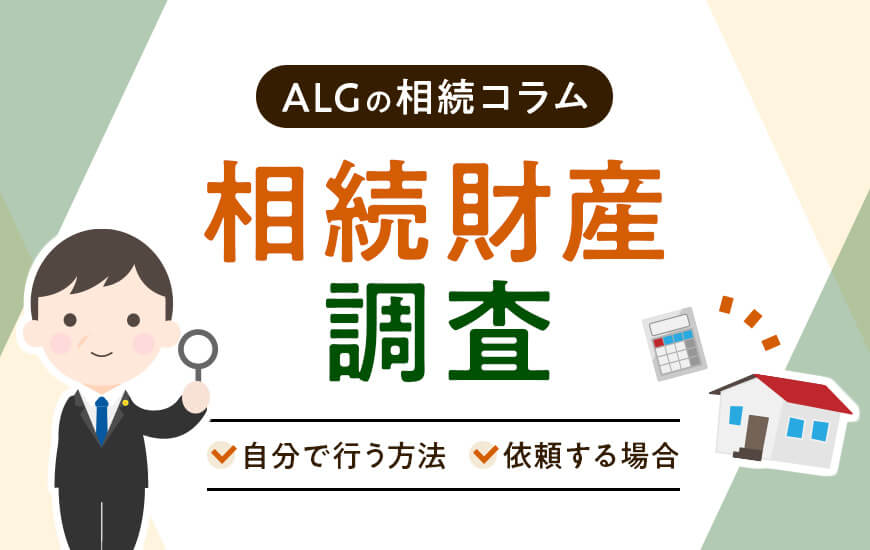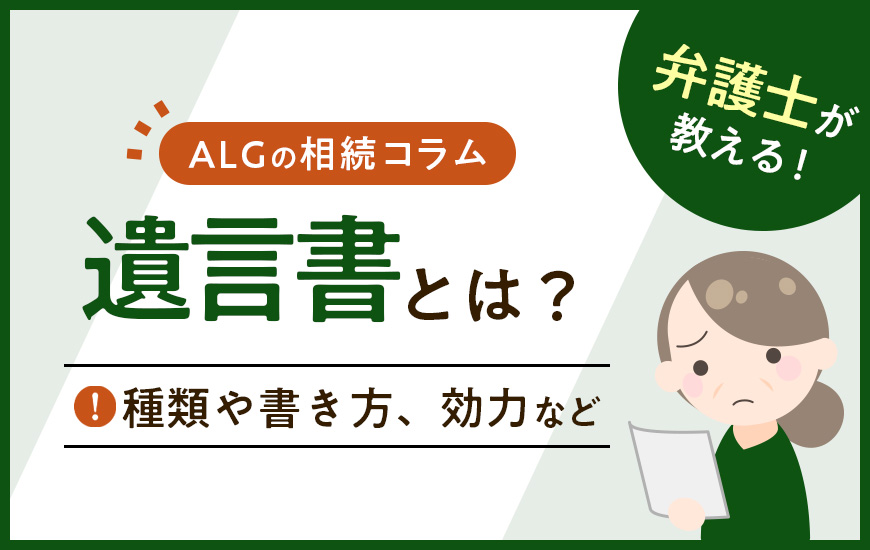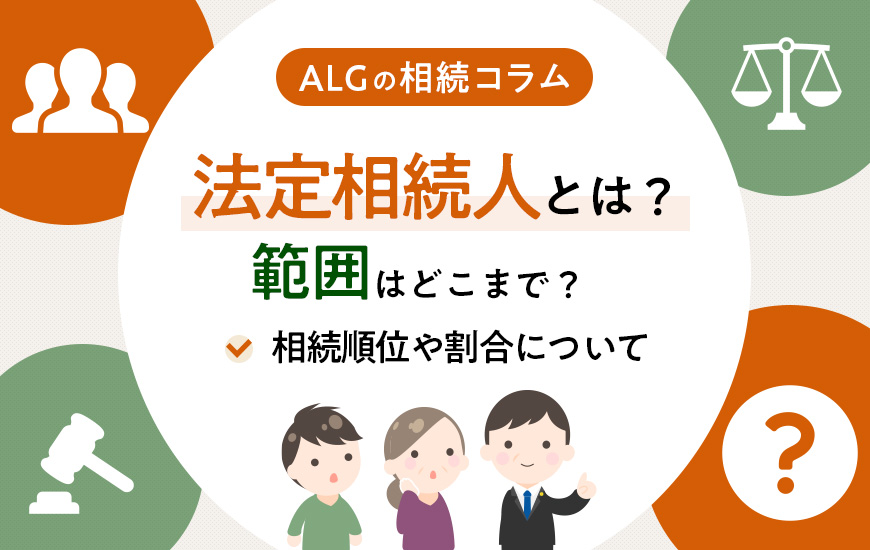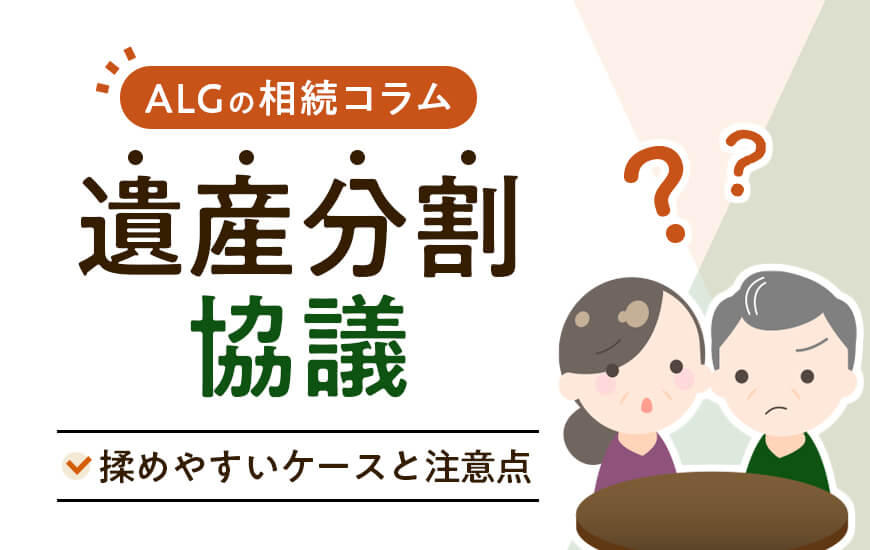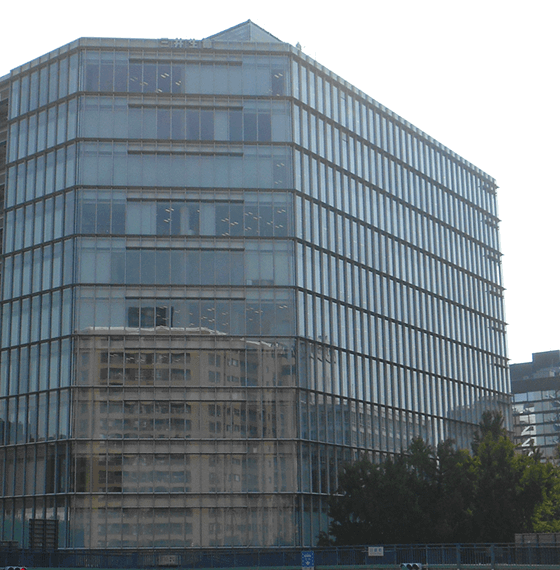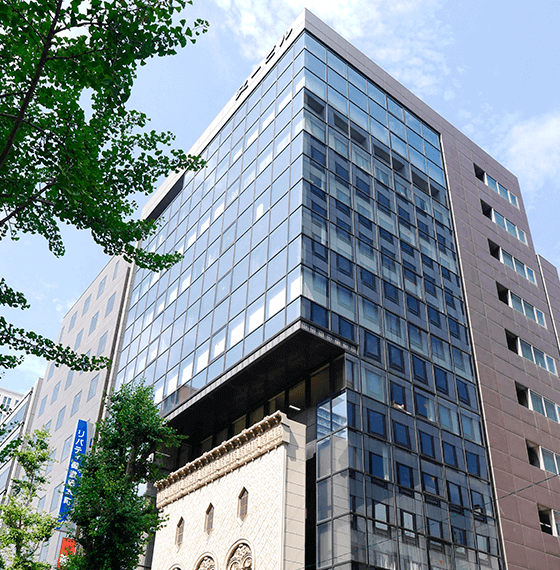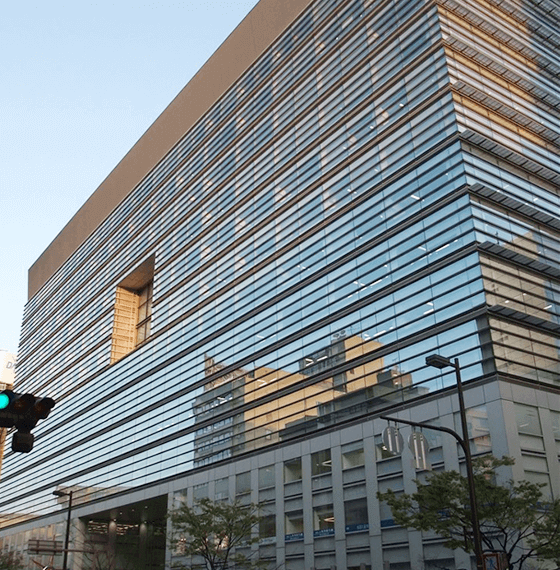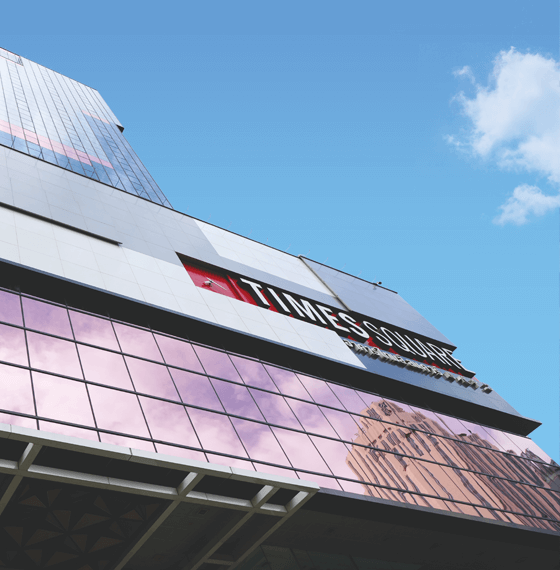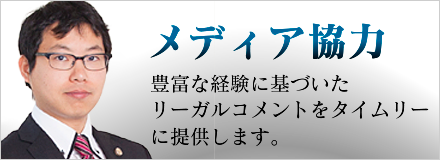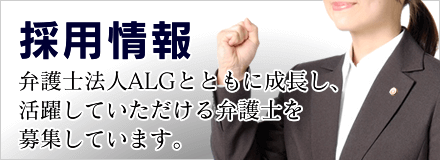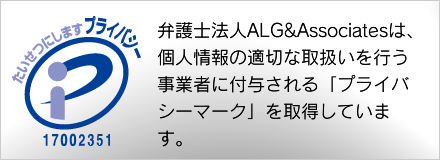相続手続きの一覧と期限について
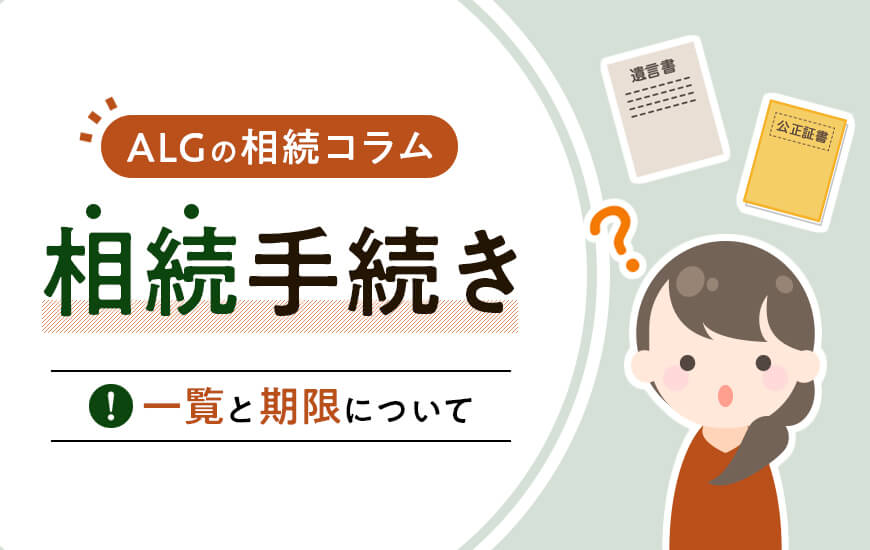
相続のはじまりは突然です。被相続人が事前に遺言書を書いていても、相続人は何から手をつければいいのか分からないことも多いでしょう。単に手続きがたくさんあるというだけでなく、それぞれの手続きに期限もあるので、優先順位をたてるのも一苦労です。
今回は期限ごとに必要な相続関連手続きについてまとめていますので、本稿を参考にして、焦らず1つずつ進めていきましょう。
目次
相続の手続きには期限のあるものが多い
被相続人が亡くなると相続の始まりです。葬儀の準備などで忙しい時期ですが、実は被相続人の死亡から1ヶ月以内に行う手続きもたくさんあります。それぞれ届け出る行政機関も違うので、煩雑になりがちですが放置すると行政罰の対象となる可能性もありますので、きちんと書類を提出しましょう。期限が短いものから順に説明していきます。
7日以内に必要な手続き
死亡届の提出
死亡届は死亡を知った日から7日以内に、被相続人の本籍地や最後の住所地などの市町村役場へ提出しなければいけません。この際、病院の死亡診断書などの添付が必要となりますが、死亡診断書や死亡届は、保険金の請求などで今後も必要となる重要な書類ですので必ずコピーをとって保管しておきましょう。
死亡届を提出することで火葬、埋葬の許可証をとることが可能になります。
10日以内に必要な手続き
被相続人の年金受給の停止(厚生年金)
被相続人が年金を受給していた場合には、その年金を停止する必要があります。年金事務所へ支給停止の申出書を提出しましょう。
停止の申し出には、被相続人の基礎年金番号や死亡が確認できる戸籍謄本等が必要です。受給状況によっては未支給年金、家族構成によっては遺族年金を受給できる可能性もあるので、あわせて年金事務所へ事前確認をしましょう。
14日以内に必要な手続き
保険証の返還
被相続人が健康保険に加入しているのであれば、その保険組合もしくは年金事務所へ資格喪失の手続きを行うことが必要です。
会社の健康保険であれば原則、勤務先で手続きを行ってくれるので会社の指示に従い保険証を返還しましょう。
被相続人が国民健康保険に加入していた場合は、市役所の窓口へ保険証を持参し、資格喪失手続きをする必要があります。
被相続人の年金受給の停止(国民年金)
厚生年金と同じく、国民年金を被相続人が受給していた場合も年金の受給停止手続きが必要となります。国民年金と厚生年金で期限は異なりますが、必要な書類や手続き場所は原則同じです。国民年金の場合にも未支給年金や遺族年金の請求ができる可能性がありますので、こちらも忘れず手続きを行いましょう。
3ヶ月以内に必要な手続き
相続方法の選択
相続する方法は3種類あることをご存じでしょうか。相続の開始から3ヶ月以内にどの方法で相続するのか選択する必要があります。選択する相続の方法によってメリット・デメリットがあるので確認しておきましょう。
単純承認
被相続人の財産をすべて相続する方法です。単純承認を行う場合は特に届出等が必要ないので最も簡単に行える相続といえます。
ただし、借金などのマイナスの財産についても相続することになるので相続財産をしっかり把握して選択する必要があります。
合わせて読みたい関連記事
限定承認
限定承認は単純承認と違い、マイナス財産の相続はプラス財産の価額が上限となります。つまり、プラス財産がマイナス財産を上回った場合のみ、清算後に残ったプラス財産を相続人が引き継ぐことになります。
限定承認は相続人全員で行う制度のため、相続人単独で選択することはできません。
合わせて読みたい関連記事
相続放棄
プラス財産、マイナス財産に関係なく、すべての財産を放棄する方法です。相続放棄は各相続人が1人で選択することができます。
相続放棄の撤回は原則としてできないので、財産調査をしっかり行った上で慎重に選択することが大切です。
合わせて読みたい関連記事
相続財産の調査、目録の作成
被相続人のプラス財産、マイナス財産を調査し、すべての財産を一覧形式とした目録を作成します。目録の作成に厳密な期限があるわけではありませんが、相続放棄等の手続きをする際に財産目録が必要となるので、相続放棄の期限である3ヶ月を目安として調査、作成を行うのが良いでしょう。
調査は単に預貯金などの確認だけでなく、不動産・動産の財産価値の調査や借入れ、未払いの税金確認等、複雑なものも多いため専門家への相談も検討しましょう。
4ヶ月以内に必要な手続き
準確定申告
1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額を相続開始から4ヶ月以内に申告・納税しなければいけません。この手続きを準確定申告といい、相続人全員の連署が必要となります。
手続きは被相続人の住所地の管轄税務署で行います。通常の確定申告と違い、社会保険料や民間の保険料についての控除証明書が自動的に届かないので、それぞれ支払についての資料準備等の時間が必要になるので早めに着手するようにしましょう。
10ヶ月以内に必要な手続き
相続税の申告及び納税
相続税には基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」があります。この額を超える相続財産があれば相続税の申告と納付が必要です。
申告期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などが発生するだけで無く、相続税減額の特例が適用されない可能性もあるので、必ず期限内に申告しましょう。
申告手続きは被相続人の最後の住所地にある税務署が管轄になります。相続税の申告には様々な資料が必要となるので、専門家への相談も早めに行うよう心がけましょう。
遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していない場合や、遺言書の内容と異なる分け方をする場合には、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。被相続人の財産について誰が、何を、どれだけ相続するか決まったら、その内容を遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書の作成に法的期限はありませんが、相続税の申告には各相続人の相続財産の内訳が必要となるため、相続税申告期限である10ヶ月を目安として進めてみましょう。
1年以内に必要な手続き
遺留分侵害額請求
遺留分とは、遺言書の内容等にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限確保できる相続財産の取り分です。相続した財産が遺留分よりも少ない場合には他の相続人に対して不足部分に相当する金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。この請求は相続を知ったときから1年以内にしなければなりません。
また、相続の開始を知らなかった場合であっても相続開始から10年経つと請求権は無くなります。
2年以内に必要な手続き
埋葬料・葬祭費の請求
被相続人が加入していた会社の健康保険や国民健康保険等から支払われる給付金です。相続人に対して支払われるのではなく、実際に葬儀を行った人が支給対象となります。支給額は埋葬に要した実費相当額(上限5万円)となっています。
ただし、被相続人が仕事中に亡くなった場合は、健康保険ではなく会社の労災保険からの給付となる可能性があります。労災保険の適用については被相続人が勤めていた会社へ確認しましょう。
3年以内に必要な手続き
生命保険(死亡保険)の生命保険会社への請求
被相続人が加入していた生命保険の死亡保険金は、自動的に支払われるのではなく必要書類を揃えて保険会社へ請求する必要があります。
相続開始後、被相続人が加入していた民間保険の調査を行い、保険会社へ連絡して請求書類を送ってもらいましょう。一般的な添付書類としては、被相続人の住民票や死亡診断書、受取人の戸籍謄本や印鑑証明書などが必要となります。保険金請求の期限は被相続人が死亡した日の翌日から3年が一般的です。
相続税の軽減措置
前述の通り、相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内と定められており、期限内に申告すれば配偶者の相続税額の軽減措置などを受けることができます。
しかし、10ヶ月以内に遺産分割協議が終わらないことも多々あります。このようなときは、法定相続割合で分割したとして申告書を作成し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。3年以内に分割協議が終えて更正の請求を行えば、遡って軽減措置が適用され相続税額の還付を受けることができます。
5年以内に必要な手続き
相続税の還付請求
相続税の還付請求は、相続税の申告期限から5年以内、つまり、相続開始から5年10ヶ月以内であれば申請可能です。
還付請求が可能となる事例としては、相続した不動産の評価額や投資信託の評価額の修正、未分割の財産を分割した場合などが代表的です。
評価額に疑問が残る場合には、評価のやり直しを検討しても良いでしょう。相続税の還付請求は相続人全員の総意がなくても、相続人単独で手続きができます。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
期限はないけれど速やかに行うべき相続手続き
相続手続きには厳密に期限が定められていないものも多数あります。
しかし、いつでも良いかというとそうではありません。なぜならその手続きを元に他の有期限の手続きを行う必要があったり、後からでは必要書類が発行できないなどの事情が発生するからです。期限があるものに比べて優先順位は低くなりがちですが、非常に重要なので忘れずに手続きしましょう。
法定相続人の確定
誰に相続の権利があるのか確定させるのが相続の第一歩です。なぜなら遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるからです。法定相続人が欠けた状態で遺産分割協議書を作成しても法的要件を満たせず、一からやり直しになる可能性があります。法定相続人は普段から知っている親戚だけとは限りません。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を必ず確認して下さい。誰も知らなかった子供の認知などは決してドラマだけの話ではないのです。
合わせて読みたい関連記事
遺言書の有無の確認、検認
被相続人が遺言書を残したか分からないケースも多いでしょう。遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
公正証書もしくは秘密証書遺言であれば公証役場の遺言検索システムが活用できます。また、2020年からは自筆の遺言書であっても法務局での保管が可能となりました。どの法務局でも遺言書の閲覧ができるのでこちらも確認したほうが良いでしょう。
秘密証書遺言もしくは自宅等で見つけた自筆証書遺言については家庭裁判所で検認手続きを受けなければいけません。検認手続きは未開封の遺言書を提出する必要があるので、遺言書を発見しても開封しないよう注意しましょう。
合わせて読みたい関連記事
遺産分割協議
遺産分割協議を行わなければ、誰がどの財産をどれだけ相続するのか確定することができません。つまり、いつまでも被相続人の財産を相続して自分の財産にすることができないのです。
また、遺産分割協議が長期にわたると相続税の軽減措置も受けられなく可能性があるなどデメリットは増えていきます。相続が始まったら、法定相続人を確定し、被相続人の財産を調査したら遺産分割協議をできるだけ早く進めましょう。
合わせて読みたい関連記事
預貯金などの解約、名義変更
相続が始まると預貯金などは相続人全員の共有財産となるため、遺産分割協議が完了するまで金融機関はその口座を凍結します。預貯金の解約や名義変更については特に手続きに期限は定められていません。
しかし、10年以上利用のない口座は休眠口座となり、預金の引き出しに追加の手数料や追加書類が必要になったりするので、相続したら早めに手続きしましょう。
(不動産を相続する場合)相続登記
不動産を相続したら、相続登記を行い、第三者に対して正当な所有権を証明できるようにしましょう。
現在は相続登記をしていなくても罰則などはありませんが、2024年4月からは相続登記が義務化されます。義務化後は、相続財産として取得後、3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく登記をしない場合には罰則が科されることもあります。
(車やバイクを相続する場合)名義変更
車やバイクを相続した場合、そのまま使用もしくは売却のいずれであっても名義変更を行いましょう。法的期限はありませんが、時間が経つと遡って取得するのが難しい書類もあるので、早めに手続きするのが得策です。
また、相続発生時の名義確認もしっかり行いましょう。車などの場合、ローン完済までは名義が信販会社などになっている可能性もあり、注意が必要です。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の手続きは自分でできる?
相続の手続きは相続人が自身で行うことももちろん可能です。しかし、相続手続きは非常に複雑で事案ごとに提出先や準備書類が異なります。
また、住民票や戸籍謄本など役所で入手する書類が多く、個人が手続きを行うには、平日に仕事を休む必要もあるでしょう。
そして、その多くは1日、2日では到底終わりません。特に相続財産の調査は、調査不足により多額の負債を抱える可能性もあるので、専門的な知識が必要になります。
また、関係各所とのやり取りでは専門用語も出てくるので内容の把握にも時間がかかります。自力でやっても簡単な手続きもあるかもしれませんが、様々な手続きに膨大な時間がかかる可能性も高いので、その手間を少しでも負担に感じられたら専門家に相談することも考えてみてはいかがでしょうか。
相続手続きについてわからないことがあったら弁護士にご相談ください
相続が始まると相続人が行う手続きは事案によって多種多様です。一つ一つの手続きに時間がかかるだけで無く、その多くに期限が設定されているので優先順位を決めながら行わなければなりません。そして手続きには相続人1人だけでは行えないものもあるので、他の相続人への確認が必要となる場面もあります。
相続には似た事案はあっても、まったく同じものはありません。ご自身の相続内容について少しでも不安や疑問を持たれたのであれば、まずは弁護士へご相談ください。相続の専門家である弁護士なら、あなたの相続に最も適したアドバイスをし、心強い味方となることができます。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)