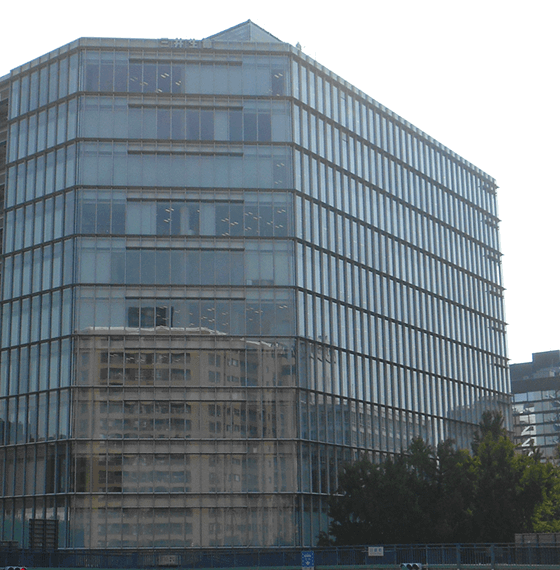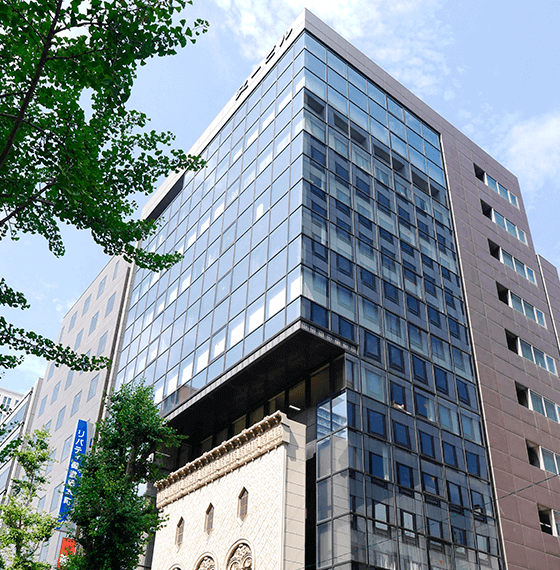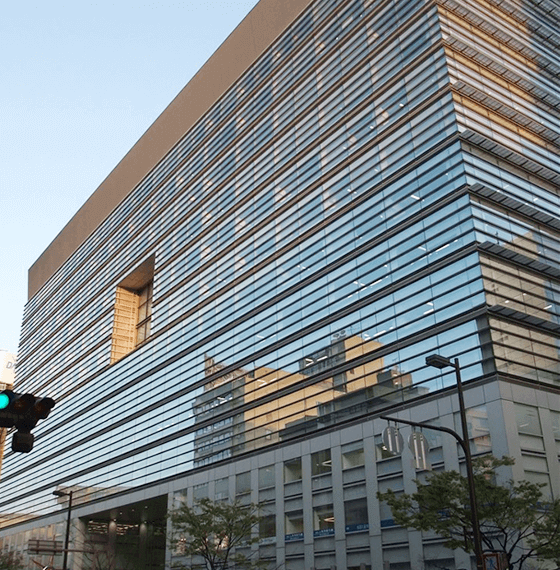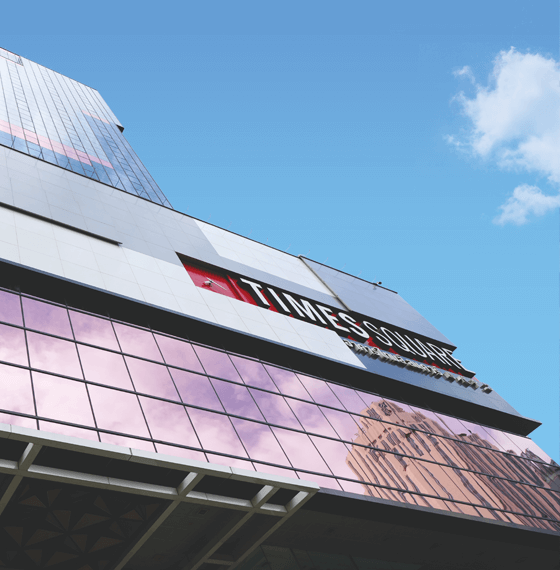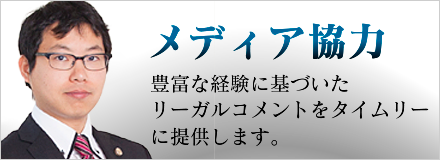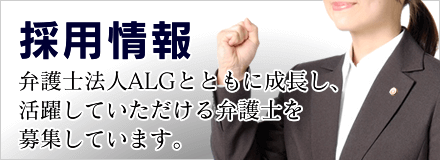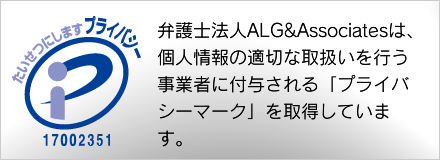遺言書とは?種類や書き方、効力などの基礎知識
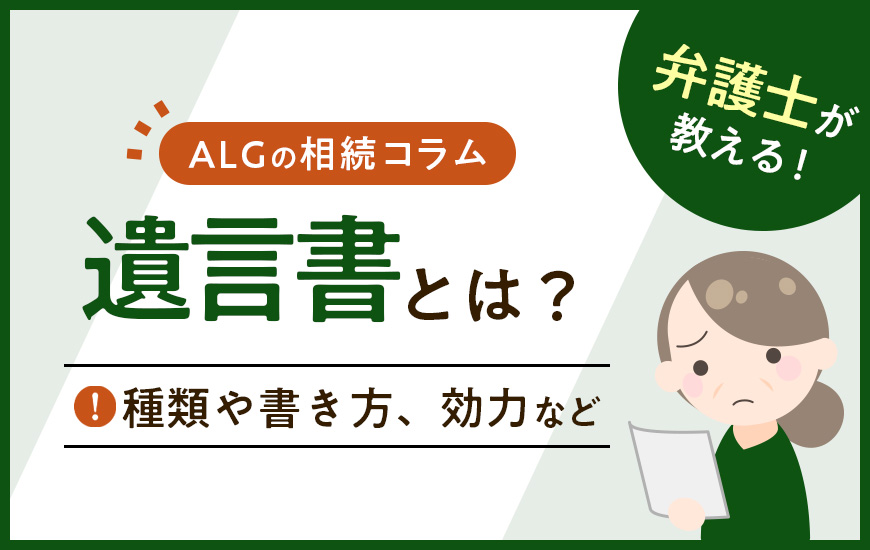
この記事でわかること
相続トラブルを防止するには遺言書の活用が有効です。しかし、遺言書に法的な効果をもたせるためには、正しい形式での記載や法的な手続きが必要です。
遺言書は故人の最後の意思を伝える大切なものです。その意思を相続に正しく反映させるためにも、遺言書について詳しく知っておくようにしましょう。
この記事では、遺言書の種類や書き方、必要な手続き等について解説します。
目次
遺言書とは
遺言書とは、被相続人(故人)が死亡後にその意思を実現させるためのものです。例えば、自身の財産について、誰に何を引き継がせるかといった相続の分配方法などが主流です。
遺言は、法律の定めにのっとった書面にすることで、法的効力を発揮します。特に、法定相続人以外に財産を引き継がせたい場合や、法定相続割合とは違った比率で分配したい場合などに非常に有効です。遺言書は、満15歳以上であれば誰でも作成できます。
遺言書の効力
遺言書には、主に次のような効力があります。
- ・遺言執行者の指定
- ・相続分の指定
- ・相続人が取得する遺産の内容の指定
- ・遺産分割の禁止
- ・遺産に問題があった時の処理方法の指定
- ・特別受益の持ち戻しの免除
- ・生命保険の受取人の変更
- ・非嫡出子の認知
- ・相続人の廃除
- ・未成年後見人の指定
遺言書の効力について、詳細な内容を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言書が無効になるケース
遺言書が無効になるケースとして、以下のようなものが挙げられます。
●遺言書としての形式を満たしていない場合
自筆証書遺言や秘密証書遺言については遺言者が自分で作成する為、日付や署名押印の漏れといった不備によって無効になるケースがあります。公正証書遺言については専門家である公証人が作成するので不備による無効は少ないです。
●遺言者が遺言書を作成した時の意思能力に問題がある場合
作成時に認知症などを発症し、正確に判断する能力が失われていたと認められると、その遺言書は無効となります。意思能力の有無を確認するには医療記録や当時の動画などが必要なので、経験のある専門家の協力を仰いだ方が良いでしょう。
遺書、エンディングノートとの違い
| 遺言書 | 自身の財産やそれを受け取る者などについて記載し、法的な効力をもつ書類 |
|---|---|
| 遺書 | 自身の考えや、親しかった者に伝えたい言葉などを記載した手紙 |
| エンディングノート | 自身の終末期に対する希望や、所有財産の内容、葬式やお墓、家族への感謝などを伝える書類 |
遺言書と混同されやすいものとして、「遺書」や「エンディングノート」があります。形式は自由であり、法的な効果は意識しないのが一般的です。
どれも、親しかった者に自身の意思を伝えるものですが、その意思を法的に実現させることを目的とするのが遺言書、意思を伝えること自体を目的とするのが遺書やエンディングノートです。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺言書の種類
法的効力をもつ遺言書には以下3種類があります。
| ①自筆証言遺言 | 遺言者本人が本文・氏名・日付を自筆します。財産目録についてはパソコンによる作成が可能です。法務局の補完制度を活用することができます。 |
|---|---|
| ②公正証書遺言 | 遺言者が話した内容を公証人が遺言書として作成し、公証役場で遺言書原本を保管します。 |
| ③秘密証書遺言 | 証言者が作成した遺言書を、公証役場で封印し、保管します。内容を公証人が確認しない為、遺言書の形式に不備の可能性があります。 |
どの形式を選ぶかは遺言者の自由です。また、どの遺言書であっても法的効果は同じです。相続人が探しやすいように、どの遺言書を作成したのかを伝えておくと良いでしょう。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、被相続人が原則全文を自筆して押印することによって作成する遺言書です。思いついたときに自由に作成できるのが特徴であり、気軽に作り直すこともできます。
自筆証書遺言のメリットとデメリットについて、下の表をご覧ください。
| メリット | ・ほとんど費用をかけずに作成できる ・内容を誰にも知られることなく作成できる |
|---|---|
| デメリット | ・ミスなどにより無効となりやすい ・自筆しなければならないため負担が大きい ・紛失するリスクや改ざんされるリスクがある ・原則検認手続きを行わなければならない |
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人により作成してもらう遺言書のことです。基本的には公証役場に出向いて作成してもらいますが、身体が不自由である等の事情がある場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。
| メリット | ・公証人が作成するため無効になるリスクが低い ・自筆する必要がないため負担が軽い ・検認手続きを行う必要がない |
|---|---|
| デメリット | ・作成するために費用がかかる ・2人の証人が必要である |
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書が存在する事実を公証人に証明してもらいながら、内容は秘密にできる遺言書です。いくつかのメリットがありますが、無効となるリスクがなくならないため、実務ではあまり利用されません。
| メリット | ・パソコン等を使って作成できる ・遺言の内容を他者に知られずに済む ・遺言者が作成したことを証明できる |
|---|---|
| デメリット | ・ミスなどにより無効となるおそれがある ・費用がかかる ・2人の証人が必要である ・検認手続きを行わなければならない |
遺言書の保管場所
| 遺言書の種類 | 保管場所 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅等あるいは法務局 |
| 公正証書遺言 | 公証役場 |
| 秘密証書遺言 | 自宅等 |
遺言書の種類によって保管される場所は異なります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言については保管場所が限定されておらず、基本的には自宅等で保管します。ただし、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうこともできます。
公正証書遺言の場合、平成元年以降の作成分については公証役場で保管されています。
遺言書の書き方
自筆証書遺言を作成する場合には、次のポイントを押さえておく必要があります。
- ・全文を自筆すること(財産目録を除く)
- ・日付が特定できるように記入すること
- ・署名押印すること
- ・遺留分に配慮しながら作成すること
遺言書は、なるべく早く作成して、できれば定期的に作り直しましょう。自筆証書遺言は、紙の代金などを除けば作成費用がかからないため、直近の財産の状況を反映するのが望ましいでしょう。
なお、自筆証書遺言を法務局に預かってもらうためには、3900円の手数料がかかります。
遺言書の検認とは
検認とは、遺言書の内容を家庭裁判所で確認し、その存在や内容を相続人に知らせる手続きです。
遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してしまうと法律違反となり、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
遺言書を発見したら、開封する前に家庭裁判所へ検認を申し立てます。この手続きは、必要書類を家庭裁判所へ提出すると、検認を行う日が確定します。その検認期日に申立人や相続人が立ち会い、裁判官が遺言書を開封して状態を確認します。
しかし、検認の申立てはすべての遺言書に必要な手続きではありません。この手続きは、遺言書の状態などを明らかにして、偽造や改ざんなどを防ぐためのものです。そのため、原本が公証役場で保管されている公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言については検認不要です。
知らずに開けてしまった場合の対処法
遺言書を、検認の手続きを行わずに開けてしまったら、そのことを家庭裁判所へ報告したうえで検認の手続きを進めることが必要です。
開けてしまっても、それだけで遺言書が無効になったり、相続人としての資格を失ったりするおそれは基本的にありません。
ただし、開けてしまった遺言書を隠すことや、廃棄することは厳禁です。もしも隠蔽や廃棄をしてしまうと、相続人としての資格を失うリスクがあります。
遺言書は絶対?ケース別の遺言書の疑問
遺言書がある場合、民法の内容よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書で遺産分割をどう指定するかは遺言者の自由なので、分配される割合が民法で定めた法定相続分を下回ることもあります。
そこで、遺言書に納得できない場合等について以下で解説します。
遺言書の内容に納得できない場合
遺言書の内容に納得できない場合、まず、その遺言書の有効性を確認してみましょう。
遺言書の有効性とは、
① 遺言書作成時に被相続人がしっかりとした判断が可能な意思能力があったか
② 遺言書の形式に不備は無いか
という2点です。
遺言書の有効性に問題がないようであれば、次に遺留分の権利を主張しましょう。遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について保障されている最低限の取り分です。
遺留分は自動的に貰えるわけではなく、希望する相続人が請求の意思表示を行うことが必要です。
遺言書に反対する相続人がいる場合
反対する一部の相続人がいることで手続きが難航するようであれば、家庭裁判所へ「遺言執行者」の選任を申し立てるのが良いでしょう 。 遺言執行者には、遺言の内容を実行するために必要な行為をする権利と義務があります。そして、相続人がその行為を妨害することは許されず、そのような行為は無効となります。
ただし、遺言執行者の存在を知らなかった第三者に権利を譲られてしまうと、無効であることを主張できなくなるおそれがあります。そのため、遺言執行者がいるとしても、手続きを急ぐ必要はあります。 遺言執行にあたっては権利関係が複雑であることも多いので、弁護士などの専門家であれば安心して任せられるでしょう。
遺言執行者について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
遺言書の内容に相続人全員が反対している場合
次のような場合は、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことは可能です。
【遺言により財産を取得する者(受遺者)も含めて、全員が遺言内容に反対し、かつ遺産分割協議の内容に全員が納得している】
例えば、遺産をすべて寄付したい、愛人に財産を渡したいといった内容の遺言書だと、多くの相続人は拒否反応を示すことでしょう。そのようなときには、財産を贈られた者も同意していれば、遺言書と異なる結果になっても問題ありません。
ただし、遺言書に、遺言内容と異なる遺産分割の禁止が記載されていた場合は、遺産分割協議による変更が不可能となります。このときには、受遺者に遺贈を放棄してもらう方法が考えられます。
遺言書に遺産分割協議を禁止すると書かれていた場合
遺言書により5年を超えない範囲の期間で財産の全部、または一部の分割協議を禁止することができます。これは相続人のなかに未成年者がいるなど、相続開始時点ではトラブルが生じそうだと判断した場合に有効な手段です。
この分割協議の禁止が遺言書に書かれていると、たとえ相続人全員が反対したとしても、原則として、指定された期間内は遺産分割協議を行えないことになります。
分割協議の禁止事項があれば、その遺言書の有効性について弁護士へ確認した方が良いでしょう。
遺言書で指定された財産を受け取りたくない場合
基本的には、遺言書に記載された特定の財産について「遺贈する(相続させる)」とされていた場合、その特定の財産の受け取りを拒否できます。
しかし、遺言書に相続人の取得割合が記載されており、その中に不必要な財産が含まれている場合には、特定の財産の取得だけを拒否することはできません。このように、相続財産の一定の割合を指定する遺贈を「包括遺贈」といいます。
包括遺贈では、不必要な財産を含めて遺贈を受けるか、全ての遺贈を放棄するかを決める必要があります。包括遺贈を放棄する場合には、相続放棄の手続きを行います。
ただし、包括遺贈でも、相続人や受贈者等の全員が協議して遺言書と異なる遺産分割をすることは可能です。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺言書について弁護士に依頼するメリット
遺言書について弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
・有効な遺言書を間違いなく作成できる
遺言書は、形式的なミスによって無効となるリスクがあるだけでなく、2つの意味に解釈できる文言を書いてしまう等のミスをするリスクがあります。弁護士に依頼すれば、注意点についてわかりやすく教えてもらえます。
・遺言書についてトラブルが発生した場合にも相談できる
遺言書の内容に納得できない者などが有効性を争ってきても、すぐに相談して対応できます。
・遺言執行者として指名できる
遺言執行者は、基本的に誰を指名しても良いのですが、手続きの負担が重く、財産を隠した等の疑いをかけられてしまうリスクもあります。いざというときには、弁護士を指名できるようにしておくことが望ましいでしょう。
遺言書に関するよくある質問
遺言書が2通以上出てきた場合はどちらが有効になりますか?
遺言書が2つ以上あるケースは実は珍しくありません。なぜなら遺言書は何度でも作成しなおすことができるからです。基本的には作成日が最も新しいものが有効な遺言書となります。
しかし、それぞれの遺言書の内容が、同一の財産について書かれているとは限りません。例えば古い遺言書に「Aの土地は相続人Bに」、と記載され、新しい遺言書に「Cの土地は相続人Dに」と記載されていた場合、この2つの遺言は違う財産についての指定であり、内容が重複しないので、どちらも有効な遺言内容となります。
遺言書にない財産が後から出てきた場合はどうなりますか?
遺言書に記載されていない財産は、その財産の分割方法が指定されていないので、相続人全員による遺産分割協議によって決めることになります。
ただし、遺言書の内容が個別の財産ごとに分割方法を指定する形式(例えば、「不動産Eは相続人Fへ」などの内容)ではなく、包括的な割合の指定(例えば、「遺産の2分の1を相続人Gへ」などの内容)であれば、遺言書に記載されていない財産であっても、この遺言書に指定された割合によって相続することになります。
また、遺言書に含まれない遺産が生じないように、遺言書には「その他、本遺言書に記載のない遺産は、全て相続人Aに相続させる」等と、記載しておくのが良いでしょう。
遺産分割協議の後に遺言書が出てきた場合はどうしたらいいですか?
遺言書の形式が有効なものであれば、遺産分割協議が終わっていたとしても遺言書の内容が優先されます。「せっかくみんなで協議したので見なかったことに・・・」と思うかもしれませんが、遺言書が無いことを前提とした遺産分割協議は、原則無効となります。もちろん遺言書が見つかった後も、相続人全員の協議により、以前の合意と同じ内容で分割することに合意ができれば有効となります。
ただし、遺言書には法定相続人以外の者(受遺者)に遺贈させることが書かれていることもあります。この場合には、受遺者を含めて改めて協議をすることが必要になります。
遺言書に関するトラブルは弁護士にご相談ください
遺言書は被相続人の意思を相続人に伝え、その意思を反映させた相続を実現するのにとても有用な制度です。しかし、その作成に不備が生じやすいだけでなく、保管場所が分かりにくく見つけられなくなるなど、運用のつまずきによって無用のトラブルを発生させてしまうこともあり得ます。
遺言書について不安があれば専門家である弁護士が適任です。弁護士は遺言書を作成するだけでなく、遺言執行者となることもできます。そして、遺言書を発見したあとも、弁護士であれば必要な手続きや、分割についてなど広くアドバイスすることができます。被相続人の意思を尊重し正しく受け継ぐためにも、まずは弁護士へご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)