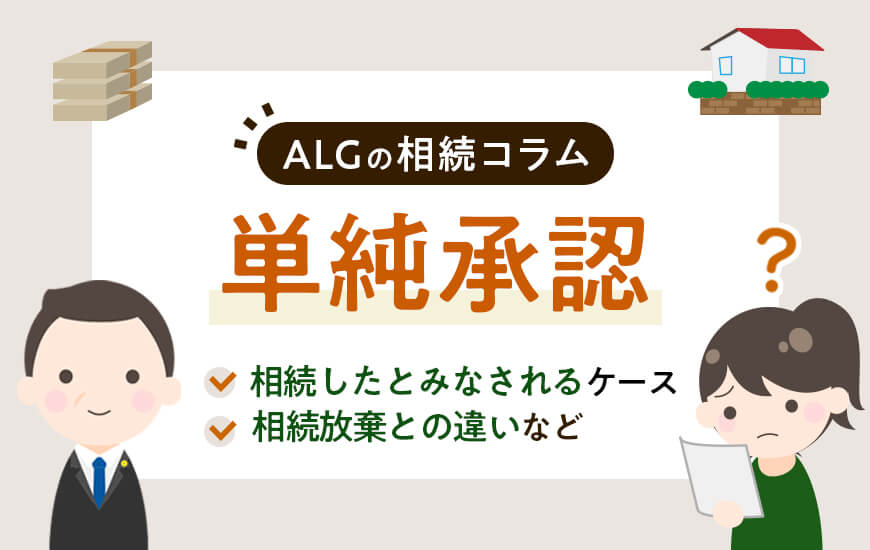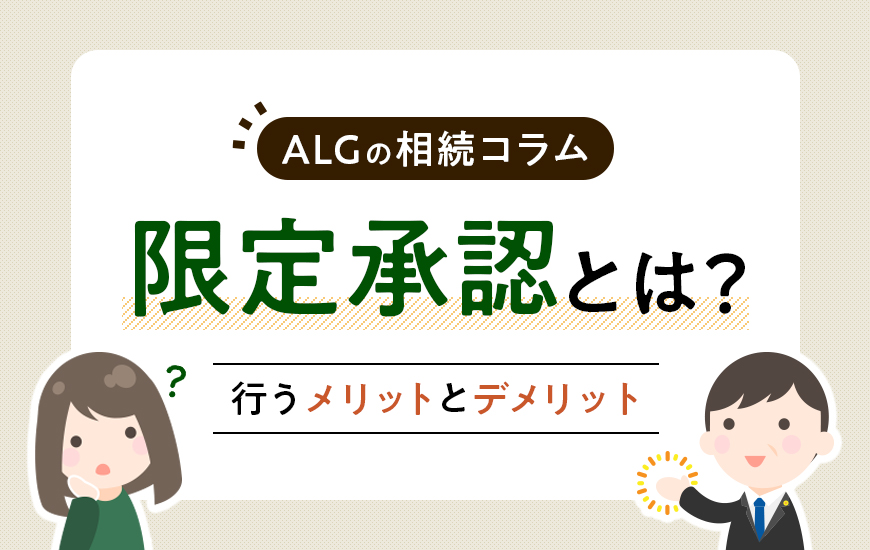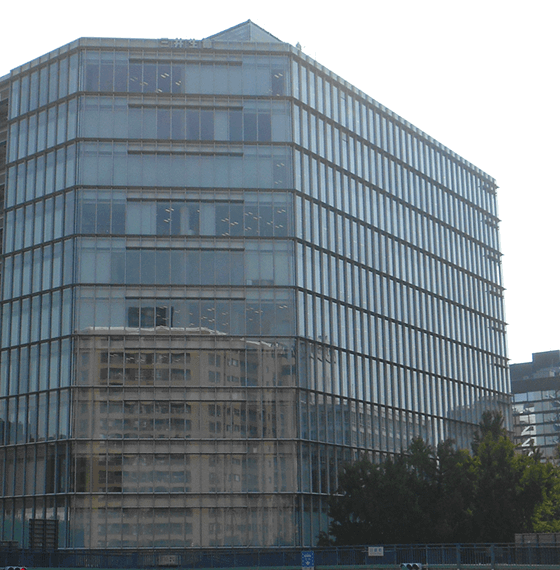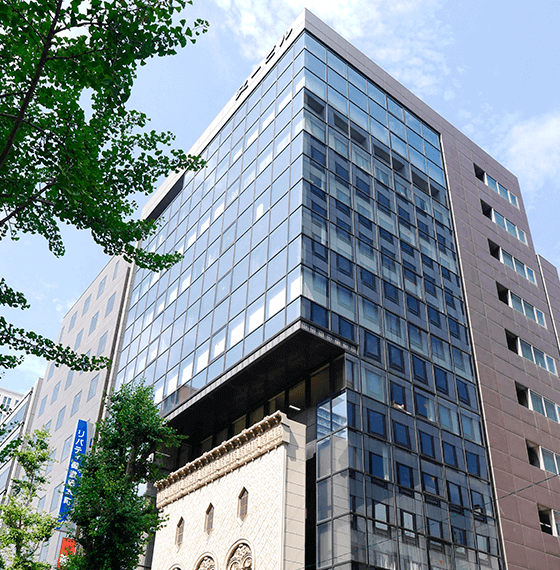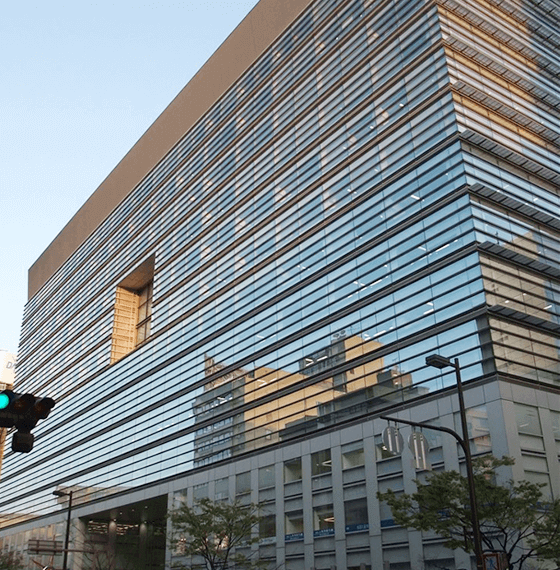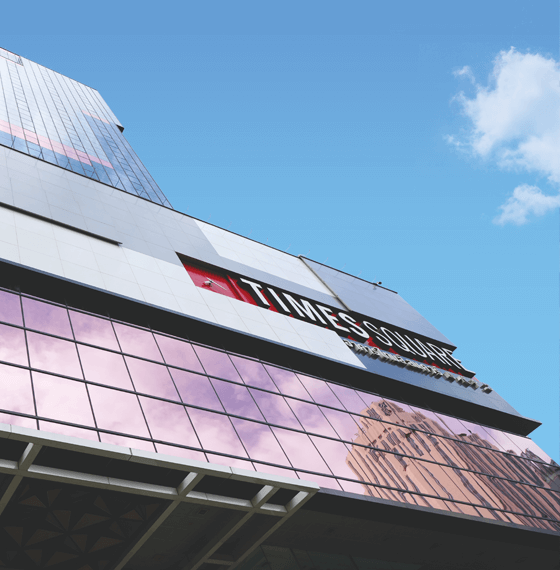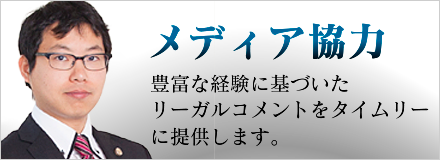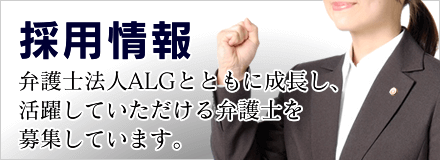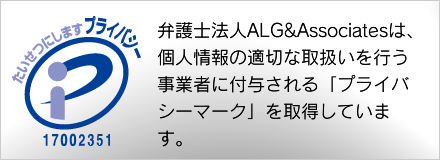相続放棄の期限は3ヶ月!延長する方法・過ぎてしまった場合の対処法
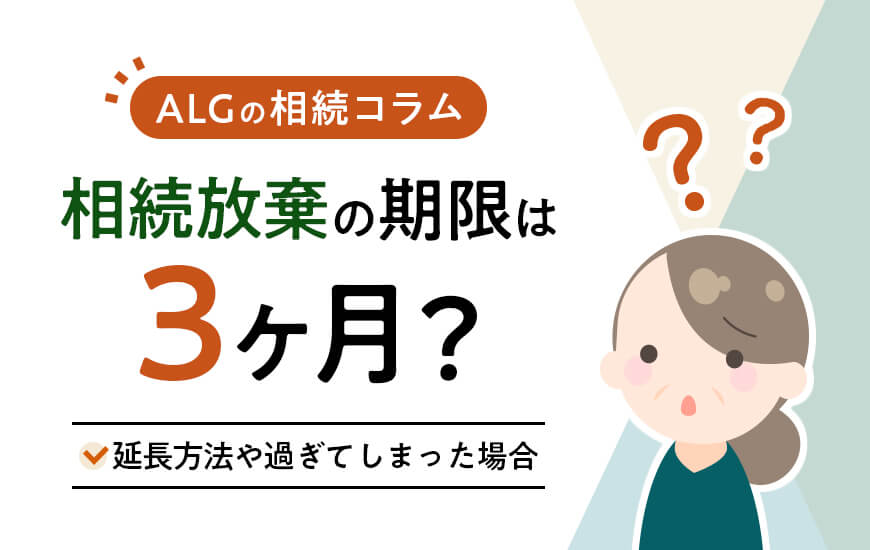
被相続人が亡くなると相続人は、遺産をある程度把握した上で、一つの判断をする必要があります。それは「相続するか」もしくは「相続放棄するのか」。非常に悩ましい問題ですが、実は相続放棄できる期間は限られています。決断できなかった、では済まない相続放棄。本稿で相続放棄のルールを知り、決断までのタイムスケジュールを確認しておきましょう。
目次
- 1 相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方
- 2 理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません
- 3 相続放棄の期限を延長する方法
- 4 3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?
- 5 相続放棄の期限に関するQ&A
- 5.1 相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?
- 5.2 相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?
- 5.3 亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?
- 5.4 先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。
- 5.5 相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。
- 5.6 相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?
- 6 相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください
相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方
相続放棄の期限は、ずばり3ヶ月以内です。この3ヶ月間は、相続人が相続方法を検討するための熟慮期間と呼ばれています。ではこの『3ヶ月』、いつからスタートするのでしょうか?
相続放棄に関する3ヶ月とは、自己(各相続人自身)のために相続が開始したことを「知った」ときからスタートすることになります。相続人が必ず被相続人の死亡を把握しているとは限りません。相続人の範囲は、身近な方に限定されるわけでは無く、疎遠になっている親族など広範囲になることもあるからです。そのため、相続人によって3ヶ月の期限日は違っていることもあります。
期限が迫っているからと、焦って手続をすると後悔する場合も…
この3ヶ月。時間があるように思われるかもしれませんが、相続人としては、被相続人の財産をすべて把握した上で決断したいところでしょう。被相続人の財産が生前にきちんと整理され遺言書や遺言執行者がいればよいのですが、相続の多くは準備の無いまま始まる事がほとんどです。そうなると被相続人の郵便物や、自宅の通帳など資料のある物から一つずつ調べていく必要があり、3ヶ月はあっという間に経ってしまいます。
しかし、焦って相続放棄を選択するのは危険です。なぜなら、放棄した後にプラス財産が多いと分かっても、あとから相続放棄の意思を撤回することはできないからです。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません
相続放棄を決断するのに3ヶ月では熟慮期間が足りない!というケースは多々あります。この場合、3ヶ月以内に裁判所へ「相続放棄の期間伸長の申立て」を行うことで期限を延長することが可能です。
ただし、この申し立てを行えば、すべてのケースで延長が認められるわけではありません。被相続人と疎遠で遠隔地のため書類がなかなか揃わない、他の相続人と連絡がつかない、財産の調査にさらに時間が必要であるなど、裁判所が熟慮期間を延長するべきと認めた場合に限られます。単に仕事が忙しいから、などの個人的な事情では認められません。約3ヶ月程度の延長が一般的ですが、事案によってはそれ以上の延長となることもあります。
相続放棄の期限を延長する方法
期限の延長は各相続人がそれぞれで行うことになっています。仮に、相続人全員が相続放棄をしたいと考えていても、相続人全員を代表して行うことはできませんので、各自で手続きすることが必要です。申し立ては被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所へ申立て書類を持参、もしくは郵送します。申立て費用は相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手のみです。郵便切手については各裁判所で総額と内訳が違うので、管轄の家庭裁判所へ問い合わせをしておきましょう。
申立てには申立書(裁判所のHPにひな形が掲載されています。)、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申し立てを行う相続人自身の戸籍謄本が共通して必要です。その他、申立人と被相続人の関係性によって追加の戸籍謄本等が必要となります。たとえば、被相続人の配偶者が申立人であれば、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。さらに裁判所が審理に必要と判断すれば個別に判断し追加書類の提出を求められることもあります。
3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?
3ヶ月の熟慮期間の間に、相続人は単純承認(すべて相続)、限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続)、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。
もし、いずれも選択せず、期限の延長手続きをしなかった場合は、自動的に単純承認したことになってしまいます。つまり、相続財産が借金ばかりであったとしても、すべて相続することになってしまうので、相続方法の選択は非常に重要なのです。
3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース
熟慮期間は原則として3ヶ月です。期間の延長を申し立てしない限り、単純承認を選択したとみなされます。しかし、特別な事情があった場合には3ヶ月を経過しても相続放棄の申立が認められることがあります。
たとえば、3ヶ月の間には判明しなかったマイナス財産があとから明らかになった場合です。裁判所のHPでは「相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」と記載されています。例外的な対応ですので、3ヶ月が過ぎてしまった後に相続放棄を考えるのであれば、弁護士へ一度相談してから行った方がよいでしょう。
相続放棄が認められないケース
相続放棄という手続き、そしてその手続きに期限があること。これは一般に広く知られている情報では無いかもしれません。しかし、「知らなかった」という理由で3ヶ月の熟慮期間後に相続放棄を認めてもらうことは原則としてできません。
また、相続財産の調査に時間がかかったため3ヶ月を経過してしまった、という場合も基本的に相続放棄は認められません。なぜなら調査に時間がかかるのであれば、途中で期間伸長の手続きを行うべきであると考えられるからです。期限を過ぎてからの相続放棄は簡単では無いことを認識しておきましょう。
3ヶ月経過していたら弁護士にご相談ください
相続の開始を知ってから3ヶ月。この3ヶ月で十分判断できるというケースは少ないでしょう。あっという間に時間が経っていたという方が圧倒的に多いのでは無いでしょうか。
しかし3ヶ月過ぎてしまったとしても、相続放棄を諦めるのは早計です。例外的ですが期限後の相続放棄も認められる可能性はあります。しかしその判断は簡単ではなく、専門的な法的知識が必要となりますので、まずは相続に詳しい弁護士にご相談下さい。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続放棄の期限に関するQ&A
相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?
相続放棄は3ヶ月以内に、という期限は、3ヶ月以内に手続きを審理まですべて終わらせないといけないということではありません。相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、申立書類を管轄の裁判所へ「提出」することが必要とされています。つまり、手続きの完了は期限後であっても問題ありません。
相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?
すでに相続(単純承認もしくは限定承認)を選択している場合には、3ヶ月経過していなかったとしても相続放棄を選択することはできません。
また、相続したつもりはなくても、被相続人の財産を一部でも処分したなどの行為があれば、単純承認したとみなされますので、その場合にも相続放棄が選択できなくなりますので注意が必要です。
亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?
熟慮期間である3ヶ月以内に知り得なかったマイナス財産であれば、期限後であっても相続放棄が認められる可能性はあります。督促状が届くまでその借金の存在が分からなかった旨を申立書に記載しましょう。
ただし、この督促状を確認してからさらに3ヶ月を経過してしまうと相続放棄を認められる可能性が低くなりますので、できるだけ早く相続放棄の申立を進めましょう。
先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。
被相続人の死亡を後から知ったというケースでは、被相続人の死亡を知らせる親族からの手紙やメールなどが、相続開始を知った日の証明の材料となります。
また、生前にほとんど交流が無かった、葬式に出席していないといった事情もあれば、あわせて説明すると良いでしょう。どのような内容が証明の材料になるのかについては事案によりますので、弁護士に相談して申立書を作成することをおすすめします。
相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。
郵送であっても3ヶ月目の期限までに裁判所へ到着することが原則です。消印が3ヶ月以内であっても郵便事故などで到着が遅れる可能性もありますので、期限が近いのであれば直接持参することをおすすめします。
ただし、持参をする場合でも期限日の裁判所の受付時間内であることが必要ですので、持参に切り替える場合には、事前に管轄の家庭裁判所へ受付時間を問い合わせておきましょう。
相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?
厳密には第1順位の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月となります。
第2順位以降の相続人については、相続の権利が発生したと裁判所などから通知が来るわけではないので、自身に相続の権利が発生しているとは気づかないことも多いでしょう。突然債権者から督促状が届いて初めて知るというケースもあります。このような場合でも相続放棄の期限が、相続の開始を「知ってから」3ヶ月と覚えておくと冷静に対処することができるでしょう。
相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください
相続人は3ヶ月以内に被相続人の財産を調査し、相続の方法を決める必要があります。しかし日々の生活の中で慣れない手続きを行うのは簡単ではありません。3ヶ月以内に決められなければ期限の延長手続きという手段はありますが、その申立にも戸籍謄本の取り寄せなど慣れない作業が伴います。そして、3ヶ月経ってから相続放棄をどうしてもしたい事情が発生する可能性もあるでしょう。
相続放棄の期限について分からない、不安だと思われたらまずは弁護士へご相談下さい。相続に詳しい弁護士であれば、適切な相続の方法や必要な手続きについてのアドバイスができますので、相続放棄に対する不安を解消できるでしょう。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)