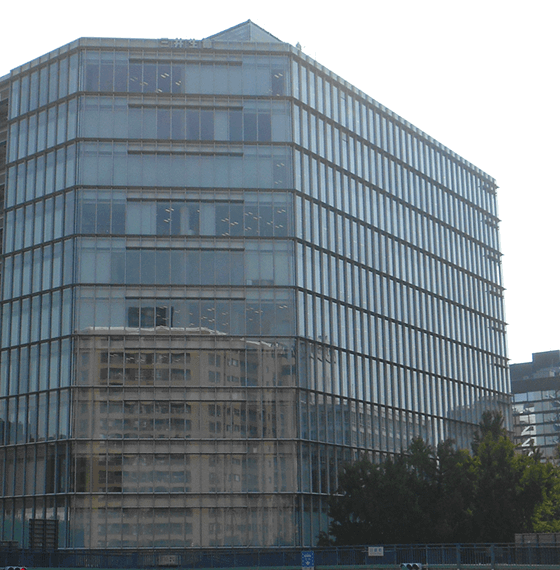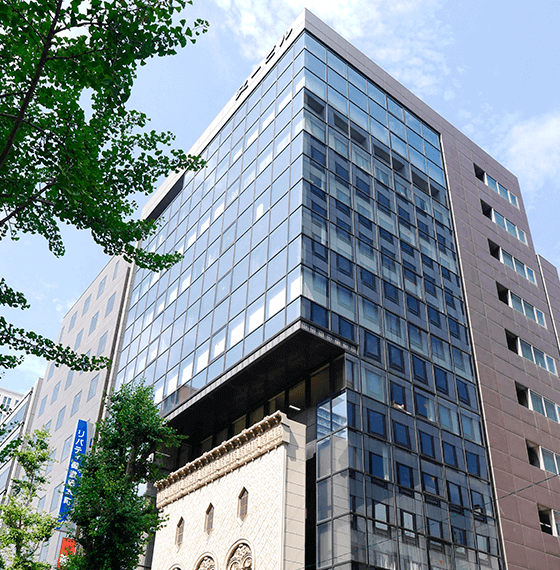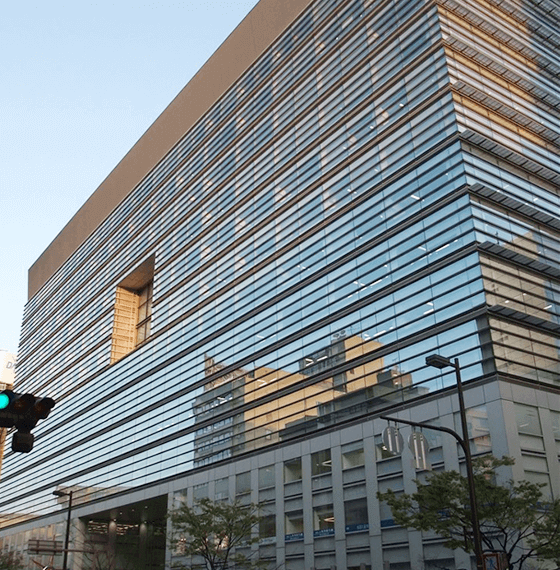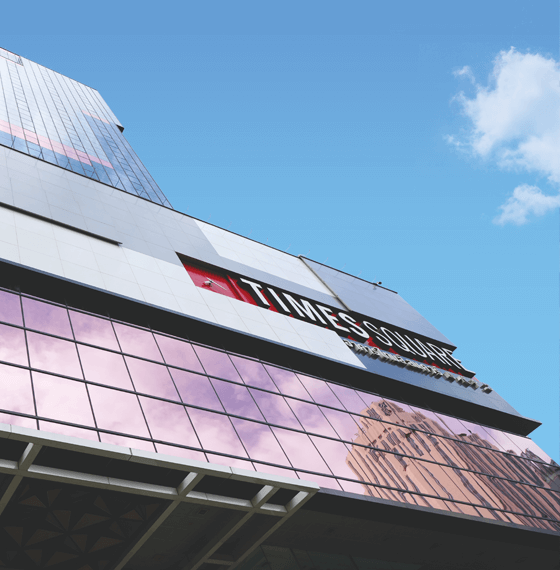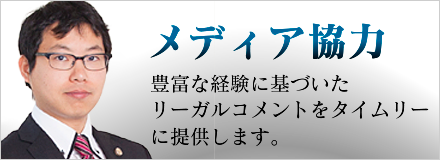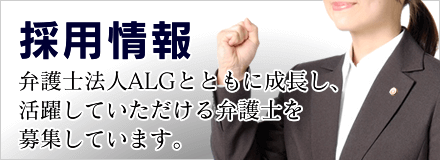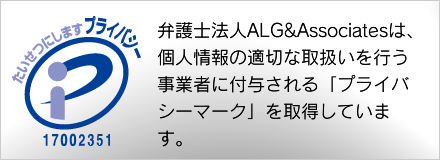遺言執行者とは何をやる?権限や選任すべきケースなどわかりやすく解説
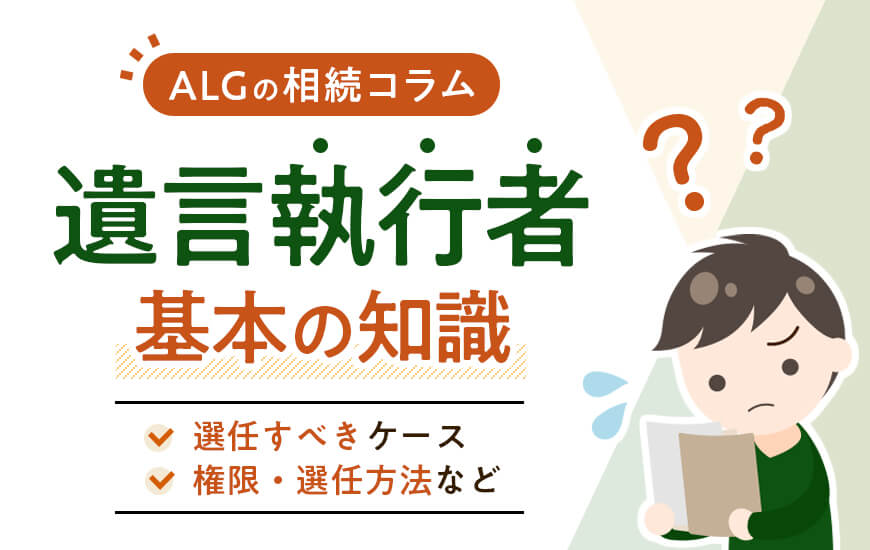
遺産のことは、すべて遺言書に記載してあるから大丈夫、と思うかもしれません。しかし、遺言書の内容を実現させるには、実は「遺言執行者」が必要なケースがあります。大切な遺言内容を実行するための遺言執行者の指名は、やはり信頼のおける人物にしたいところです。
では、聞きなれない遺言執行者とはどういった役割を持つのか、その職務について確認しておきましょう。
目次
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言内容の実現に向けて必要な一切の事務を遂行する者を指します。遺言が効力をもつのは、当然ながら、遺言者が亡くなった後であるため、遺言の内容を実現させるには、その役割を担う者が必要となるケースがあります。
遺言執行者は、遺言書に記載することで指定が可能です。もし、遺言書に指定されていなかった場合には、相続人らが家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることもできます。遺言執行者が行う事務について確認していきましょう。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺言執行者がやるべきこと
遺言執行者に選任された者が行う職務は、その遺言内容によって異なりますが、共通して必要な職務もあります。また、遺言執行者がもつ権利義務についても知っておきましょう。
相続人の確定
遺言執行者は、相続開始後、戸籍謄本等を請求して調査を行い、相続人を速やかに確定させる必要があります。これは、遺言内容を実現させるために対象となる相続人の範囲を把握するためです。
そして遺言執行者には遺言執行者に就任したことの通知や、財産目録など相続人に対して交付する必要があります。これらの書面は相続人を確定させたら、相続人全員へ送付しなければいけません。
相続財産の調査
遺言執行者には、財産目録の作成が義務付けられています。財産目録を作成する為には相続財産の調査が必須です。
財産とは遺言書に記載されているものだけではなく、遺言書作成後に発生した財産についても調査する必要があります。財産目録には具体的な財産内容を記載する必要があるので、金融機関から残高証明を取り寄せたり、不動産の関連書類を取り付けるほか、相続人らのヒアリングも行うなど、事案に応じて対応しなければなりません。
財産目録の作成
遺言執行者が行う事務の一つとして、相続財産の目録を作成し、相続人らに交付することが義務付けられています。民法上、遅滞なく作成して交付すると明文化されているので、遺言執行者に就任したら、ただちに着手する必要があります。
また、財産目録は相続人らにとって相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を検討する上でも重要な情報になりますので、相続人らは財産目録作成に立ち会うことを要求することもできます。財産目録作成の遅滞に重大な過失などがあれば損害賠償請求にも発展する可能性があるので速やかに着手しましょう。
その他
遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるため就任後は直ちにその職務を行う義務があります。また、相続人に対し、その手続きの進捗状況を報告する義務を負い、相続人からの問い合わせにも対応しなければなりません。相続財産を管理するにあたっては、善管注意義務、つまり、通常その遺言執行者に期待される範囲での注意義務を負うことになりますので、不当な管理によって財産に損害があれば、相続人らから損害賠償を請求される可能性があります。
そして、相続財産に関連した受取物があれば、相続人へ引き渡す義務があります。なお、遺言執行にかかった費用については原則として相続人へ費用を請求することができ、遺言執行に関する報酬も請求できます。
遺言執行者の権限でできること
2019年の民法改正によって、遺言執行者の権限がより明確となり、強化されました。遺言内容を実現させるため、遺言執行者は単独で預貯金の解約・払い戻しをすることができます(通常は、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書等が必要)。
さらに、口座の名義を遺言内容に沿って特定の相続人の名義へ変更することもできます。株式や不動産の名義についても同様に遺言執行者に変更の権限があります。不動産の処分についても遺言書に権限の記載があれば、売却してその売買代金を相続人へ分配することもできます。遺言執行者が選任されている場合、相続人が勝手に行った相続財産の処分は、遺言執行の妨害行為として無効になります。
遺言執行者が必要になるケース
遺言執行者はすべての相続に必要というわけではありません。
相続人のすべてが、遺言書内容に納得がいき、相続手続きに協力してくれるのであれば、遺言執行者を選任しなくても遺言書通りの分割が可能です。逆に言うと、遺言書の内容に納得がいっていない相続人がいて、手続きに協力してくれない場合には、遺言執行者を選任し、遺言執行者の権限をもって、遺言書の内容を実現する必要があります。
一方、「相続人廃除」または「認知」について遺言書に記載がある場合は、遺言執行者が必要になります。相続人廃除とは、遺言者がその相続人から生前に虐待や侮辱を受けた、もしくは著しい非行があるといった場合に、遺言者がその推定相続人から相続人としての権利を奪うことを指します。また、認知は婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)を自分の子供であると認める行為です。認知によってこの非嫡出子が相続人となり遺産を受け取ることが可能になります。少数ではありますが、遺言によって一般財団法人設立の意思表示、定款に記載すべき内容を定めている場合にも遺言執行者の選任が必要になります。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺言執行者になれるのは誰?
遺言執行者は個人でも法人でもなることができます。さらに相続人であっても遺言執行者になることができます。
しかし、遺言内容が遺言執行者となった相続人の希望と異なる場合には、執行に精神的負担も伴うので遺言執行者は遺言内容に利益関係のない第三者を選任するほうがよいでしょう。
また、遺言の執行にあたっては様々な法的手続きも多いので、弁護士や司法書士といった専門家の選任も検討しましょう。
遺言執行者になれない人
相続開始時点での未成年者と破産者は遺言執行者になれません。ただし、未成年者であっても既婚者は成人とみなされるので就任可能です。同様に、破産者であっても裁判所から免責許可の決定があれば就任できます。
遺言執行者の選任について
遺言者が遺言執行者を選任する場合、遺言によって指定する必要があります。
そして、遺言で遺言執行者が指定されてない等の事情があれば、相続人らが家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
遺言書に複数の遺言執行者が指名されていた場合
遺言執行者の指定に人数制限はありません。そのため、遺言書で複数の執行者を指定することも可能です。複数の遺言執行者がいる場合、遺言によって各執行者の職務が指定されていれば、その定めに従い各執行者は遺言内容を実行します。
しかし、各執行者の役割分担が指定されていなければ、その職務の執行にあたっては遺言執行者の多数決によって職務の分担を決定することになります。ただし、家屋の修繕を行うなどの相続財産に対する保存行為については、遺言執行者が単独で行うことができます。
家庭裁判所で遺言執行者を選任する方法
家庭裁判所で遺言執行者を選任するには、遺言者の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所への申立てが必要です。必要書類としては、遺言執行者選任の家事審判申立書(裁判所ホームページで申立書の雛形を取得することができます)、遺言者の死亡が記載された戸籍謄本、遺言執行者候補の住民票、遺言書の写し、利害関係を証明する資料(親族であれば戸籍謄本などになります)などが一般的です。その他、収入印紙や連絡用郵便切手、さらに事案によって裁判所から追加書類の提出が求められることもあります。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
遺言執行者の仕事の流れ
遺言執行者の業務の一般的な時系列は以下の通りです。
- ①相続開始
- ②遺言執行者に就任した旨の通知書を作成し、相続人へ送付
- ③相続財産調査・相続人調査
- ④財産目録の作成と相続人への送付
- ⑤遺言内容の実行(預貯金の解約、相続財産の名義変更、売却、分配等財産の引き渡し)
- ⑥任務完了についての通知書を作成し送付
以上はおおまかな流れになりますので、遺言書の内容によってその業務は多岐に渡ります。たとえば遺言に子供の認知や相続人廃除があれば速やかな手続きが必要になります。遺言執行者の職務は難解なものも多く、時間の制約もあるのでスムーズに行うには専門家を選任した方が良いでしょう。
遺言執行者の辞任
遺言執行者に選任されても、就任「前」であれば拒絶が可能です。この場合の拒絶理由は限定されていません。
しかし、遺言執行者に就任した「後」に辞任するには正当な事由が必要です。つまり、遺言執行者が引っ越しや病気などで、客観的に職務の継続が困難であると認められるような場合に限定されます。単に職務内容が難しいといった理由では認められないでしょう。
就任後の辞任については家庭裁判所へ辞任の申立てをし、家庭裁判所はその申立てに正当事由があるか調査し判断します。就任後の辞任はハードルが高いので、就任前に職務を完遂が可能かしっかりと検討することが必要です。
任務を怠る遺言執行者を解任できる?
遺言執行者が職務を怠ったり、義務を果たさないなど正当な理由があれば、家庭裁判所へ申立てをしてその遺言執行者を解任することができます。この申立ては相続人単独で行うことはできず、相続人や受遺者など相続の利害関係者全員の同意が必要とされています。
また、家庭裁判所は遺言執行者からの聞き取りなどの調査を行う為、解任が正式に決定されるまでには一定の時間が必要となります。その期間の執行についても検討が必要になりますので、遺言執行者の解任を考える場合には専門家に相談しながら進めた方が良いでしょう。
遺言執行者が亡くなってしまった場合、どうしたらいい?
遺言執行者の死亡が相続開始「前」であれば、遺言者が遺言書を書き換えることによって新たな遺言執行者を選任することができます。
しかし、遺言者が書き換えを行わないまま相続開始になると、遺言執行者が不在になってしまいます。この場合には、相続人らが家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申立てすることが必要になります。
また、遺言執行者の死亡が相続開始「後」であった場合、遺言執行者の地位は、遺言執行者の相続人へ承継されませんので、前述と同じく相続人らが選任の申立てを行うことになります。
遺言執行者についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください
遺言執行者は遺言内容をスムーズに実現させるための存在です。しかし、相続に関する手続きは非常に煩雑で難解なものも多数あります。法律上は未成年者と破産者以外なら誰でも遺言執行者になれる、とされていますが、その職務内容が誰でもできるということではありません。
相続の専門家である弁護士であれば、相続に関する手続きを熟知しているので遺言の執行を速やかに行うことが可能です。また、中立な立場の専門家が遺言執行者になれば、その執行に対しての不安や不満を解消することができるでしょう。遺言執行者について少しでも疑問があればまずは弁護士へご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)