弁護士依頼前
日額5700円
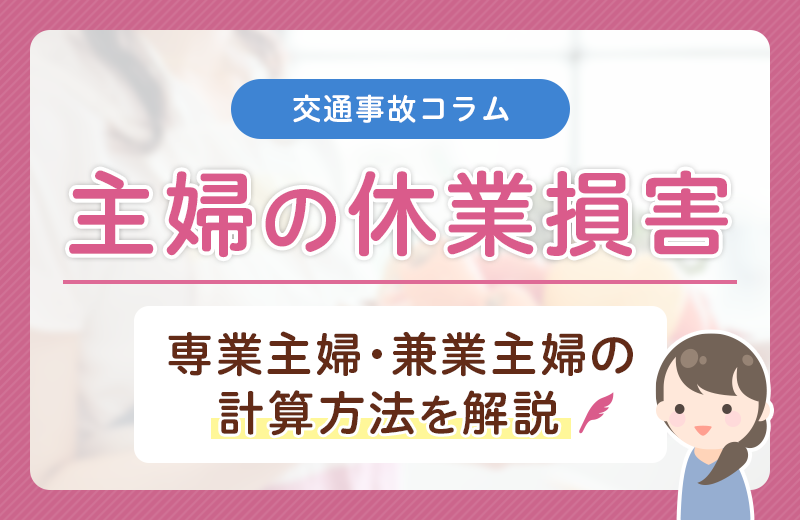
交通事故に遭った際に請求できる損害賠償金の費目の一つに休業損害があります。休業損害とは、事故の怪我によって仕事を休んだことに対する補償です。
「休業」と聞くと会社員など給与の出る職業を思い浮かべるかもしれませんが、休業損害は主婦でも請求することができます。
例えば、むちうちになってしまった場合、主婦でも家事・育児に支障が出ているのであれば休業損害を請求することができます。
主婦の場合、休業損害の計算が少し複雑で、弁護士基準で算定した賃金を用いる方法や自賠責基準で算定した賃金を用いる方法など複数あります。
この記事では、「主婦の休業損害」に着目し、複数の計算方法の違いやケース別の注意点について解説していきます。
弁護士依頼前
日額5700円

弁護士依頼後
日額9718円
約4000円の増額
目次 [表示]
休業損害は、主婦(主夫)などの家事従事者にも認められます。
主婦(主夫)の家事労働は家族のために無償で行われますが、料理・洗濯・掃除などを外注すれば対価が発生します。
したがって、自分以外の家族のための家事労働には経済的な価値があるとして、交通事故が原因で家事ができなかった場合には「減収があった」と考えて、年齢や性別、専業・兼業を問わず、主婦(主夫)の休業損害が認められます。
この考え方からすると、一人暮らしで家事をしている場合は、「自分以外の家族のために家事を行っている」とはいえないため、休業損害は認められないことになります。
専業主婦の休業損害は、次の式に当てはめて計算します。
休業損害 = 1日当たりの基礎収入額 × 休業日数
比較的わかりやすい式ですが、専業主婦の場合は実際に給与を受け取っているわけではないので
というように、基礎収入や休業日数の判断基準がポイントになります。
次項でひとつずつみていきましょう。
交通事故の損害賠償額の算定基準には、以下の3つの基準があります。
休業損害では、3つの基準ごとに「基礎収入」の考え方が変わります。基準ごとの違いについては以下の表にまとめています。
この基準の中で、弁護士基準では「賃金センサス」の女性の全年齢平均賃金を使用して計算します。主夫であっても、性別で家事労働の評価に差を発生させないため、同じく女子の全年齢平均賃金を使います。
次項からは基準ごとの基礎収入の考え方について解説していきます。
| 基礎収入 | |
|---|---|
| 自賠責基準 | 休業一日当たり6100円 |
| 任意保険基準 | 自賠責基準と同等か少し高額になる程度 |
| 弁護士基準 | 令和5年 1万949円 |
自賠責基準では、基礎収入は1日当たり6100円と定められており、会社員であっても主婦であっても、職業によって金額に違いはありません。
なお、2020年3月31日以前の事故については基礎収入1日当たり5700円と考えられていました。
任意保険会社の基礎収入の考え方は、任意保険会社ごとに異なります。そのため明確な基準はありませんが、多くの任意保険会社では以下のような基礎収入の計算方法を取っています。
多くの場合、現実の収入をもとに基礎収入を算定した方が休業損害の金額が大きくなるので、任意保険会社が基礎収入を日額6100円で提案してきても安易に受け入れないようにしましょう。
弁護士基準の主婦の基礎収入は賃金センサスを用いて求めます。 賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発表している労働者賃金に関する統計データです。
| 年齢 | 令和5年 |
|---|---|
| 全年齢平均 | 399万6500円 |
| ~19歳 | 254万9600円 |
| 20~24歳 | 318万300円 |
| 25~29歳 | 381万1600円 |
| 30~34歳 | 397万8200円 |
| 35~39歳 | 413万4600円 |
| 40~44歳 | 424万1600円 |
| 45~49歳 | 437万2900円 |
| 50~54歳 | 441万1000円 |
| 55~59歳 | 432万6300円 |
| 60~64歳 | 357万2800円 |
| 65~69歳 | 301万2300円 |
| 70歳~ | 295万6900円 |
主婦は、事故前年の女性の全年齢平均賃金を365日で割った金額を1日当たりの基礎収入額とするのが一般的です。
【令和5年の専業主婦の1日当たりの基礎収入額】
令和5年(2023年)の女性の全年齢平均賃金は399万6500円でした。
この金額を365日で割ると、主婦の1日当たりの基礎収入額は1万949円となります。
自賠責基準の基礎収入よりも、弁護士基準の方が高額であることがわかります。
| 年度 | 賃金センサス |
|---|---|
| 令和5年(2023年) | 399万6500円(日額1万949円) |
| 令和4年(2022年) | 394万3500円(日額1万804円) |
| 令和3年(2021年) | 385万9400円(日額1万573円) |
| 令和2年(2020年) | 381万9200円(日額1万463円) |
主婦の場合の休業日数は、「家事労働に従事できなかった日数」をカウントします。
入院している間は家事労働できないことが明らかなので、入院期間=休業日数となります。
一方で通院に関しては、主に2通りの考え方があります。
通院期間のうち、実際に通院した日数を休業日数として扱う方法です。
自賠責基準では、自宅で安静にしている期間は休業日数に含まれないことが多いので注意しましょう。
通院期間のうち、全く家事労働できない状態の休業割合を100%として、症状の回復状況に応じてだんだんと家事労働できるようになったものと考えて、段階的に休業割合を減らして計算する方法です。
(例)
通院期間3ヶ月の休業割合を、「最初の30日は100%」、「次の30日は50%」、「最後の30日を30%」というように計算します。
兼業主婦の場合の計算式も、基本的には専業主婦と同じく
「1日あたりの基礎収入×休業日数」
になります。ただし、弁護士基準での基礎収入の考え方は専業主婦と少し違います。
兼業主婦の場合、基礎収入に当たるものとして、「家事労働としての評価収入」と、「仕事での現実の収入」の2種類があります。
以下、算定基準ごとの兼業主婦の基礎収入について、次項で詳しくみていきましょう。
兼業主婦の場合、基礎収入に当たるものとして、「家事労働としての評価収入」と、「仕事での現実の収入」の2種類があります。
以下、算定基準ごとの兼業主婦の基礎収入について、次項で詳しくみていきましょう。
兼業主婦の基礎収入は、自賠責基準では1日当たり6100円※です。この額は、専業主婦の場合と同じです。
しかし兼業主婦の場合は、実際の収入の方が日額6100円を上回っているケースもあるでしょう。そのことを給与明細などで証明することができれば、実際の収入額で計算することが可能です。ただし、上限は1日当たり1万9000円と定められています。
※2020年3月31日以前に発生した事故については、1日5700円で計算されます
弁護士基準では、「家事従事者としての休業損害」と、「給与所得者としての休業損害」のうち、いずれか高額の方を基礎収入として採用します。
例えば、令和6年に交通事故の被害に遭われた場合、令和5年の女性の全年齢平均賃金(399万6500円)と令和5年の実収入を比較して、どちらを基礎収入とするかを判断します。
このケースにおいて、実収入が平均賃金を下回っていた場合は、家事労働者としての1日当たり1万949円が基礎収入額となります。
兼業主婦の休業日数は、「実際に仕事を休んだ日数」と「家事労働ができなかった日数」をカウントします。
①実際に仕事を休んだ日数
勤務先に協力してもらい、勤務表などから仕事を休んだ日数を証明していきます。
②家事労働ができなかった日数
客観的な証明は難しいため、専業主婦の場合と同様に実通院日数を基準としたり、通院期間の中で段階的に休業割合を減らす方法で計算したりします。
【仕事を休んでいない兼業主婦の場合の休業日数】
兼業主婦の場合、「仕事を休んでいないと休業損害は認めない」と相手方保険会社から言われることがあります。
ですが、仕事は無理をして行っていても家事に支障が出ている場合には、怪我の内容・程度や、家事労働に支障をきたした内容・程度などを具体的に証明することで、主婦としての休業損害が一定程度認められる可能性がありますので、弁護士に相談してみましょう。
主婦の休業損害は、相手方の任意保険会社または自賠責保険会社に請求するのが一般的です。
このとき、専業主婦として請求する場合と、パート・兼業主婦など給与所得者として休業損害を請求する場合とで必要書類が異なるため、次項で詳しく解説していきます。
専業主婦が休業損害を請求する際に必要な書類は以下の通りです。
兼業主婦の方で、給与取得者として休業損害を請求する場合は、専業主婦の場合と請求方法が異なります。
実際の給与所得に基づいて休業損害を請求する場合は、休業の事実を証明するために以下の書類が必要です。
休業損害証明書は相手方の任意保険会社または自賠責保険会社に連絡すれば書式をもらうことができます。
増額しなければ成功報酬はいただきません
次項からは、主婦の休業損害の注意点についてケース別に解説していきます。
交通事故の怪我により、家事が行えない場合、家政婦を雇うことも考えられます。家政婦の実費は相手方保険会社に休業損害の代わりとして請求することができます。
もっとも、主婦としての休業損害との二重取りはできません。なぜなら家政婦の費用も主婦としての休業損害も家事労働ができなかったことによって生じた損失に対する補償だからです。
また、友人や家族に家事代行を依頼し、代行業者よりも高い金額を支払った場合には、家政婦を雇う場合にかかる相当な費用の範囲内でのみ請求が認められるでしょう。
複数世帯で暮らしていると、その中に家事従事者が複数いることが考えられます(例えば、嫁と姑など)。
その場合、被害者がその世帯の中で、家事労働を主として行っていたのか、もしくはサブとして家事労働を助けていたのか、家事労働の割合が判断のポイントとなります。
実際の家事の内容や程度から、被害者が家事労働の主担当として認定されれば、通常の主婦としての休業損害を獲得できる可能性は高いと考えられます。
しかし、被害者が主担当でないなら、家事労働の休業損害は通常の主婦よりも小さいと判断され、主婦としての休業損害は減額される可能性があります。
交通事故の怪我で育児に支障をきたす場合に、一時保育やベビーシッターを利用した費用は休業損害の代わりとして相手方に請求できる可能性があります。
一時保育やベビーシッターの必要性・相当性が認められた場合には、利用料の実費を請求できますが、休業損害との二重取りは認められないため注意しましょう。
例えば、休業日数10日のうち一時保育を3日間利用した場合は
これらのうち、どちらで請求するかを決めることになります。
ご高齢の主婦の場合、休業損害の計算方法が少し異なります。
一般的には賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を使用して計算しますが、高齢者の場合は「年齢別の女性の平均賃金」を用いて休業損害を算出します。
これは、一般的な方法で休業損害を算出すると、被害者と同年代の女性の平均賃金より不相応に高額となってしまうためです。
また、高齢であることから、比較的軽い家事を行っていた場合は、事故前の家事の程度によって休業損害が何割か減額されてしまう可能性もあります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
ご依頼者様(専業主婦)の車両が渋滞待ちのため停車していたところ玉突き事故に遭い、ご依頼者様は頸椎捻挫、末梢神経障害等の傷病を負い、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方から賠償案が提示されましたが、賠償案が適切であるか判断がつかなかったため、
ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
当方弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、休業損害の提示額が自賠責基準を使っており、基礎収入額は日額5700円、期間は1ヶ月にとどまっていました。
そこで、担当弁護士は基礎収入額を賃金センサスに基づいて日額9178円で計算するよう交渉しました。
ご依頼者様は通院日数が多く、お子様もいらっしゃる世帯だったため、具体的に支障が生じた家事の内容を説明して見直しを求めたところ、日額を9718円として、80日を超える休業期間が認められ、最終的に相手方の当初の提示額から160万円増額する内容で示談が成立しました。
主婦の休業損害には、客観的な証明資料が少ないので、個別的判断になることが多い事案といえます。
かつては、主婦の休業損害を認めないという考え方もあり、今でも保険会社によっては、主婦の休業損害を正しく提示してこない場合もあるでしょう。
たとえ提示があっても自賠責基準とあまり変わらないような金額であることがほとんどです。しかし、証拠書類に乏しい主婦の休業損害では、その保険会社の提示を覆すのは困難です。
弁護士であれば、弁護士基準を使えるのはもちろん、様々な判例を根拠とした交渉力で、あなたの休業損害を主張する大きな後ろ盾となれます。
現在では、主婦とひとくくりにもできず、専業・兼業・主夫と多様化しています。それぞれの事情に合った交渉が求められ、専門家への相談は必須といえるでしょう。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
