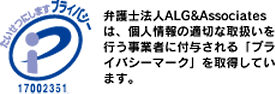前科はデメリットのみ
被疑者・被告人が、刑事事件で有罪判決を受け、刑の執行を終えた場合、その人はもう被疑者・被告人ではありません。
再度何か罪を犯した場合でない限りは、被疑者・被告人として扱われることはありません。
しかしながら、有罪判決を受けると、前科がつきます。
前科がつくと、その旨が前科調書に記載され、検察庁において記録として残り、取り返しはつきません。
また、記録として残るのみならず、次の項目において述べるような、様々なデメリットがあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまった場合には、刑の重い、軽い以前の問題として、前科がつかないようにすることが重要になります。
そのためには、被疑者本人の反省はもちろんのこと、弁護人による適切な弁護活動も重要となります。
前科がつくとは
前科は記録として残ります。
前科がつくと、その旨が前科調書に記載され、どのような被疑事実で、どのような処罰が科されたのかが記録として残ります。
なお、ご質問されることがあるのですが、前科が戸籍や住民票に記録されることはありません。
前科の情報は、みだりに公開されてしまうと、就職その他社会生活を送るにあたって、多大な支障が出てしまう可能性があります。 このことを踏まえて、最高裁昭和56年4月14日第3小法廷判決は、「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」と判断しています。
しかしながら、インターネットが普及している現代社会においては、公的な前科の記録が公開されずとも、場合によってはインターネット上のニュース記事等で前科の情報が残ったままになってしまいます。
現在、「忘れられる権利」というのも議論の対象にはなっていますが、何にせよ、前科がつくことを防ぐに越したことはありません。
将来、別の刑事裁判に巻き込まれた場合
前科の存在は大きく考慮されます。


刑事裁判に巻き込まれた場合、前科があるかないかでは状況が大きく異なってきます。 憲法上の無罪推定の原則から、裁判手続きでは、原則として、前科があったことをもって犯罪事実の認定に用いてはならないとされています。
しかしながら、これはあくまで犯罪事実の認定、つまり「罪となる行為を行ったかどうか」の認定の話であり、「罪を行った人の処罰をどうするか」という量刑の問題とは別です。
検察官や裁判官が処分や刑を決める際には、状況にもよりますが、前科の存在は大きく考慮されます。
前科の数が多ければ、状況にもよりますが、「反省をしていない」という印象を与えかねませんし、同じ犯罪でも、前科がないときは執行猶予がついたのに、前科があるときには執行猶予なしの実刑判決という結論になるようなこともあります。
前科がつくことによる職業の制限
一部の職業においては欠格事由となって、
採用・就職が制限されます。


前科がつくと、一部の職業においては欠格事由となって、採用・就職が制限されたり、資格取得ができなくなったりします。
すでに資格を有している人に前科がつくと、資格が剥奪される可能性もあります。
欠格となる要件や期間は、刑罰の内容や資格にもよりますが、具体的に資格が制限される可能性のある資格としては、国家公務員や地方公務員、自衛隊員、保育士 旅客自動車運送事業者などや、社会福祉士・介護福祉士、公認会計士、行政書士や司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、警備業者・警備員、学校の教員などがあります。
これらの職業については、今後の資格取得が制限されるのみならず、すでに資格を有している人は一定期間資格に基づいて仕事が行えなくなる等のデメリットがあり、前科がつくことによって職を失ってしまう可能性も否定できません。
社会的信用の損失
社会生活上の支障を生じる可能性があります。


前科があると、これが万が一判明した場合、社会的な信頼を失うという事態になりかねません。
勤務先において前科が判明した場合は、トラブルを起こして会社に迷惑をかけかねない人材だと評価される可能性も否定できず、結婚相手や結婚相手の両親からいい顔をされない可能性があります。また、会社を設立したり事業を始めたりする際にも、資金借り入れの際や、取引先との関係に支障をきたす可能性もあります。
前述のように、前科はみだりに公開されるべきものではないということは裁判所でも認められているものの、インターネット上の検索履歴や、興信所等による信用調査の結果、前科が判明してしまう可能性は否定できません。
また、自身のみならず、親族も、親戚に前科者がいるということで、社会生活上の支障を生じる可能性があります。