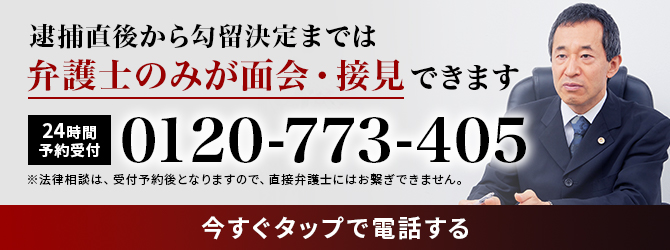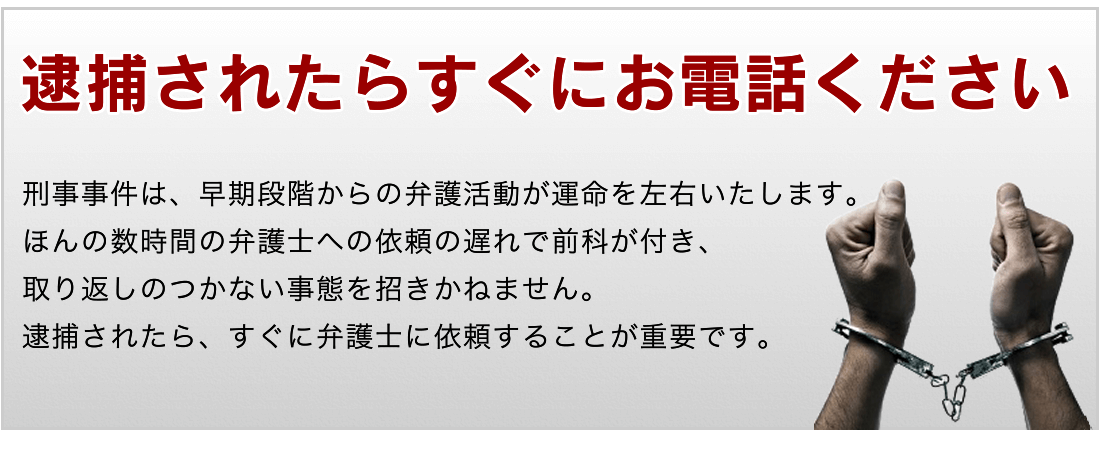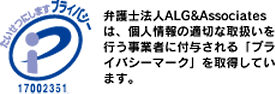家宅捜索の内容
家宅捜索は、犯罪の立証をするために証拠などを警察や検察が抑えることを目的があります。
家宅捜索を行うためには、捜索差押許可状を裁判所から発行しなければなりません。
捜索差押許可状の内容には逮捕者または被告人の名前、罪名、捜索対象場所、物、身体、押収物、有効期限等が記載されています。
捜索差押許可状の内容に基づき警察や検察は家宅捜査を行い、捜索差押許可状にない内容の捜索や差押えはできません。
point
家宅捜索には必ず捜索差押許可状の内容を読み上げてから捜索を開始します。
突然のことでパニックになられてるでしょうが、必ず令状の内容を確認するようにしましょう。
また、警察が令状を提示しない場合は令状の提示を求めましょう。
家宅捜索の条件
例えば、覚醒剤の所持で現行犯逮捕された場合、ほかに覚醒剤を所持していないか否かを家宅捜索し捜査する対象になります。
盗撮などでも自宅のパソコンにほかの画像が保存されていないか、余罪はないかなど家宅捜索をするケースもあります。
家宅捜索はほかに余罪はないか、または逮捕した犯罪を立証するための決め手となる証拠を差し押さえるためにに行われます。
一方、強制捜索は捜査差押許可状を裁判所から発行する前に行うほどの緊急性または必要性が認められてる範囲で行うことを言います。
近年では、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反、盗撮、児童ポルノ所持、商標法違反などで逮捕された場合に家宅捜査が行われることが増加しています。
家宅捜索は拒否することができますか?
家宅捜索は強制処分であり、拒否することはできません。
「捜索差押許可状」は裁判所が発付する以上は強制処分となり拒否することが不可能になります。
適法な家宅捜索に抵抗し、物理的に妨害するようなことをすれば、家宅捜査の対象となっている罪名とは別に、公務執行妨害罪に値する可能性があります。
家宅捜索は弁護士に立ち合いを依頼することは可能ですか?
弁護士は、起訴前段階の捜索差押えについても、住居主から委任を受ければ刑事訴訟法114条2項によって立ち会うことができます。
刑事訴訟法第114条第2項
前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。