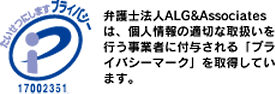領収書を偽造・改ざんして会社の経費を不正受給するのは業務上横領罪?懲戒解雇の可能性も


領収書を偽造、改ざんする不正は、経費に関する不正として珍しくないようです。
ですが、そのような行為は、みなさんが想像されている以上に重い罪に該当するおそれがあります。
ここでは、領収書の不正についてご説明いたします。
目次
領収書を偽造、改ざんして会社の経費を不正受給するのは何罪?
白紙の領収書を入手して金額を書き込んだり、発行された領収書の金額を書き換えたりする不正は、昔から多くの会社で行われてきました。
しかし、このような不正は、会社と社員の問題だけでなく、会社の脱税の問題や、文書の信用性に対する侵害の問題にもつながりかねません。
領収書を偽造、改ざんして会社の経費を不正に計上したり、受給したりすると、何罪が成立するのか等について、以下で解説します。
支給されている経費を私的に使用すると業務上横領罪が成立するおそれ
会社から必要経費として事前に渡されたお金を私的に使用したケースでは、業務上横領罪が成立します。
例えば、出張等の際に旅費が高額になる場合には、会社がお金を仮払いするケースがあります。
会社から受け取った仮払金を出張等で使い切らなかった場合には、余った金額全てを会社に返還しなければなりません。
そうであるにもかかわらず、お金を返すことが惜しいと感じ、余った金額を私的に流用したり、経費とは関係のない領収書を用いて出張費を水増し請求したりした場合には、業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」に成立します。この罪を犯した者は、10年以下の懲役に処されます(刑法253条)。
領収書を書き換える、改ざんする等して経費を不正計上すると詐欺罪が成立するおそれ
白紙の領収書に数字を書き込んだり、受け取った領収書の数字を書き換えたりする方法で、経費として不正にお金を受け取った場合には詐欺罪が成立するおそれがあります。
領収書には手を加えていない場合でも、自分が同僚等と私的に飲食して受け取った領収書を、取引先の接待費の領収書と偽って会社に提出し、経費を請求した場合にも詐欺罪が成立するおそれがあります。
これらの不正は、領収書を発行した会社に確認すれば明らかとなる場合もありますが、悪質なケースでは、領収書を発行した店や取引先と口裏を合わせていることもあります。
詐欺罪とは
詐欺罪は、「人を欺いて」「財物を交付させた者」に成立します。
この罪を犯した者は、10年以下の懲役に処されます(刑法246条)。
人を欺いて財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同様に処罰されます。
領収書の偽造や改ざんは(有印)私文書変造罪が成立するおそれ
受け取った領収書の数字を書き換えた場合には、(有印)私文書変造罪が成立するおそれがあります。
押印が無い領収書で、署名のみがある場合であっても「有印」に該当することに注意が必要です。
(有印)私文書変造罪とは
領収書を書き換えたり、改ざんしたりすると成立する(有印)私文書変造罪は、権利、義務または事実証明に関する文書または図画を変造した者に成立する罪です。
この罪を犯した者は、3月以上5年以下の懲役に処されます(刑法159条2項)。
経費の不正計上のケース
領収書を書き換えたり、改ざんして会社の経費を不正に受給したりする行為は、様々な場面で行われるリスクがあります。
主な場面としては、以下のようなケースがあります。
交通費の不正受給
領収書を用いた交通費の不正受給の手口としては、目的地までの新幹線のチケットを購入して領収書を受け取り、それを払い戻して、より安い高速バス等を利用し、費用を請求する際には新幹線の代金を請求する、というものがあります。
空出張による不正受給
空出張による不正の手口としては、実際には出張がないにもかかわらず、出張先と偽った場所への航空機のチケット等を購入して領収書を受け取った後、払い戻しを受け、出張には行ったかのように費用を請求する、といったものがあります。
接待交際費の不正計上
接待費の不正受給の手口としては、取引先の接待と偽り同僚等と個人的な飲食を行って領収書を受け取り、その領収書を提出し接待費として請求する、といったものがあります。
また、接待は行ったものの、実際に要した接待費よりも増額させて請求する場合もあります。
悪質な場合には、取引先と口裏を合わせることがあります。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
不正を行った社員の責任
たとえ従業員が軽い気持ちで領収書を用いた不正を行ったとしても、その行為には刑事上の責任と民事上の責任が生じており、会社からは懲戒処分を受けるおそれがあります。
また、社内で不正が行われていると、不当な費用を計上しているとして、会社が過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税等の追徴課税を課されることがあります。
そのような事態を避けるため、また、世間からコンプライアンスの遵守を求められていることもあって、特に大企業においては、不正を行った社員に対して厳しい態度で臨む会社が少なくありません。
刑事上の責任
業務上横領罪も詐欺罪も、刑法で定められた刑の上限が懲役10年であり罰金刑の規定がないため、重い罪であることがわかります。
その後の捜査により起訴され、執行猶予が付かない実刑判決を受けてしまった場合、刑務所に収監され、その後の人生に大きな影響を及ぼすことになってしまいます。
仮に執行猶予判決を獲得できたとしても、前科が付いてしまうため、悪影響を及ぼすことに変わりはありません。
会社が受けた被害が少額であったり、示談が成立したりした場合等には、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
しかし、被害が高額であったり、手口が悪質であったりした場合等には、初犯であっても起訴されるリスクは高いといえます。
民事上の責任
領収書を用いて会社の金銭を不正受給した場合、会社から不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を受けるおそれがあります。
不正を行った社員が刑事罰を受けたとしても、金銭の被害が回復されるわけではないため、会社は社員の不正により被った損害を取り戻そうと考えます。
従業員から損害に対する弁償が行われれば、会社は刑事事件化しない可能性もありますが、不正に金銭を得た社員が遊興費等でお金を使い果たし、損害に対する弁償が困難な場合も少なくないため、刑事事件化されるリスクは高いといえます。
領収書の書き換え、改ざんは懲戒解雇になるおそれも
懲戒処分には戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇といった処分が規定されていることが多く、最も重い処分が懲戒解雇です。
お金に関する不正に対しては、比較的重い懲戒処分が行われる傾向があり、領収書の偽造や改ざんを行うと、懲戒解雇となるリスクがあります。
どの懲戒処分を行うかは会社が選択することになりますが、不正を行ったのが経理担当者である場合や、長期間に渡って何度も繰り返されている場合、手口が悪質である場合、金融機関や警備会社といった信用を大切にしている業界の会社である場合等には、懲戒解雇となるケースが多いと思われます。
懲戒解雇を有効とする裁判例(ダイエー事件)
当該事例は、社員が領収書の改ざんによって10万円を着服し、会社から懲戒解雇処分を受けた事例です。
懲戒解雇された原告は、着服したのがこの1回だけであることや、着服した10万円をすぐに返金したこと、阪神・淡路大震災後の過酷な労働条件下で身心が疲弊していたこと等を理由に、懲戒解雇は無効であると主張しました。
しかし、被告が大型スーパーマーケットの経営等を目的とする株式会社であること等から、被告が金銭に関する不正に対して厳罰をもって臨むことにはそれなりの合理性があるため、懲戒解雇は有効であると裁判所は認定しました(大阪地方裁判所 平成10年1月28日判決)。
領収書を改ざんし会社の経費を不正受給してしまったら
もしも領収書を書き換え、改ざんして会社の経費を不正受給してしまったら、なるべく早く弁護士に相談してください。
お金に関する不正に対しては、会社からの懲戒解雇が有効とされるケースが多く、懲戒解雇されてしまうと、今後の再就職が困難になる等、多くの悪い影響が生じてしまうからです。
そして、不正受給した金額等によっては、刑事事件化するリスクもあります。
そのような事態を避けるためには、会社と示談を成立させるべきだと考えられます。
その理由については、以下で解説します。
業務上横領罪は被害者からの被害申告(告訴)で事件化するケースが多い
業務上横領罪は、被害者である会社等から刑事告訴されることにより刑事事件化されるケースが多いのですが、被害者との間で示談が成立していれば、刑事告訴されないケースが多いと言われています。
被害者である会社にとっても、社内で不正が行われたことが世間に知れ渡ると、管理が悪いとみなされて悪評が広がってしまうおそれがあるため、被害弁済さえ受けることができれば刑事事件にはしたくないと考えているケースも多いからです。
会社との示談交渉を弁護士に依頼するメリット
会社との交渉を、横領した本人が行うことはおすすめできません。
被害者である会社側の被害感情が強い場合には、交渉が決裂したり、巨額の迷惑料を請求されたりするおそれがあります。
数多くの示談を成立させている弁護士であれば、法律に基づいた冷静な交渉をして、ご依頼者様にとって有利な条件で示談を成立させることが可能であるため、ぜひ弁護士にご依頼ください。
返済を考えているけど金額が大きく一括で支払うのは困難。分割払いはできる?
不正な請求をしてしまったことを反省し、会社への返金をしたいと思っているものの、不正請求額が大きくなっている場合や、手元にお金が残っていないために一括で支払うのが困難である場合も考えられます。
このような場合は、分割払いによって返済をしたいところですが、分割払いによる返済を認めてくれるかどうかは会社次第です。
被害者である会社からすれば、不正請求を行った従業員の信用は失われている場合も多いと思いますが、会社は被害弁償を受けることを第一に考えているため、交渉次第で認めてもらえる可能性があります。
不正受給に関するお悩みはお早めに弁護士にご相談ください
領収書を偽造、改ざんしてしまい、お悩みの際には弁護士にご相談ください。
何もせずに放っておくと、懲戒解雇等の処分を受け、刑事責任や民事責任を追及される事態に陥りかねません。
社内の不正は、被害者である会社からの刑事告訴により刑事事件化される割合が高いといえます。
そのため、刑事事件化を防ぐためには、会社との示談を成立させることが重要です。
場合によっては、分割払いを認めてもらう等の交渉が必要となります。
数多くの横領事件の刑事弁護を扱った弊所であれば、少しでもご依頼者様のお力になれると思います。
まずはお気軽にご相談ください。