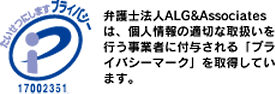起訴されたらどうなる?起訴後の流れや不起訴処分を目指すには


法に反する罪を犯したと判断される場合、刑事裁判において罪の事実確認や刑罰などの審判がなされます。最終的な審判は裁判官によって行いますが、はじめに検察官にて被疑者を刑事裁判にかけるかどうかの判断、つまり、起訴するかどうかの判断がなされます。
そして、日本は非常に高い有罪率を誇っており、起訴された場合には、99.9%の確率で有罪判決が下されるとされています。
そこで本記事では、検察官が行う起訴に着目し、起訴後の流れや不起訴処分を目指すために行うことなどについて、詳しく解説していきます。
目次
起訴とは
起訴とは、刑事事件を起こした被疑者について、検察官が裁判所に対して審判を求める行為のことをいいます。
簡単に言うと、「検察官が裁判所へ被疑者を処罰するように訴えを起こすこと」で、公訴提起を意味しています。
なお、刑事事件の起訴には、いくつか種類があります。
そのなかでも、以下の2種類に大きくわけられており、同じ起訴であってもそれぞれ異なる手続きを踏みます。
- 通常起訴(=正式起訴)
- 略式起訴
では、それぞれにどのような違いがあるのか、次項にて詳しく解説していきます。
通常起訴
通常起訴は正式起訴のことを指し、これらは公判請求とも言われています。
検察官によって通常起訴されると、被疑者は被告人へと呼称が変わり、公開の法廷で刑事裁判が開かれて裁判官から判決の言い渡しを受けることになります。
なお、起訴後は裁判が終わるまで被告人の身柄拘束(=勾留)が継続することが多く、被疑者の段階から勾留されている状態で起訴された場合には、自動的に「起訴後勾留」へと切り替わるようになっています。
被告人を勾留する目的は、「被告人が裁判を欠席しないようにするため」といわれており、これは日本の刑事裁判が被告人不在の裁判を認めていないという背景からきています。
略式起訴
略式起訴とは、正式な裁判ではなく、書面だけの簡略化した裁判で罰金刑もしくは科料のみの刑罰を科すように簡易裁判所に求める手続きのことをいいます。
略式起訴は、検察官が比較的軽微であると判断した事件に限り行われますが、略式起訴を行うための要件もあります。
略式起訴の要件
- 簡易裁判所の管轄する事件であること
- 100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること
- 被疑者から同意を得ていること
これらの要件を欠けることなくすべて満たし、簡易裁判所が略式起訴することが相当だと判断できる事件でなければ、略式起訴を行うことは認められません。
起訴されたらどうなる?どこに行く?
検察官によって起訴された場合、どのように変化するのでしょうか。
大きく変わることには、次の3つが挙げられます。
- 被疑者から被告人へ立場が変わる
- 身柄を拘置所に移送される
- 起訴後も勾留が続く
では、それぞれの変更点について、もう少し深く掘り下げていきましょう。
被疑者から被告人へ立場が変わる
わかりやすく大きく変わることは、被疑者と呼ばれていた名称が被告人となることです。
また、ただ名称が変わるのだけでなく、それと同時に法的な立場も変化します。被疑者は、罪を犯したと疑われる立場にありましたが、被告人は刑事裁判を受ける立場にあります。
つまり、罪を犯した可能性がより高いとされる立場になったことを意味します。
ただし、被告人となれば、一旦身柄の拘束を解くようにと保釈申請(保釈請求)を行うことが可能となります。これは、被告人だけに認められている権利であり、起訴され被告人とならなければ保釈を求めることはできません。
そもそも保釈制度とは?
保釈金を納付することで、被告人の身柄を一時的に解放する制度のことをいいます。
保釈制度は、「被告人が受ける社会復帰困難などの不利益が大きくなりすぎないようにする」ためにあります。
なお、保釈に必要となる保釈金は、保釈を決定した裁判所が決めます。
保釈金の相場は、被告人の資力や犯した罪の内容によって考慮されるため、事件ごとに異なります。しかし、大体150~300万円程度であることが多いといわれています。
保釈について、詳しくは以下のページをご覧ください。
身柄を拘置所に移送される
被疑者の段階で勾留される場合は、身柄を留置場内で収容されるのが一般的ですが、起訴されると留置場から拘置所に移送されることになります。
ただし場合によっては、起訴される前と同様に留置場に留められることもあります。
また、留置場の管轄は警察ですが、拘置所の管轄は法務省となるため、施設内に取り調べを行う警察官はいないなどの特徴があります。
なお、拘置所にいる被告人と面会することは可能ですが、収容されている拘置所によって面会の決まりがあるため注意が必要です。
拘置所の面会について、詳しくは以下のページをご覧ください。
起訴後も勾留が続く
起訴された後も証拠隠滅や逃亡のおそれを防ぐために、勾留が継続されます。
これを、「起訴後勾留(被告人勾留)」といい、基本的には裁判が終わるまで身柄拘束が続きます。
起訴後の勾留期間は、被疑者勾留時とは異なり、期限がありません。
正確には、2ヶ月と法律で定められているものの、勾留が必要と判断される限り1ヶ月ごとに更新されていき、勾留期間の更新に上限もないことから、無限に勾留を継続することができます。
なお、起訴後勾留の請求も起訴前勾留(被疑者勾留)と同様に検察官が裁判所に対して請求の手続きを行います。裁判所が請求を認めた場合、最初に2ヶ月間の勾留が認められ、以降1ヶ月ごとに更新されていく流れになります。
刑事事件では早い段階での弁護士依頼が重要となる理由
日本の刑事事件における有罪率は、99.9%と非常に高い数値を維持し続けているため、どれだけ早い段階から弁護活動を行えるかが被疑者・被告人の命運を分けます。
また、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断するまでに残された時間は少なく、逮捕から最大23日間しかありません。
そのため、この23日の間に被害者との示談交渉を進めることや、有効な証拠の収集などを行い、不起訴処分を目指した弁護活動を行うことが重要です。そのためには、なるべく早い段階で弁護士に相談し、弁護活動に着手する必要があります。
では、弁護士であればどのような弁護活動が行えるのか、もう少し掘り下げて解説していきます。
不起訴処分を目指す弁護活動
被疑者が起訴される前の段階であれば、不起訴処分を目指す弁護活動が主軸となります。
被害者の存在する事件の場合は、被害者との示談成立が不起訴処分を獲得するうえで非常に重要となります。
示談は、事件の当事者である被害者と加害者である被疑者の和解を意味するため、示談が成立すれば不起訴処分となる可能性を大きく高めることが期待できます。
一方で、被害者が存在しない事件の場合は、物理的に示談することができないため、再発防止に向けた取り組みや贖罪寄付を積極的に行い、被疑者が事件に対して深く反省していることを検察官へ主張します。
すでに起訴されたケースにおける弁護活動
被疑者が起訴された後の段階であれば、執行猶予付きの判決獲得を目指す弁護活動が主軸となります。
起訴後であっても、被害者との示談成立は被告人の量刑を判断するうえで非常に有効な情状となります。
そのため、被害者が存在する事件の場合は、起訴後も引き続き弁護士を通じて被害者との示談交渉を継続していきます。
一方で、被害者が存在しない事件の場合は、引き続き被告人の情状をよくしていくことが大切です。
また、犯罪事実が軽微であることを裁判の中で主張し、量刑の軽減を目指します。なお、これらの弁護活動は、被害者が存在する事件の際にも同様に行います。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
起訴されたあとの流れ
通常起訴の流れ
通常起訴は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。なお、ここで被疑者は、「被告人」と呼ばれるようになります。
通常起訴の流れ
- ①起訴状の送達
- ➁第一回公判期日の決定
- ➂裁判
- ④判決
では、それぞれの手続きについて、詳しく解説していきます。
①起訴状の送達
通常起訴の場合、検察官から裁判所へ提出された起訴状が、遅滞なく裁判所から被告人に起訴状が送達されます。
起訴状の送達は、起訴されてから数日以内には被告人の手元に届きます。このとき、被告人が被疑者として勾留されている場合には、起訴状は留置場に送達され、留置場で起訴されたことを知ります。
起訴状に書かれている内容
- 被告人を特定するための事項(氏名、生年月日、職業、住居、本籍等)
- 公訴事実
- 罪名及び罰条
起訴状には、上記①~③の内容が記載されており、間違いがないかの確認を行います。
なお、被告人を特定する事項が不明の場合には、被告人の人相や指紋などを具体的に記載し、被告人をできる限り特定します。
②第一回公判期日の決定
裁判所が第一回公判期日を指定すると、被告人に召喚状が送達されます。
召喚状の送達は、起訴から1~2週間程度で行われます。起訴から1~2ヶ月後の日が第一回公判期日と指定されることが多いです。なお、起訴状の送達と同様に、被告人が留置場にいる場合は、召喚状も留置場に送達されることになります。
また、裁判所が必要と認めたときには、裁判をよりスムーズに進めるために、公判期日の前に公判前整理手続きを行います。
公判前整理手続きとは、第一回公判期日の前に被告人の弁護人と裁判所、そして検察官が争点や証拠を整理して、判決までのスケジュールを立てることをいいます。
なお、裁判員裁判では必ず公判前整理手続きを行わなければならないとされています。裁判員制度で選ばれた裁判員の負担を軽減することが理由の一つとされています。
③裁判
裁判の流れ
- 1.冒頭手続き
人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、意見陳述などが行われます。 - 2.証拠調べ手続き
冒頭陳述、証拠調べが行われます。 - 3.弁論手続き
論告・求刑、弁論が行われ、弁論終結、結審となります。 - 4.判決の宣告
裁判所が被告人に対して、判決を言い渡します。
弁護士は、裁判を行うなかで「被告人が事件当時どのような状態(精神状態など)であったのか」や、「被告人が今後どのように更生していくのか」などについて、具体的に裁判官へ伝えていきます。
裁判における弁護士の主張は、裁判官が被告人の量刑を判断する際に考慮される“情状”に大きく影響するため、非常に重要となります。
なお、犯罪事実などに争いがない事件であれば、裁判は2回ほどで終了することが多いです。事件の争点が多ければ多いほど裁判が長くなる傾向にあります。
④判決
被告人が罪を認めており、犯罪事実に争いがない事件の場合には、2回目の裁判で判決を言い渡されることが多いです。
なお、2回目の裁判は、一般的に1回目の裁判が終わってから2~3週間後に行われます。
裁判官は、被告人が罪を犯したことに確信が持てる場合には有罪判決を、確信が持てない場合には、無罪判決を言い渡します。下された判決が有罪判決であり、執行猶予がつかない場合は、刑務所に入らなくてはなりません。
一方で有罪判決ではあるものの、執行猶予がつく場合には、刑務所に入らずに日常生活を送ることができます。
執行猶予とは、裁判官より言い渡された刑の執行が一定期間猶予される制度であり、認められた執行猶予の期間中に罪を犯さなければ刑が免除されます。
下された判決が無罪判決である場合は、「被告人は罪を犯していない」と認められたことになるため、直ちに身柄拘束が解かれて釈放されます。
また、無罪であるにも関わらず身柄拘束されたことに対して、“刑事補償請求”を行うことができます。なお、刑事補償請求の請求先は国であるため、無罪判決を下した裁判所へ請求書を提出します。
略式起訴の流れ
身柄拘束を受けない在宅事件などで略式起訴された場合は、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。
略式起訴の流れ
- 1.検察官が簡易裁判所に対して略式裁判の請求を行う
- 2.簡易裁判所が略式命令を発布する
- 3.被告人へ略式命令が送達される
- 4.その後検察庁から被告人へ略式命令納付書が送られる
- 5.略式命令納付書で指定された検察庁窓口または金融機関にて罰金・科料を支払う
- 手続き終了
一方で、身柄拘束を受けている身柄事件などで略式起訴された場合は、まず検察官から略式裁判の説明がなされ、略式起訴される当日に警察署から裁判所へ連行されます。
裁判所に到着後は、略式命令を受けるまで裁判所にて待機となり、略式命令を受けた時点で身柄拘束が解かれます。
なお、罰金・科料の支払いがなされない場合には、労役場に留置され労働させられることになります。
労役場とは?
全国の刑務所や拘置所のなかに併設されている「強制的に労働をさせられる場所」のことです。
刑事裁判で確定した罰金や科料を納付できないときに留置されます。
罰金は減額できる?
略式命令の内容に不服がある場合は、略式命令を受けた日から14日以内に正式裁判の申立てを行うことができます。
正式裁判の内容次第では、被告人の情状が考慮されて罰金が減額される可能性はありますが、ほとんど無いに等しいといっても過言ではないでしょう。
むしろ、現状の罰金よりも重い量刑が科せられるリスクや、弁護士に支払う弁護士費用が罰金の金額を上回るおそれがあります。そのため、検察官によって略式起訴の手続きがなされる前に、弁護士に相談することが大切です。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
起訴されたあとでも示談はできる?
被害者との示談は、起訴されたあとでもできます。
確かに、被害者との示談成立は不起訴となる可能性を高めることから、早ければ早いほどよいといえます。しかし、裁判で執行猶予を獲得できる可能性も高めるため、「起訴後だと遅い」ということは決してありません。そのため、起訴後も引き続き被害者との示談交渉を継続することが大切です。
ただし、被害者との示談交渉は容易ではなく、長い時間を要す場合も多いでしょう。しかし、諦めずに裁判が結審するまでは、示談成立を目指した方が望ましいです。
また、起訴後に被害者との示談交渉を開始する場合は、事件から時間が経っていることを理由に、被害者がより加害者側と関わるのを拒む可能性があります。
そのような場合には、示談の話が遅くなってしまったことや、被害者の心情に配慮しつつ、真摯に反省の気持ちを伝えるなど、より丁寧に被害者と接することが大切です。
刑事事件における示談について、詳しくは以下のページをご覧ください。
刑事事件では示談成立を目指すべき!起訴に関するよくある質問
起訴されたあとの身柄はどうなりますか?
起訴されたあとの身柄は、勾留によって拘束されることになります。
また、この時点で被疑者は「被告人」へと呼称が変わり、法的な立場も変化します。
これを“被告人勾留”といい、身柄の拘束先が留置場から法務省が管轄する拘置所に変わることや、保釈請求を行うことが可能となるなどの変化があります。
拘置所に留置された後は、刑事裁判が開かれるのを待ちます。その間は、弁護士と裁判の方針などについて接見にて話し合うことになるのが一般的ですが、決められた保釈保証金の支払いが可能な場合には、その手続きについて弁護士と打ち合わせることになるでしょう。
起訴されたら家族に連絡はきますか?
警察は被告人の家族に連絡する義務はないため、連絡が来るとしたら、それは被告人の弁護士であることがほとんどでしょう。
また、身柄拘束を受けていない在宅事件などで略式起訴がなされた場合には、「起訴状」や「召喚状」が裁判所から被告人の自宅に郵便で送られてきますので、その郵便を家族が見て起訴された事実を知る場合もあります。
なお、刑事事件について家族に知られたくないという場合には、その旨を警察に伝えることで対応してもらえることが多いです。弁護士が介入している場合は、弁護士が被告人に代わって裁判所に家族に知られたくない旨を伝えてくれるため、より円滑に進めてもらえます。
起訴されたら会社や学校にもバレますか?
起訴されても会社や学校などに連絡がいくことはないため、バレることはありません。
重大な事件でない限りは、裁判の情報が報道されるおそれもないため、会社や学校に知られる可能性は低いでしょう。
しかし、事件が会社や学校に関連している場合は、聞き込みなどが行われ、そこからバレる可能性があります。また、勾留されれば身柄拘束が長くなるため、長期間、会社や学校を休まざるをえないことから、バレる可能性もあります。
なお、弁護士が介入している場合には、弁護士から勾留の事実を会社や学校に伝えることが多いです。会社や学校に極力バレたくないということであれば、その旨を弁護士に伝えてできる限りの対応をしてもらうとよいでしょう。
起訴されてしまう前に、あるいは既にご家族が起訴されてしまった方は、出来るだけ早めに弁護士にご相談ください。
起訴され、刑事裁判で有罪判決が下されると前科がついてしまいます。前科による採用・就職制限や解雇・懲戒などのデメリットは決して軽視できるものではなく、今後の人生に大きく影響していきます。
日本の刑事裁判は、起訴されると高確率で有罪判決が下されるという実情がありますが、100%有罪判決が下されるというわけではありません。
そのため、起訴される前の早い段階から裁判を避けるための弁護活動を行い、たとえ起訴されたとしても、その後も継続して量刑の減軽を目指した弁護活動を行うことが大切です。
弁護活動は、早ければ早いほど行動範囲を拡大することができ、充実したものとなり得ます。特に刑事事件に精通した弁護士を選択することで、より円滑に進めることができるでしょう。
起訴されるかもしれない、あるいは既に起訴されてしまいお困りの方は、弁護士法人ALGへご相談ください。