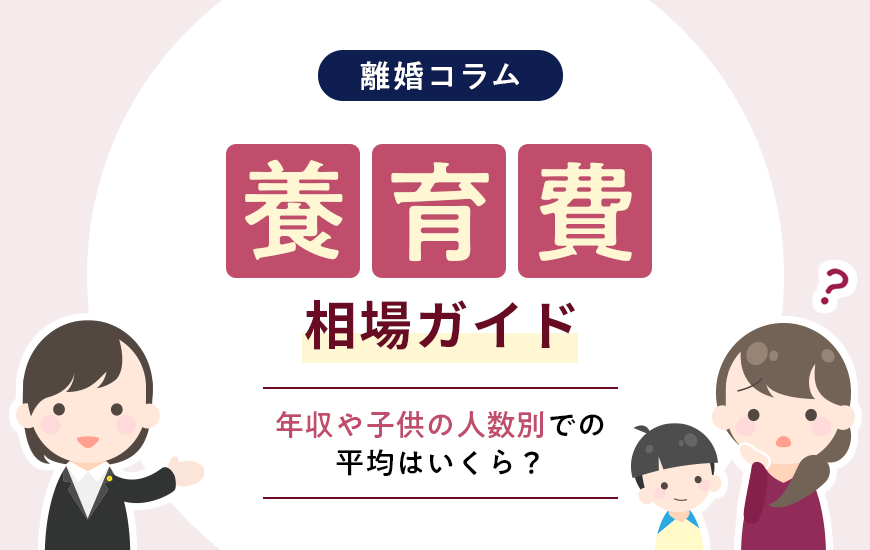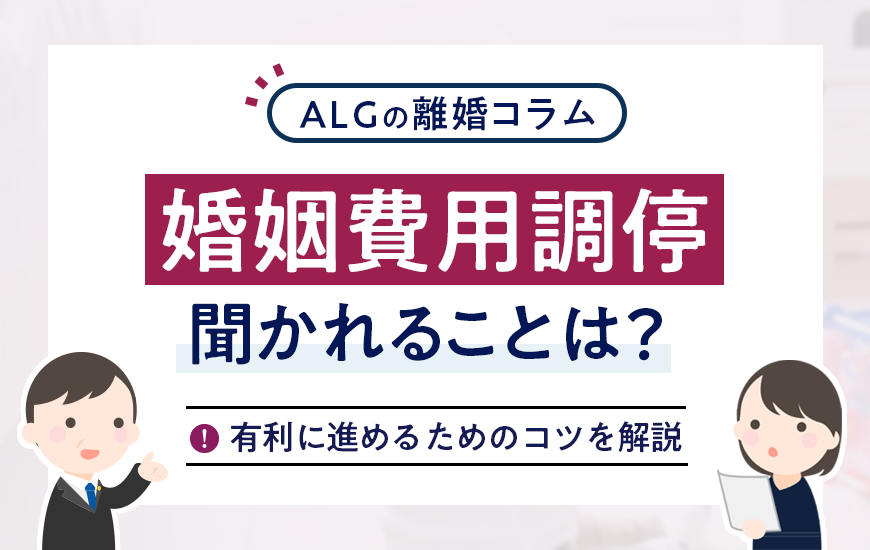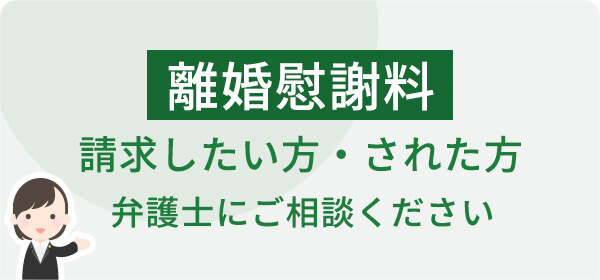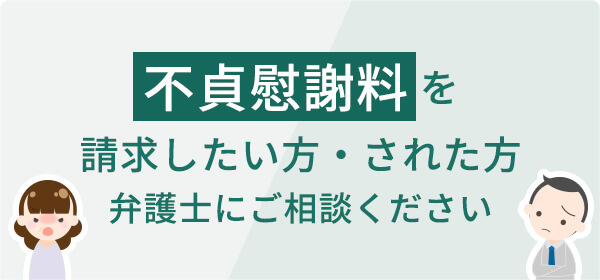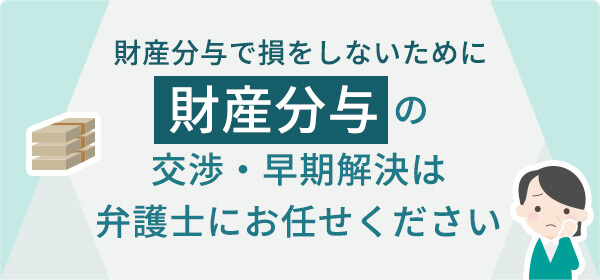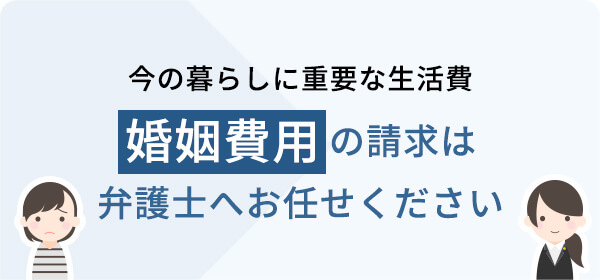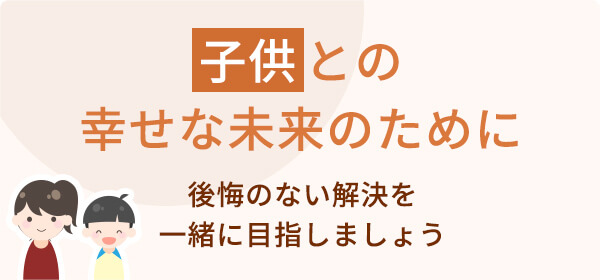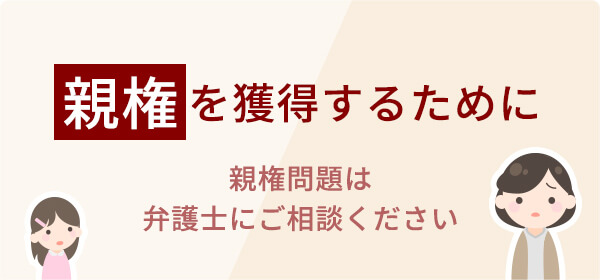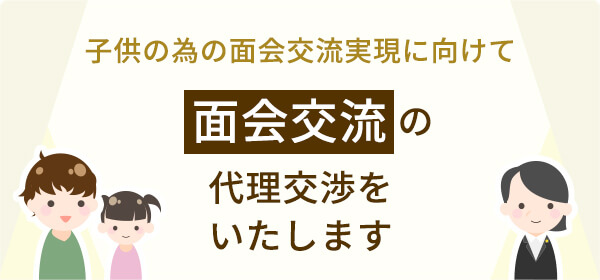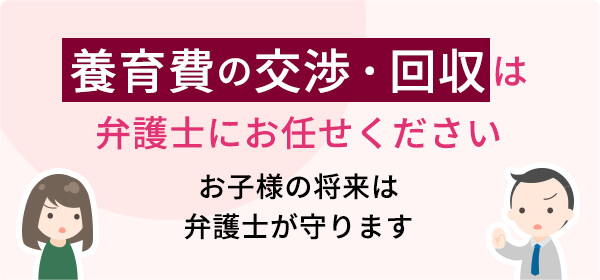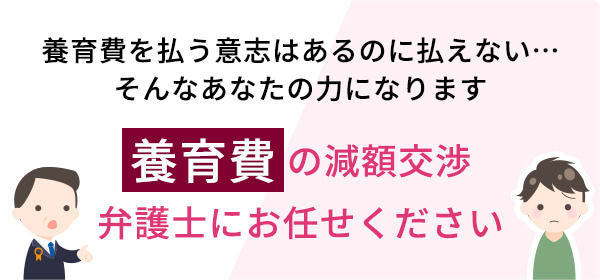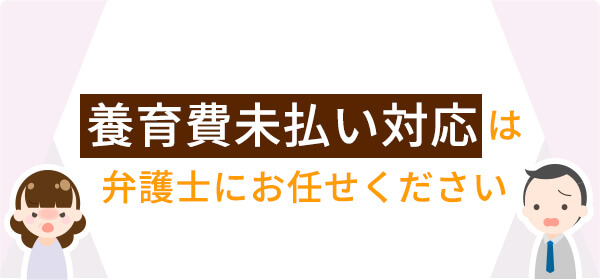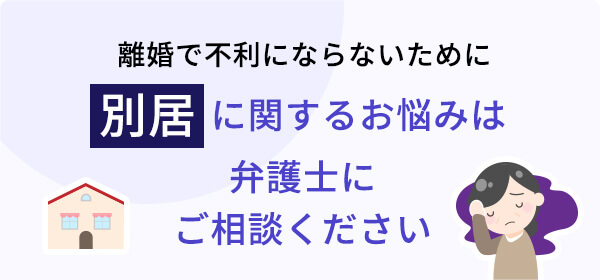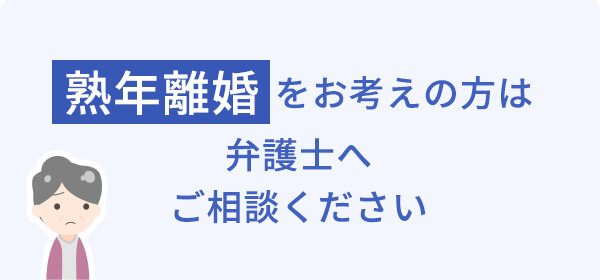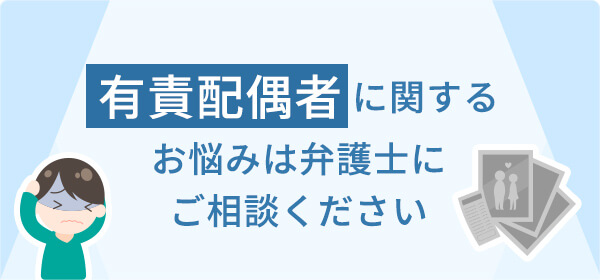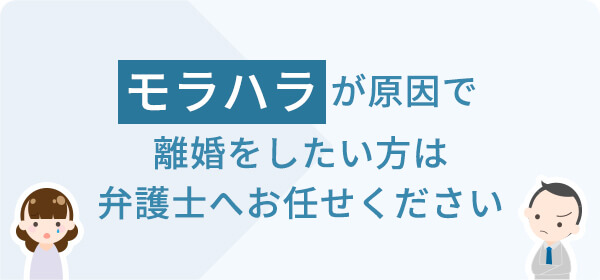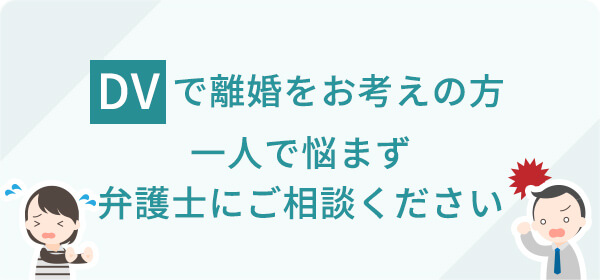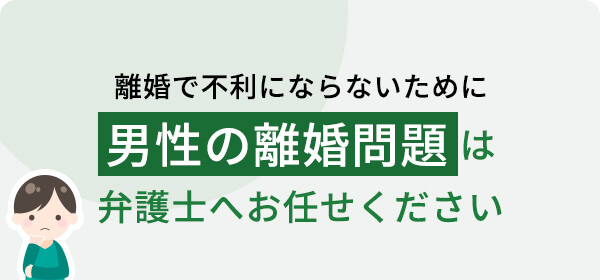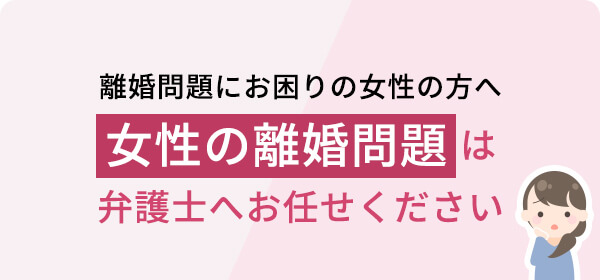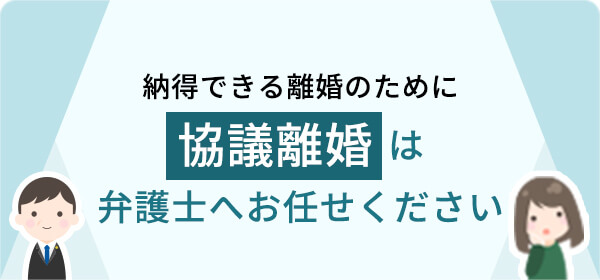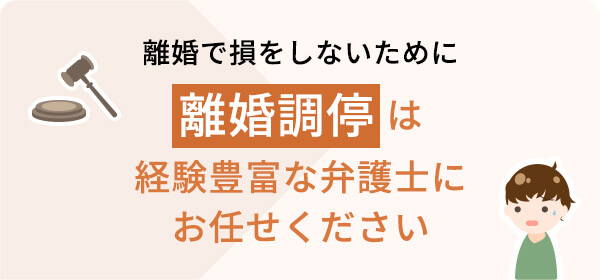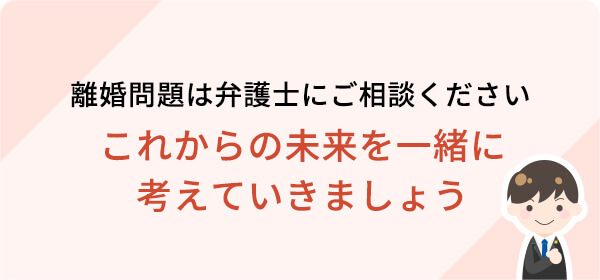婚姻費用とは?認められないケースや請求方法、算定表について
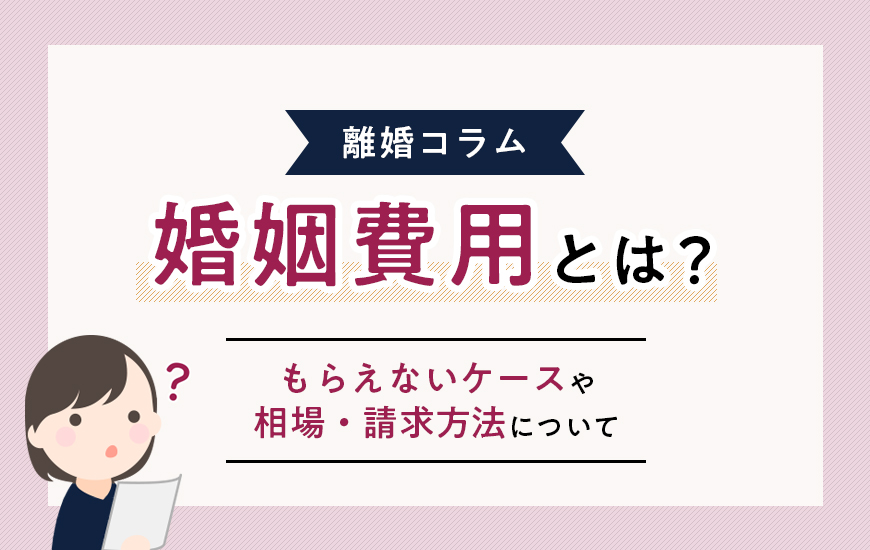
夫婦関係改善のためや、離婚への準備期間として別居を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
別居の際に心配になるのは、当面の生活費かと思いますが、夫婦のなかで収入が少ない側は、収入の多い側に婚姻費用として生活費を請求することができます。
婚姻費用の支払いは基本的に義務であり、受け取れる可能性が高いですが、なかには請求が認められないケースもあるため注意が必要です。
この記事では、婚姻費用の計算方法や算定表の見方、請求方法などについて解説していきます。
目次
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦や未成年の子供が、夫婦の収入・社会的地位に相応な生活をするにあたって必要な生活費のことです。
具体的には、以下のような費用が婚姻費用のなかに含まれます。
- 住居費
- 食費や光熱費などの生活費
- 子供の養育費
- 医療費
- 必要と考えられる範囲の交際費・娯楽費 など
婚姻費用を支払う側は、「別居するのになぜ生活費を負担しないといけないの」と疑問に思うかもしれません。しかし、夫婦には同居・協力・扶助の義務があります(民法第752条)。別居中は同居していないとはいえ、婚姻関係にあることに変わりはありません。そのため、生活費の支払い義務が生じるのです。
別居する際の注意点として、家を出る前に配偶者に別居する旨をきちんと伝えてから別居を開始しましょう。正当な理由なく勝手に家を出てしまえば「悪意の遺棄」となり、あなたが有責配偶者となる可能性もあります。
また、別居はしていないけれど家庭内別居状態であり、生活費をもらっていないという場合にも、婚姻費用は請求できます。
養育費との違いは?
離婚にまつわる婚姻費用と似たものに「養育費」があります。
養育費とは、未成年の子供を育てるにあたって必要となる生活費や教育費のことで、離婚後に子供を監護していない親から監護している親へと支払われます。
婚姻費用が「離婚する前」の配偶者と子供の生活費を指すのに対し、養育費は「離婚した後」の子供の生活費を指します。
養育費には配偶者の分の生活費が含まれないため、婚姻費用の方が高額となるのが通常です。
合わせて読みたい関連記事
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
婚姻費用を払ってもらえないケース
婚姻費用の支払いは基本的に義務ですが、なかには請求しても受け取れないケースがあります。例えば、自分が有責配偶者となった場合です。
有責配偶者とは、夫婦が不仲になる原因(浮気をする、暴力を振るう等)を作った方の配偶者のことをいいます。
自分で夫婦関係を壊しておいて家を出たあげく、婚姻費用まで請求するのは、あまりに都合が良すぎる身勝手な行為と判断されてしまいます。
ただし、有責配偶者が子供を連れて別居をした場合、子供に罪はありませんので、子供の生活費にあたる分の請求は認められるのが一般的です。
婚姻費用はいつからいつまで請求できるか
婚姻費用の支払い期間は、婚姻費用を請求した時から、離婚または別居を解消するときとなります。
離婚が成立するまでは、婚姻関係にあるため、夫婦間には「同居・協力・扶助」義務があり、婚姻費用の支払い義務が継続します。
なお、婚姻費用は別居を開始したら自動的に支払われるものではありません。請求して初めてその義務が発生します。忘れずに請求するようにしましょう。
婚姻費用算定表とは
婚姻費用の金額の決め方については、以下の流れとなります。
- 話し合い
- 調停
- 審判
婚姻費用の金額を決める際には、話しあいで揉めないためにも婚姻費用算定表を用いて相場を算出すると良いでしょう。
婚姻費用算定表とは、家庭裁判所の裁判官らの研究に基づいて作成されたもので、夫婦の年収から簡単に婚姻費用の相場を算出できます。
調停や審判の手続きでも、養育費算定表を参考にしながら話し合いが進められるため、夫婦間の話し合いでも、養育費算定表を参考にすることが一般的でしょう。
婚姻費用算定表の見方
婚姻費用算定表は、子供の有無や人数、年齢に応じていくつか種類があるため、まずは自身の家族構成に一致する表を探します。
表を見つけたら、夫婦それぞれの年収を確認します。給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額を、自営業者の場合は確定申告書の課税される所得金額を確認するようにしましょう。
夫婦のうち年収の多い方が婚姻費用を支払う義務者、年収の少ない方が婚姻費用を受け取る権利者となります。
表の縦軸が義務者の年収を、横軸が権利者の年収を表しているので、双方に該当する年収に最も近い金額に丸をしましょう。
義務者の年収と権利者の年収の行と列が交差する点が、義務者から権利者に支払うべき婚姻費用の月額の相場となります。
相場より多くもらうには
婚姻費用算定表で算出した相場よりも婚姻費用を多くもらうには、相場よりも増額する必要性と相当性があることを、具体的な資料をそろえて相手に論理的に主張しなければなりません。
特に増額が認められやすい医療費と教育費について見ていきましょう。
- 医療費
算定表で算出した婚姻費用の相場には、持病のない人が通常必要な範囲の医療費が含まれています。
そのため、受け取る側や一緒に暮らす子供に持病や障害があり、高額な治療費が必要となるケースでは、増額が認められる可能性もあります。
- 教育費
算定表で算出した婚姻費用の相場には、公立学校の学費を基準とした教育費が含まれています。そのため、子供が私立学校に通っている、通わせる予定があるような場合は私立学校の学費分が上乗せされる可能性もあります。
婚姻費用の請求方法
夫婦での話し合い
この話し合い(協議)は別居する前に行うことが理想的です。
別居後だとなかなか協議の機会を設けるのが難しくなりますし、婚姻費用は“請求する意思を相手に示したとき”からの分しか請求することができないので、早めに話し合った方がよいです。
話し合いがスムーズに進み、月額や支払い方法等の条件が定まれば、その内容を公正証書に残すようにしましょう。
公正証書とは公証役場で作成される文書のことで、公文書として扱われるので、後から揉め事が起こるのを防ぐことができます。
別居後に内容証明郵便で請求する
相手が話し合いに応じない、または応じないと予想されるようであれば、婚姻費用を請求する旨を記載した内容証明郵便を送付しましょう。
内容証明郵便では、以下の情報が記録され、郵便局で保管されます。
- 文書の内容
- 送付日
- 受取日
- 差出人
- 受取人
特別なものと敬遠されるかもしれませんが、郵便局で誰でも利用できる手続きですのでご安心ください。
内容証明郵便それ自体に法的な効力が生じるわけではありませんが、相手に婚姻費用を請求した事実を示す重要な証拠となります。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる
協議をしても結論が出なかったり、内容証明郵便を無視されてしまったりする場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停とは、調停委員を介した話し合いで問題の解決を図る裁判上の手続きです。調停では、夫婦が交互に調停委員に自分の思いを主張していくため、相手方と顔を合わせることはありません。
また、調停委員を間に挟むことによって、これまで相手方に伝えられなかったことを、調停委員を介して伝えてもらうことができ、冷静に話し合いができるでしょう。
調停はご自身でも対応することができますが、初めての手続きでは書類や資料の書き方で負担がかかり、緊張して調停委員に上手く主張できないといったことも考えられます。そのため、調停の手続きは弁護士に依頼することをおすすめしています。
婚姻費用の分担請求を弁護士へ相談するメリット
婚姻費用の分担請求は弁護士への相談をおすすめしています。以下でメリットを確認していきましょう。
- 最適な方法で婚姻費用を請求できる
ご相談者様の今の状況を丁寧にヒアリングし、どの方法によって婚姻費用を請求するか最適な方法を選択し、迅速に対応します。
- 相手方への対応を任せることができる
弁護士に相談することで弁護士はあなたの代理人となり、相手方への連絡や交渉をすべて弁護士に任せることができます。その結果、相手方と顔を合わせることもありませんし、スムーズに話がまとまる可能性が高まります。
- 適切な金額の婚姻費用を請求できる
当事者間では、婚姻費用の相場を知らず相場より低い金額で合意してしまったり、相手方に言いくるめられてしまう可能性があります。弁護士であれば、適切な婚姻費用の金額を熟知しており、交渉のプロでもあるため、適切な婚姻費用を請求できます。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
婚姻費用に関するよくある質問
一度取り決めた婚姻費用を後から変更することはできますか?
婚姻費用を一度取り決めた後でも、当事者間で合意できれば金額を変更することが可能です。しかし、後のトラブルを避けるために、話し合いによって金額を変更した場合は「合意書」や「公正証書」を作成しておくと安心です。
また、話し合いで合意できなくても、取り決めた後に予期しない事情が生じた場合には、婚姻費用の増減が認められる可能性があります。
増額変更が認められやすい例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 支払う側の収入が転職・昇進等により大幅に増加した
- 受け取る側の収入がリストラ等により大幅に減少した
- 受け取る側や一緒に別居している子供が病気になり治療費が必要になった
他方、減額変更が認められやすい例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 支払う側の収入がリストラや病気等により大幅に減少した
- 受け取る側の収入がパートから正職員になる等して大幅に増加した
調停で決めた婚姻費用を相手が払わない場合はどうしたらいいですか?
調停で取り決めた婚姻費用が支払われない場合は、まずは相手方に直接連絡をしてみましょう。
それでも反応がなければ、以下の方法を検討しましょう。また、これらの方法はどちらの方法を選択しても構いません。
- 履行勧告
家庭裁判所が相手方に手紙や電話で支払いを催促する制度です。あくまでも、相手方に支払いを促すものであり、強制力はありません。
- 履行命令
家庭裁判所が相手方に一定の期間内に婚姻費用を支払うよう命令し、相手方が期限を守らなければ10万円以下の過料の支払いを命じる制度です。
また、調停調書に基づき強制執行の申立てをすることで、相手方の預貯金や給与を差し押さえることができます。
婚姻費用分担請求調停ではどんなことを聞かれますか?
婚姻費用の分担請求調停では、現在の収入・支出・資産といった情報の他に、次のようなことを質問される可能性があります。
- 調停を申し立てた理由や経緯
- 現在別居をしているかどうか
- 子供の養育状況
- 婚姻費用としていくら必要か
- 希望する婚姻費用の支払い方法や支払日
- ローンや引き落としの金額・口座
この他にも、特に考慮してほしい事情があるのであれば、自分から主張する必要があります。
婚姻費用の調停で聞かれることについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
婚姻費用分担請求調停が不成立になった場合はどうなりますか?
調停で婚姻費用の条件がまとまらなければ、調停不成立となり、自動的に審判手続きへと移行します。
審判では調停のような話し合いは行わず、家庭裁判所の裁判官が夫婦双方に対して聴き取りを行います。
裁判官は聴取した事情や、調停で提出された資料、必要に応じて提出された追加資料等をもとに、一切の事情を考慮して審判をします。
審判の結果に不服がある場合は、即時抗告を行って高等裁判所に判断してもらいます。
なお、審判は2週間経つと確定して法的拘束力を持つので、即時抗告をするのであれば、審判書を受け取った翌日から2週間以内に申し立てる必要があります。
婚姻費用について算定表の見方などわからないことがあれば弁護士にご相談ください
婚姻費用は算定表により簡単に相場を算出することができますが、各家庭には様々な事情があるので、一概に算定表の金額が適正であるとは言えません。
また、子供が4人以上いるケースや、夫と妻それぞれに一緒に別居している子供がいるケースなどでは、そもそも当てはまる算定表がないので、算定表のもとになる計算式から算出する必要が出てきます。
算定表の見方がわからなかったり、算出した金額に納得がいかなかったりする場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、相談者の事情を反映させた婚姻費用を算出することが可能です。
特に弁護士法人ALGには、離婚の解決実績が豊富な弁護士が多く在籍しており、婚姻費用に関する問題の解決ノウハウも豊富です。
婚姻費用は別居中の大切な生活費ですので、少しでもお困りの場合は、ぜひ早いうちにお問い合わせください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)