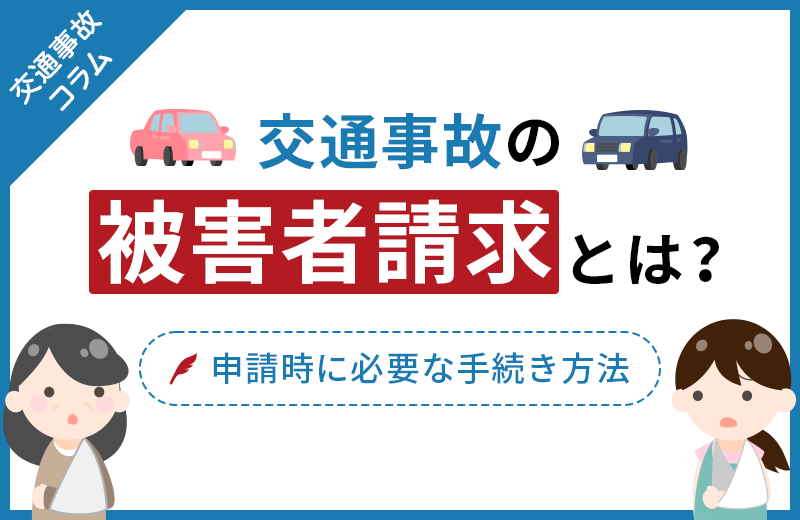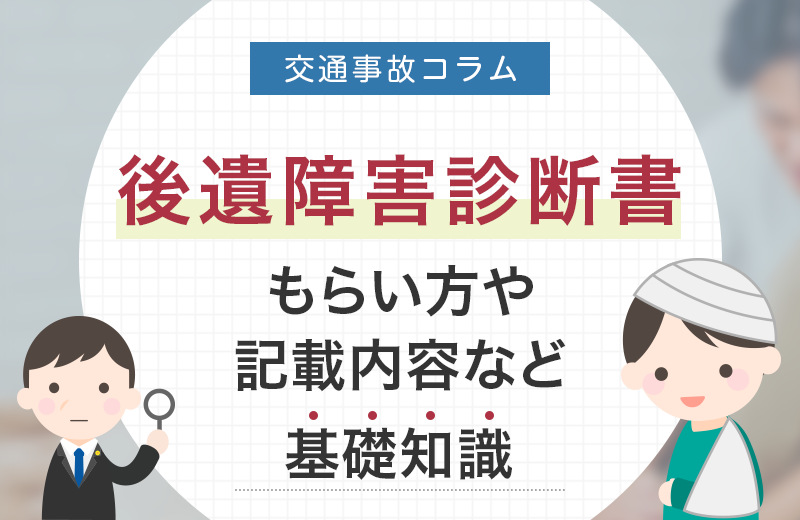交通事故の診断書を提出すべき理由や提出先などの基礎知識
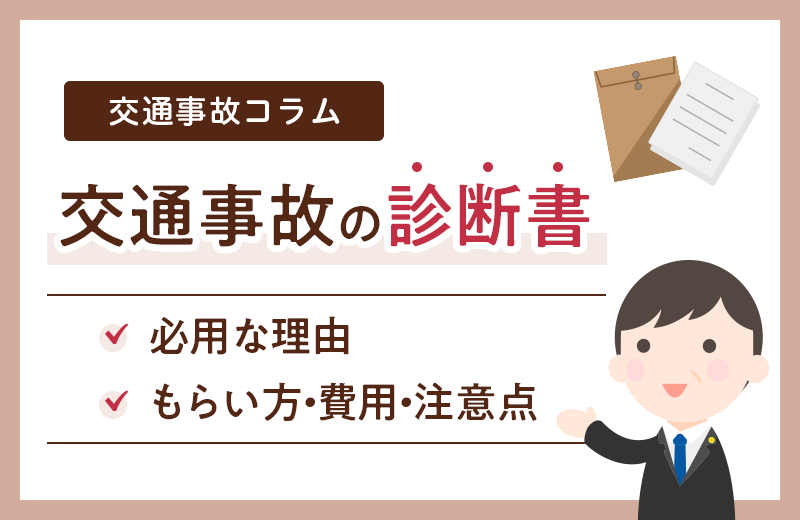
交通事故に遭って怪我を負ったら、病院を受診し診断書をもらうようにしましょう。
診断書は交通事故において重要な役割を担っています。
交通事故の診断書は警察に届け出る際以外に、示談交渉時にも必要になります。
また、慰謝料や損害賠償額を適正に受け取るために必要な書類となります。
なお、提出先によって診断書に関する注意点が違うのも大きなポイントです。
この記事では「交通事故の診断書」に着目して、診断書とは何か、提出先別の注意点などについて解説していきます。
目次
交通事故後に必要になる診断書とは?
交通事故以外でも、診断書の提出を求められることは、社会生活の中であるのではないでしょうか。
診断書とは診察した医師が、病気が怪我の程度、状況について証明するものです。
診断書が必要になる理由
-
警察に提出する診断書
人身事故として処理してもらうために必要
-
相手方の保険会社に提出する診断書
適切な損害賠償を請求するために必要
-
後遺障害等級認定で提出する診断書
後遺障害等級を受け、適切な後遺障害に関する損害賠償を請求するために必要
診断書に書かれる内容
診断書にかかれる内容は以下のとおりです。
- 傷病者
- 傷病名
- 症状の詳細・今後の見通し
- 治療開始日
- 治療期間
- 作成年月日
- 病院名
- 医師名
治療期間には「加療1ヶ月」「全治1ヶ月」など、治療終了日の目安が書かれますが、実際にはそれ以上の期間をかけて治療する場合もあります。
詳しくは次項で解説していきます。
「全治○週間」は過ぎても問題ない?
診断書の治療期間には、「全治3週間」「全治日数3週間」「加療3週間を要する」と書かれることがあります。
これは、医師が大まかな診断結果を証明しているだけのため、記載の日数を超えて治療を受けても問題はありません。
診断書の日数と実際の治療の日数に相違がある場合、損害賠償額は診断書の日数で計算するのではないかと不安に思う方もいらっしゃるかと思いますが、損害賠償の金額は実際の治療期間から算定されることになります。
診断書を作成する際の費用
医師に診断書を作成してもらう際には、無料という訳にはいきません。治療費とは異なり、「文書料」という名目の費用がかかります。
診断書作成にかかる費用は病院によって様々ですが、交通事故の診断書では1通あたり約5000円程度としている病院が多いのではないでしょうか。
交通事故の診断書の費用は加害者の保険会社に請求することが可能です。
相手に請求する場合も一度費用を立て替えることになるので、領収証を保管しておきましょう。
診断書は病院で必ず作成してもらえる
診断書を作成できるのは「医師」だけです。診断書は、病院に通院して、医師に診断書の作成を依頼することで、取得できます。
医師は診断書の作成依頼を断ることはできないため、作成を依頼することで、取得できるでしょう。
また、過去の症状についてもカルテが残っている場合は作成が可能です。
交通事故で負った症状を改善するために整骨院や接骨院に通われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、整骨院・接骨院の施術者は柔道整復師といい、医師ではありません。
そのため、接骨院・整骨院では施術証明書という証明書しか受け取ることはできず、診断書を取得することはできないことに注意しましょう。
診断書はコピーではなく原本を提出する
診断書は基本的に原本を提出します。相手方保険会社に提出する診断書は様式が定められていることもあり、警察に提出する診断書を使い回すことはできません。
勤務先に提出する診断書は、コピーでも認められることがあるため、勤務先へ確認しておきましょう。
【提出先別】交通事故の診断書の注意点
診断書は提出先によって様式が異なります。相手との示談交渉をスムーズに進めるためにも診断書は早めに準備をし、提出しましょう。
提出先別の診断書については以降で詳しく解説していきます。
警察に提出する診断書
まずは警察署へ診断書を届け出ることで、人身事故として扱ってもらう事ができます。
人身事故となるか物損事故となるかで警察の動き方が大きく異なります。違いの一つとして事故の状況を書いた、実況見分調書が作成されるか否かという点があります。
診断書を提出しなければ実況見分調書がなく、相手方から適正な損害賠償を受け取れなくなる可能性もあるため注意をしましょう。
提出期限は定められていませんが、事故と怪我の因果関係を証明するためにも、事故発生からできるだけ早く届け出ましょう。
そのためには事故後少しでも身体に違和感があったら、すぐに病院を受診するようにしましょう。
診断書の記載事項
- 傷病名
- 全治日数の見込み
初診段階では、まだ怪我の詳細が明らかになっていないため、診断書の記載内容も大まかなものとなります。
物損事故として処理した後でも提出可能
事故当時に大きな怪我や痛みがない場合、物損事故として処理されることがあります。
物損事故として処理されてしまった場合、相手方保険会社との間で争いになり、傷害がなかったものとして慰謝料が発生しない可能性もあるため、痛みや違和感がある場合は病院を受診し、診断書を警察署に届け出るように心がけましょう。
こうすることで、物損事故から人身事故に切り替えることができます。
また、事故当日は痛みがなくても交通事故の場合は、後から痛みが出てくる場合もあります。後から痛みが出た場合でもすぐに病院を受診するようにしましょう。
保険会社に提出する診断書
適切な損害賠償を請求するために、相手方保険会社にも診断書を提出する必要があります。
損害賠償の請求方法は2種類あり、どちらの方法を選択するかで、提出先が異なります。
一括対応
加害者の任意保険会社が治療費を直接病院に支払い、自賠責保険に対し、自賠責保険の範囲内の費用について、任意保険会社が支払った費用を償還する方法。一括対応により、被害者は病院窓口で医療費を支払ったり、書類を集めたりしないでよくなります。
また、一括対応の場合は、診断書は病院から任意保険会社へ直接提出されます。
被害者請求
任意保険会社が一括対応をしない場合や、無保険の場合、被害者が直接自賠責保険に対し、損害賠償を求めることができます。これを、被害者請求といいます。
被害者請求をする場合は、自賠責様式の診断書と診療報酬明細書を病院に作成してもらう必要があります。
加害者が任意保険会社に加入しているのであれば、一括対応で請求するケースがほとんどでしょう。
一括対応では、相手方保険会社が病院から診断書を直接受け取るため、被害者は保険会社用の診断書を用意せず、同意書のみ提出することになります。
被害者請求の場合は書式指定があるため注意が必要
被害者請求とは、損害賠償請求のうち、自賠責負担分を相手方自賠責保険会社に直接請求することです。
被害者請求を行う場合、自賠責様式の診断書が必要です。事前に自賠責保険会社に連絡をし、被害者請求の書式を取り寄せると良いでしょう。
診断書の記載事項
- 傷病名
- 治療開始日・治癒または治癒見込み日
- 治療の内容・経過
- 検査結果
- 今後の見通し
- 受傷部位
交通事故の被害者請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
別の怪我が発覚した場合は再提出が必要
交通事故により初診のときに、診断されなかった傷病名が新たな検査等により発見された場合は、必ず新たな傷病名が記載された診断書をとるようにしてください。
一括対応の場合は、毎月診断書が病院から保険会社に提出されますので、あまり気にする必要はありません。
ただ、事故からしばらくしてから診断された傷病名については、事故との因果関係が争われることが多々あり、治療費が否認されてしまい、自己負担となる場合もあるので注意が必要です。
自賠責保険に対し被害者請求をした後に新たな怪我が発覚した場合は、診断書や診療報酬明細書を集めて、再度被害者請求をすることになります。
ただし、相手方の自賠責保険への損害賠償請求には時効があり、傷害分の費目では、事故の翌日から3年経つと請求できなくなります。
勤務先に提出する診断書
怪我が原因で休むときは勤務先へ診断書の提出が必要となる場合もあります。
勤務先へ提出する診断書には「怪我により就労が不可能である」旨を記載してもらうよう医師へ相談しましょう。
特に、診断書に指定の様式はなく、コピーで大丈夫な場合もあります。
後遺障害等級認定で提出する診断書
交通事故により後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けるための診断書が必要です。
後遺障害等級認定とは
交通事故による後遺症が自賠責法に定められた1~14級までの後遺障害等級のいずれかに認定されることを指します。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」を請求することができます。
この認定を受けるためには後遺障害診断書が何より大事です。
後遺障害診断書には様式が定まっており、保険会社から取り寄せて医師に記入してもらう必要があります。
後遺障害診断書は作成してもらう際に自覚症状についてしっかりと記載してもらう事がポイントです。
自覚症状はご自身でしか分からないため、診察時に医師に伝え漏れの無いようにしましょう。
後遺障害診断書の正しい書き方については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
診断書を提出しない場合のデメリット
診断書を提出しなかった場合、以下のようなデメリットがあります。
| 提出先 | デメリット |
|---|---|
| 警察 |
|
| 保険会社 |
|
| 後遺障害等級認定 |
|
診断書を提出しないのは被害者にとってデメリットでしかありません。
加害者から「診断書を提出しないでほしい」「診断書を取り下げてほしい」と言われても安易に応じないようにしましょう。
警察による実況見分調書が作成されない
人身事故の場合、警察は捜査の一環として事故現場で実況見分を行い、捜査資料として実況見分調書を作成します。
診断書を提出しないことで、実況見分調書などの詳細な刑事記録が作成されません。
詳細な刑事記録がなければ、事故の過失割合など相手方と意見が食い違った時に主張を裏付ける証拠が足りず、過失割合で争いになった場合、証拠がなく不利に働く場合があります。
適切な賠償金を受け取れない
交通事故で怪我をした場合、診断書を提出しないことで人身事故から物損事故として処理されてしまいます。
物損事故扱いのままでは、実況見分調書が作成されない、交通事故証明書が発行されないなど不利益があります。
保険会社が物損事故のままでも人身扱いにして賠償金を支払う場合もありますが、怪我の有無が争いになった場合や事故態様が争いになった場合には、人身事故として処理されていないことが被害者にとって不利益になることがあります。
自賠責保険の請求時に交通事故証明書を利用できない
自賠責保険には、交通事故証明書を提出する必要がありますが、物損事故では、交通事故証明書を入手することができません。
ただ、全く自賠責保険に請求できないわけではなく、物損事故扱いのまま、自賠責保険に治療費等を請求する場合には、交通事故証明書入手不能理由書を作成して提出しなければなりません。
加害者が任意保険に加入していない場合などは、自賠責保険に請求せざるを得ませんが、物損事故扱いにしたことにより、事故が軽微と思われ、怪我と事故との因果関係が否認されないとも限りません。事故で怪我をした場合は診断書を提出することをお勧めします。
診断書は取り下げることができる?
一度提出した診断書は基本的に取り下げ不可となります。
しかし、稀なケースですが、診断書を取り下げることができるケースがあります。
被害者の怪我が非常に軽いものである
病院に行くまでもないような擦り傷程度であれば人身事故ではなく物損事故として扱うこともあります。
警察の捜査が始まる前
実況見分や事情聴取など、警察の本格的な捜査が始まる前なら診断書を取り下げることができる可能性があります。
加害者側が取り下げを求める理由
加害者はなぜ診断書を取り下げてほしいのでしょうか。その理由を見ていきましょう。
刑事罰(前科が付くのを)避けたい
警察に診断書が出されると加害者は刑事罰を受ける可能性もあります。
刑事罰を受けることで就職や仕事に影響が出ることがあり、それを嫌がり診断書の取り下げを求めることがあります。
免許停止・免許取り消しを避けたい
人身事故を起こすと加害者は民事上の責任、刑事上の責任に加えて、行政上の責任を負う必要があります。人身事故になると免許の加点もありますし、ゴールド免許であればゴールド免許ではなくなります。
また、被害者の怪我が大きいほど点数は高くその分、免許停止や免許取り消しになる可能性も高くなり、診断書を出されたくないと求めるのです。
交通事故の診断書についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
交通事故に遭ったらほとんどの人は交通事故の診断書について分からないことだらけと思います。
「診断書のような医療的なことについて、弁護士に相談してもいいの?」と思われるかもしれませんが、お困りの方はぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士であれば診断書や後遺障害診断書についてもアドバイスすることができます。
後遺障害等級認定では後遺障害診断書の内容が非常に大事ですが、交通事故に詳しくなければ内容について的確にアドバイスすることは難しいことでしょう。
交通事故に診断書でお困りの方は、私たち弁護士法人ALGに一度お問い合わせください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
- 料金について、こちらもご確認ください。
-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。